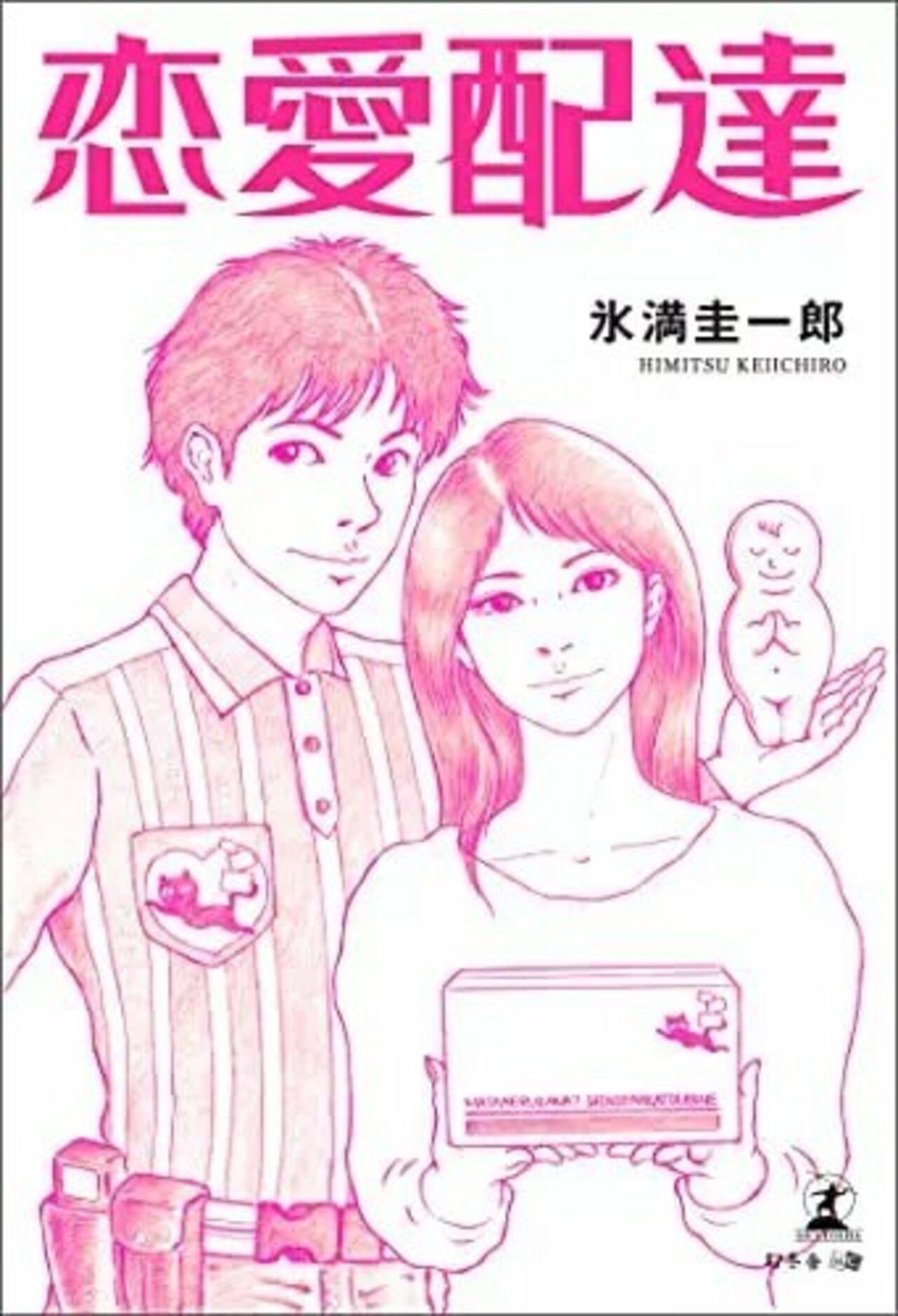高校二年のあの日、想い人に初めてここで出逢った。その時に詠んでくれた同じ和歌を彼に詠まれたことで自分の心は昔に遡ってしまっている。高校生に戻った橘は、
「古今和歌集の夏歌と伊勢物語の第六十段の花橘に収められた和歌ね。ではお礼に……
『橘の香をなつかしみほとゝぎす 花散る里をたづねてぞとふ』
これは源氏物語の第十一帖の花散里の巻で光源氏の詠んだ歌なの」
とあの時と同じように彼に歌を返し、ゆっくりと近づき彼の瞳をまっすぐに見つめる。
「私はあなたのことが好きだった。でもそれを今まであなたに言えなかった。あなたに言いたいことと聞きたいことを今日まで抱えてしまった。あなたが残してくれたメモ書きの、『ごめん、約束守れなくて、僕は――』の先はいったい何だったの……今でもそれが知りたくて」
先生の驚きの告白を聞いてしまった僕は、「えっ……」と自分の口から出かかったその先の言葉を慌てふためいて飲み込むしかなかった。その僕の口の中には、『僕は君のことが好きだ。でも今の自分は君を幸せにはできないから』という言葉があったからだ。自分の心臓の鼓動が一気に早くなり乱れていくのが僕にはわかる。
先生に向かって生徒の立場の自分がそんな言葉を口にしていたら大変なことになっていた。でもなぜ、自分がそれを先生に言おうとしていたのか理解できない。
いつの間にか二人の距離は一気に縮まり先生はすぐ目の前に立ち自分の瞳の中を覗き込んでいるが、そのあまりの近さに僕は驚いてしまう。間近で見た先生はほとんどお化粧をしていないのにどんな花よりも美しい。その美しさは悲しみを抱いて孤高となることで完成されたのだろう。
少しの間、先生に見惚れていた。その時を自分が独り占めしてもいいと思えてしまう。そよ風に髪を靡かせる先生はさながら自分と同じ高校生のようにあどけない表情でキラキラと輝いている。今なら先生ではなく彼女と呼んでも許される可憐な姿をしている。その彼女を見ていて、初めて美しいという言葉の意味を知る。間違いなく美しいのが彼女で、この世界で彼女だけが美しいのだろう。
よく見ると葉先にできる花の露が彼女の瞳の睫毛の上でユラユラ揺れている。瞼を閉じてしまえばそれが涙の糸に変わってしまう。……それも時間の問題だろう。それは夕陽に輝く真珠を思わせる透明度の高い今まで見た中で最も美しい花の露。おそらく彼女の想いがその露を美しく形作っているに違いない。