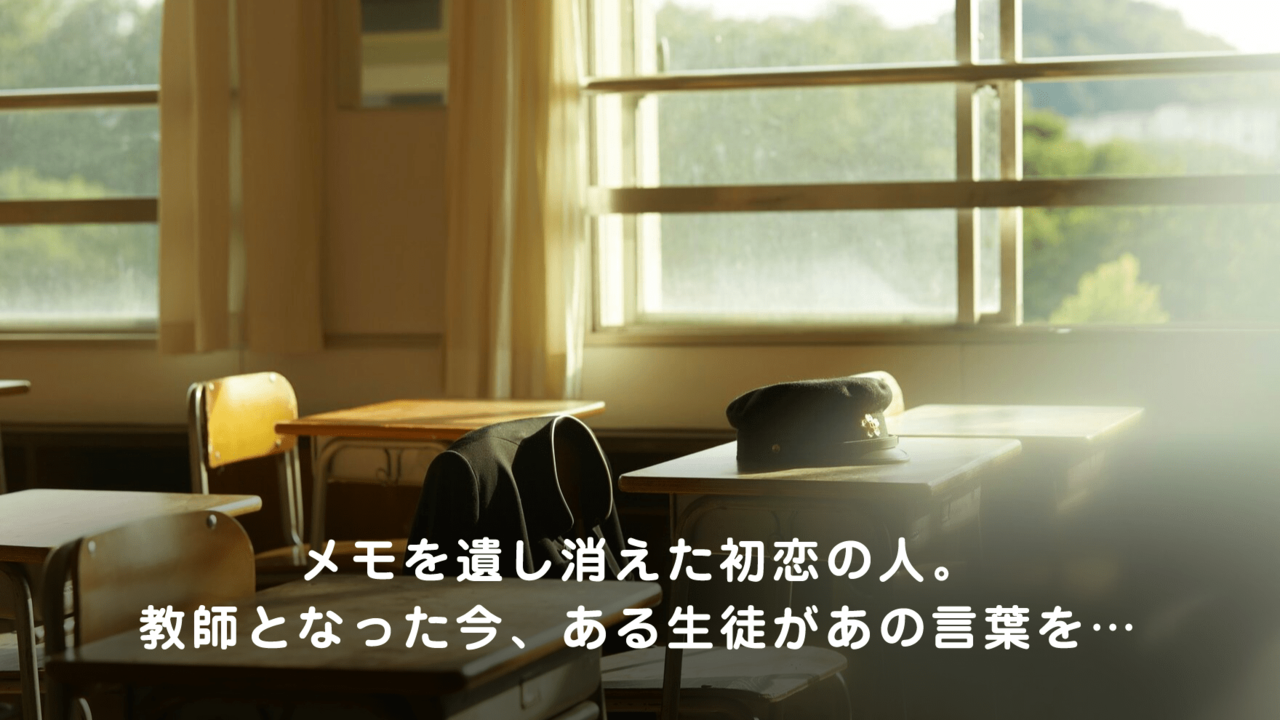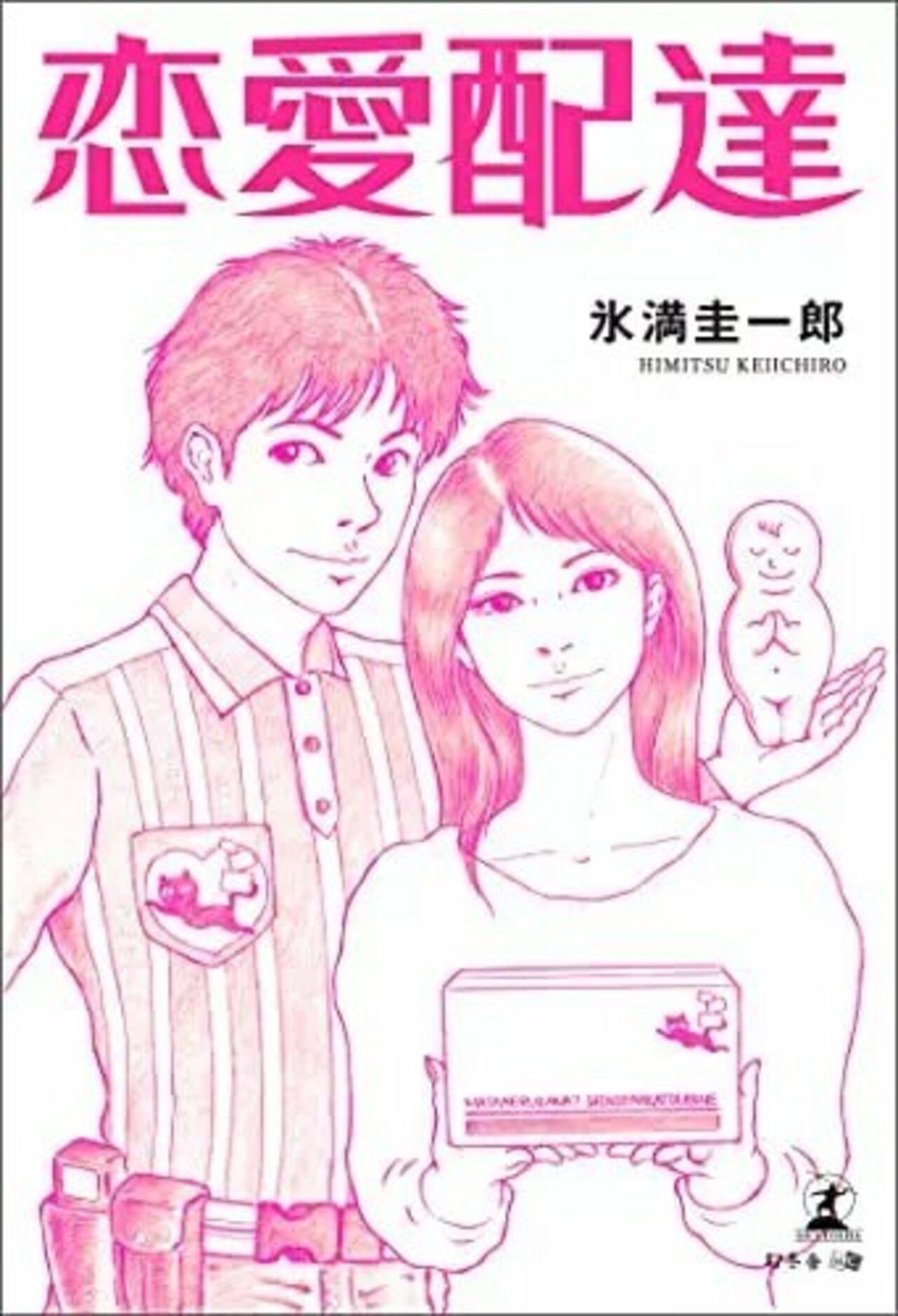第二 雑歌の章その二
誰そ彼
そういえば、そこには母親と綺麗なお姉さんと自分が一緒にいた気がするが、他にも誰かがいたような……母親に似た女性と自分と同じぐらいの女の子の姿が記憶の中をぼんやりと過っていくがはっきりとはせず、ただ漠然とそんな気がしていた。
彼の母親の優海は時間があると、幼い彼を連れて自分の母校にあるこの花壇を訪れて熱心に花の手入れをしていた。花壇の真ん中に設置されているのは優海たちの学年が卒業記念に寄付していった花時計。幼い頃の彼は飽きもせずに持参したサンドイッチと麦茶を口に入れ、母親の花の手入れや植え替えを手伝い大好きな花時計を一日中眺め過ごしていた。
まだ橘がこの高校の学生だった頃、優海から花壇の手入れの仕方を習った。彼のことは幼い頃から知り面倒をよくみていた。また優海たちの寄付で花時計ができたことも当然知っていた。
「なんとなくは覚えているんですけど」
と僕が言うと、
「君はまだ小さかったから仕方ないけど。あの時の君が大きくなってまた一緒にいるのはなんだか……不思議よね」
と言いながら目の前にいる制服姿の彼の中に恐らく潜んでいるはずの想い人を探していた。
だが、驚いたことに彼も熱いまなざしで自分を見つめ返してくる。そのまなざしは彼本人のものではなく、自分の求めている人のものだと……感じる。突然視線を自分から外した彼は夕陽を眺めながら徐に、
『五月待つ花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする』
と和歌を諳じた。それを聞いた途端に花壇の花時計は逆回転を始め時はどんどん遡ってゆき、その刹那自分も彼と同じ制服を着た高校生に戻れたと橘は思った。同時に想い人の存在を彼の中に確信する。
今だったらやり直せる。あの時の初恋の相手に告げられずにいた気持ち、あの日約束した図書館でいくら待っても来なかった人、自分を残してこの世界から突然消えてしまった人……。
『ごめん、約束守れなくて、僕は――』
とだけ書いて残した、たった一枚のメモ書き。その辛い想い出を残して自分の花時計はそこで止まったままになっている。