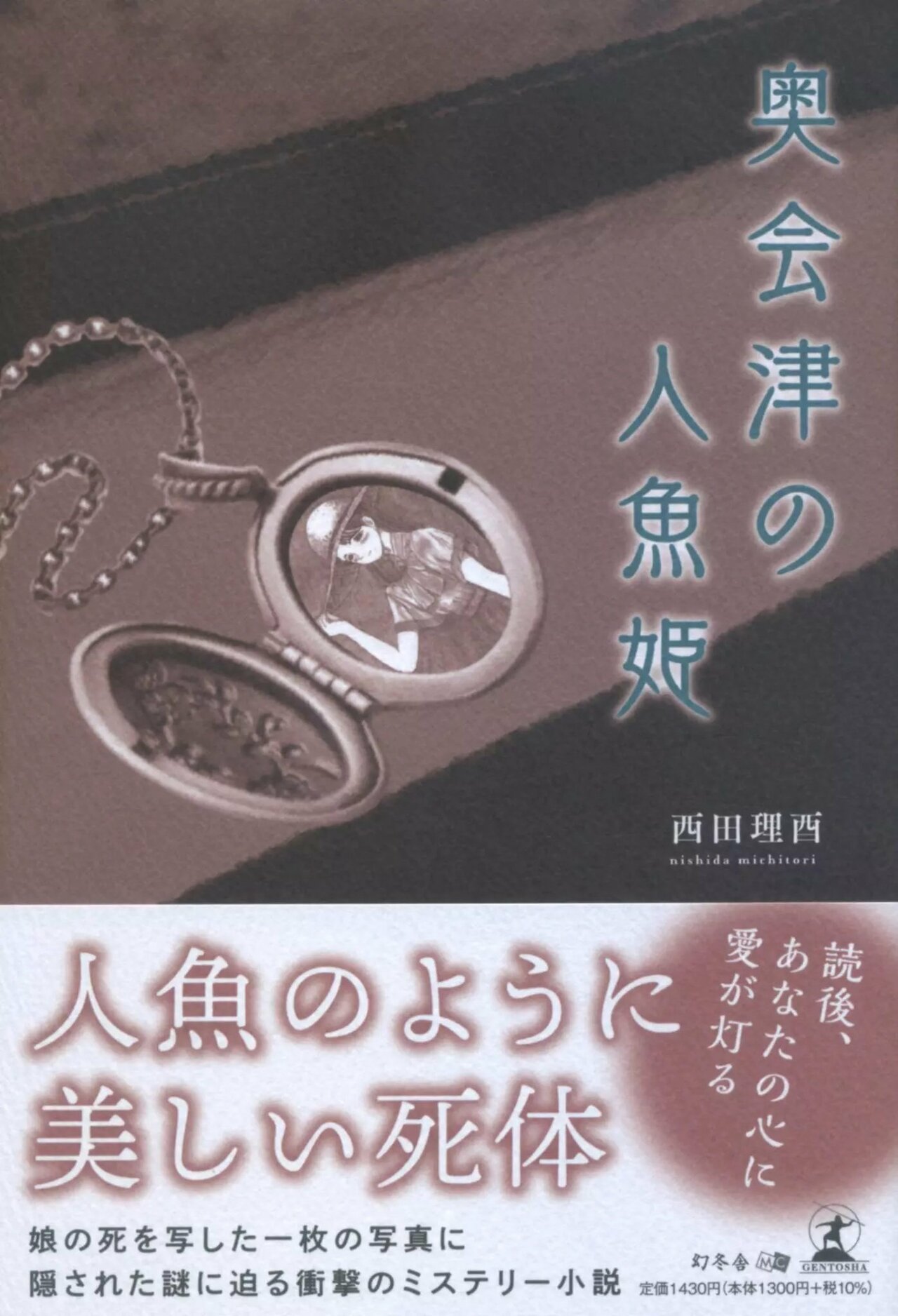「俺に対しては相変わらず冷たい態度を取り続けていた汐里だが、これは俺なりの汐里に対する贖罪の気持ちの表れでもあった。だが車の代償として汐里から返ってきた言葉は『こんなことで、私が味わってきた苦しみを消せるとまさか思ってないよね?』だった。乙音が自分のことのように喜んで、汐里に代わって俺に何度もお礼を言ってくれたのに対して、最後まで汐里の言葉は辛辣そのものだった」
そこで千景はひどく悲しそうな顔で座卓の角のあたりに視線を落とした。汐里との和解がもう永遠に叶わなくなってしまったことを、いつまでも悔いているような千景の様子に、鍛冶内の胸は痛んだ。
その時、遠くから誰かが歩いてくる足音が聞こえてきた。就寝前に、おやすみの挨拶をしに来た乙音だった。旧友の二人は、テーブルにほっておかれていた盃を慌てて手に取ると、ほとんど入っていない酒の滴を口に運んだ。
「あまり遅くならないうちにちぃちゃんを寝せてあげてくださいね、おじさま。お医者さまからも、きつく言われているんです」
「あ、ああ、気をつけるよ、乙音ちゃん」
奥会津の夏は、昼夜に温度差がある。昼は暑いが、夜風が吹き込む頃になると、肌寒さすら感じる時がある。都心のヒートアイランドが体の奥深くにまで染み込んでいる鍛冶内にとって、めぶき屋の心地良さは、障子越しに吹き込んでくるかすかな風が肌に触れる時の、些細な違和感の中にも感じることができた。
「前置きの話に長々付き合ってくれて感謝するよ、鍛冶内。一晩かけてもっといろいろな話をお前としたいと思っていたが、乙音が奥で俺の就寝時間を気にしているのは間違いがない。ここいらで、俺が頼みたいことの中身を話すよ」
「ああ」
千景はそこで激しく咳き込んだ。鍛冶内が背中をさすったが、咳はなかなか治まらず、やっと終わった時には、千景はぐったりとしていて、しばらくは話もできない状態だった。心配した鍛冶内が、話は明日聞くからと言っても千景は聞かなかった。