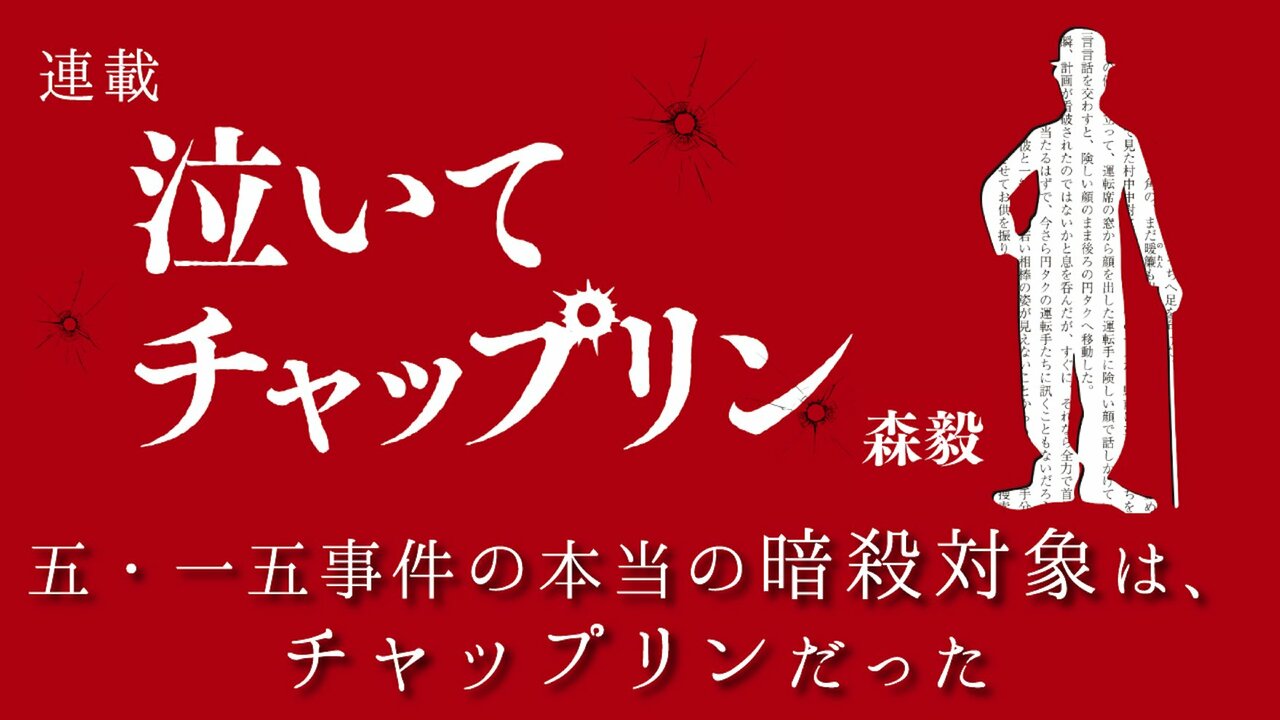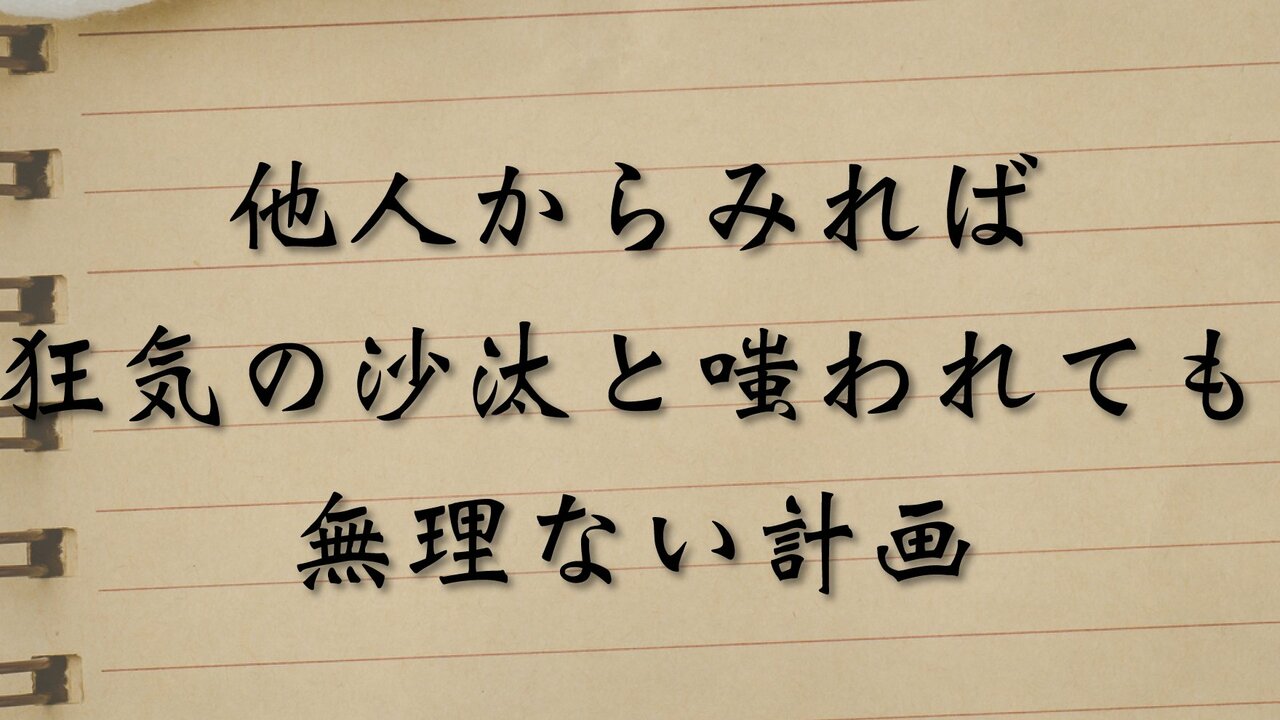彼の原隊(本来の所属部隊)は歩一だったが、去年の十月、参謀本部や陸軍省に勤務する佐官クラスの中堅将校を中心に結成された秘密結社《桜会》による、やはり陸軍の改革と国家改造を謳った軍事クーデターが直前に発覚し未遂に終った事件、いわゆる『十月事件』後に自ら望んで陸士に転補したのだった。
また、その十月事件の収拾と事後処理のイニシアチブをとったのが、そのときは教育総監部長官であった荒木貞夫(あらきさだお)中将だったが、それがその後の士候等の過激な活動にすくなからず影響を与え、結果的に田島をそうした行動に奔(はし)らせたのだった。
というのも、陸軍は明治の建軍以来実権は維新の功労者の一人、山県有朋(やまがたありとも)が築いた権力構造を継承する長州(ちょうしゅう)出身者、いわゆる『長閥(ちょうばつ)』に一手に握られていて、陰では「陸軍は長州の陸軍」と囁かれ、軍内部には不満や怨えん嗟さの声が渦巻いたのであるが、その山県有朋にもヒケをとらない野心家で東京生まれの荒木中将もまた、そんな不満を胸に秘めた一人であった。
が、良くも悪くも野心家の荒木は、ただ不満を口にするだけではなく、そんな陸軍を改革するための人脈を持ち前の弁舌を駆使して精力的に築いていた。
そのために彼は、保身に汲々としている長閥の幹部たちを陰では「ダラ幹」と呼んでいる青年将校等とも気軽に酒を酌み交わし、政党政治を否定している彼等の革命的な国家改造論にも耳を傾けると同時に、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」という帝国憲法第十一条を金科玉条とし、帝国を皇国、国民を皇民、国軍を皇軍、人道も皇道と誇称するなど、狂信的ともいえる尊皇思想をもって長閥に対抗するための、いわゆる「皇道派」を形成し、勢力の拡大を図っていた。
そんな折りも折り、軍首脳陣を慄然(りつぜん)とさせたこのクーデター計画が発覚し、一物(いちもつ)が縮みあがり、周章狼狽(しょうろうばい)する「ダラ幹」にかわって、彼等青年将校に「話の分かる閣下」と期待されている彼に事態収拾のお鉢がまわってきたというわけだった。
むろん、荒木はチャンス到来とばかりに、参謀本部に勤務するクーデターの首謀者、橋本欣五郎(はしもときんごろう)中佐と長勇(ちょういさむ)少佐が潜んでいる築地の料亭《金龍亭(きんりゅうてい)》に、やはり参謀本部に勤務する腹心の佐官三名を従えて乗り込み、二人の説得にあたり、曲がりなりにも無事その務めを果たしたのだった。
がしかし、これが公になり、「皇軍」の威信にキズをつけぬためという大義名分をもって、《桜会》の主要メンバー十数名を地方の師団や連隊に飛ばすなど、処分とは名ばかりの軽い行政処分をしただけでお茶を濁し、真相究明もすることなく事件を内々に処理したのだった。
心ある者からは「臭いものに蓋をしただけ」という論難非議(ろんなんひぎ)はあったが、それを契機に彼は、軍中枢部はむろん地方の師団や連隊の人事にまで容喙(ようかい)し、「長閥の陸軍」を「皇道派の陸軍」、すなわち厳格な天皇制を堅持し、陸軍が率先して近代国家建設にあたらんという自負と野望を秘めた、いわゆる「昭和の帝国陸軍」に変えていった。
たとえそれに異をとなえる者があっても、相手が陸相であろうと参謀総長であろうと、自慢のカイゼル髭をしごきながら
「それではまた若い者が承知しないと思いますよ」と、クーデターの再発をほのめかす一言で一蹴(いっしゅう)した。
また彼は、その後も青年将校等との交際を怠らなかったが、人間上り調子のときには時勢も味方するもので、二カ月後の前年十二月の犬養政権誕生にあたり、その実力(?)を買われ陸相に抜擢されたのだった。
もっとも、たとえ荒木のその処置が姑息な懐柔策にしろ、陸軍の教育総監長官という立場を弁(わきま)えず、過激な青年将校と必要以上に親しく接している荒木中将の入閣については、
「若い連中を諫めるどころか、逆に、ご機嫌取りをして増長させているようなあんな男を、本当に陸相にしてもいいんですか?」と、危惧する政権内の声もないではなかったが。
「それじゃあ、ほかにだれか若い連中を抑えることができる者がいるかね? 毒は毒をもって制す、邪を禁ずるに邪を以てすともいうだろう」
と、犬養首相は苦笑いしたといわれていたが、それが大きな間違いだった。首相自身にとっても帝国日本にとっても。
が、たしかにそれを機に《桜会》は消滅し、佐官クラスの、いわゆる中堅将校等の過激な活動は抑えられたものの、逆に尉官クラスの青年将校や士候等は、荒木新陸相の姑息な事件処理を、「話の分かる閣下」が自分たちの活動を理解し容認している証ととらえ、より過激に活発になっていった。ことに二十歳前後の若い士候等は、それが顕著だった。
で事件の翌月、田島は士候等の頭を冷やすため陸士へ転補したのだった。
とはいえ、それにはそれなりの資格や、それ相応の推薦、つまりコネが必要だったが。
「なに、陸士を首席で通したきみは、その資格にはまったく問題ないし、私が直接口利きをしたわけでもないし、親父にしたって、本庁(陸軍省)の補任(ほにん・人事)課長の松井大佐に電話を一本入れただけで、尽力したというほどのことではないさ。
しかも、きみは知らないかもしれないが、これも天の配(はいざい)剤というか、その補任課長の松井大佐は、親父が陸士の区隊長をしていたときの生徒だったから否(いや)も応(おう)もなかったからね」
と、山内大尉は事もなげにいって笑った。
「は、それは松井大佐殿にも転補のお礼に伺ったときにお聞きしました……ですが、あまりいい顔はされませんでしたが」
と、田島は苦笑した。
「だろうな。本庁のお偉方の目には、きみも危険人物の一人と映っているだろうからな。
しかし『君子は豹変す』とはいうが、きみが正真正銘の危険人物になったとなると、私も悠長に笑ってコーヒーを飲んでいる場合ではないな」
と山内大尉は、手にしたコーヒーには口もつけず机にもどした。
田島は答に窮しているように口許を引き締めた。
深い沈黙が部屋を支配した。
田島は山内大尉の口がひらくのを辛抱づよく待った。
柱時計の時を刻む単調な金属音が、凝固した部屋の空気に反発するようにリズミカルに響いていた。
が、やがて大尉の鼻から長い吐息が静かにもれた。
「それにしても、『士別れて三日』とはいうが、どうしてそういうことになったのか納得できるよう説明してもらえるかな。話によっては、私も腹を括らねばならんからな」
と、大尉はポンと腹を軽く叩いて笑った。
「むろん大尉殿にはお話ししなければと思い、失礼をも(かえり)みず突然お訪ねした次第です。ですがそのために後日、大尉殿に、延(ひ)いては要職におられるお父上殿にも、あらぬご迷惑をおかけすることにもなりかねませんので、大尉殿にお目にかかるのも、まことに勝手ながら、今夜かぎりとさせていただきますことを先にお詫びしておきます。今ここへ来る時も、お供が二人いましたので、村中くんに手伝ってもらって撒いてきたような次第ですので」
「どうやって撒いてきたか知らないが、そんな気遣いは無用だ。第一、憲兵隊に睨にらまれているのは、きみより私のほうが先なんだ。それに親父だって、日本が今のままでいいとは思ってないし、憲兵隊など屁とも思ってない男だからね。そんな心配は一切無用だ」
と、大尉は鷹揚(おうよう)に笑った。
が、田島は神妙な顔で応えた。
「はあ、しかし今回のその計画というのは吾ながら少々夢想的というか、他人からみれば狂気の沙汰と嗤(わら)われても無理ない計画ですので……ですが、それをお話しするまえに、私の独断専行を重ねてお詫びいたしておきます、いえ、これまでの格別なご厚誼(こうぎ)を思えば、お詫びしてすむことでないのは重々承知しておりますが、私など、所詮(しょせん)縁のなかった赤の他人だったとご容赦ください」
「容赦するかどうかはきみの話を聞いてから考えるさ。しかし今もいったように、いかに『君子は豹変す』るとはいえ、これまでは士候等が暴走することを抑えてきたきみが、突然百八十度方向転換するというのは、どういう風の吹きまわしかな?
無論きみのことだから、ミイラ取りがミイラになったとは思えないし、熟慮に熟慮を重ねたうえでのことだろうが、あまりに唐突な話で、きみか私のどちらかが狐に化かされているんじゃないかとでもいった気分だ」