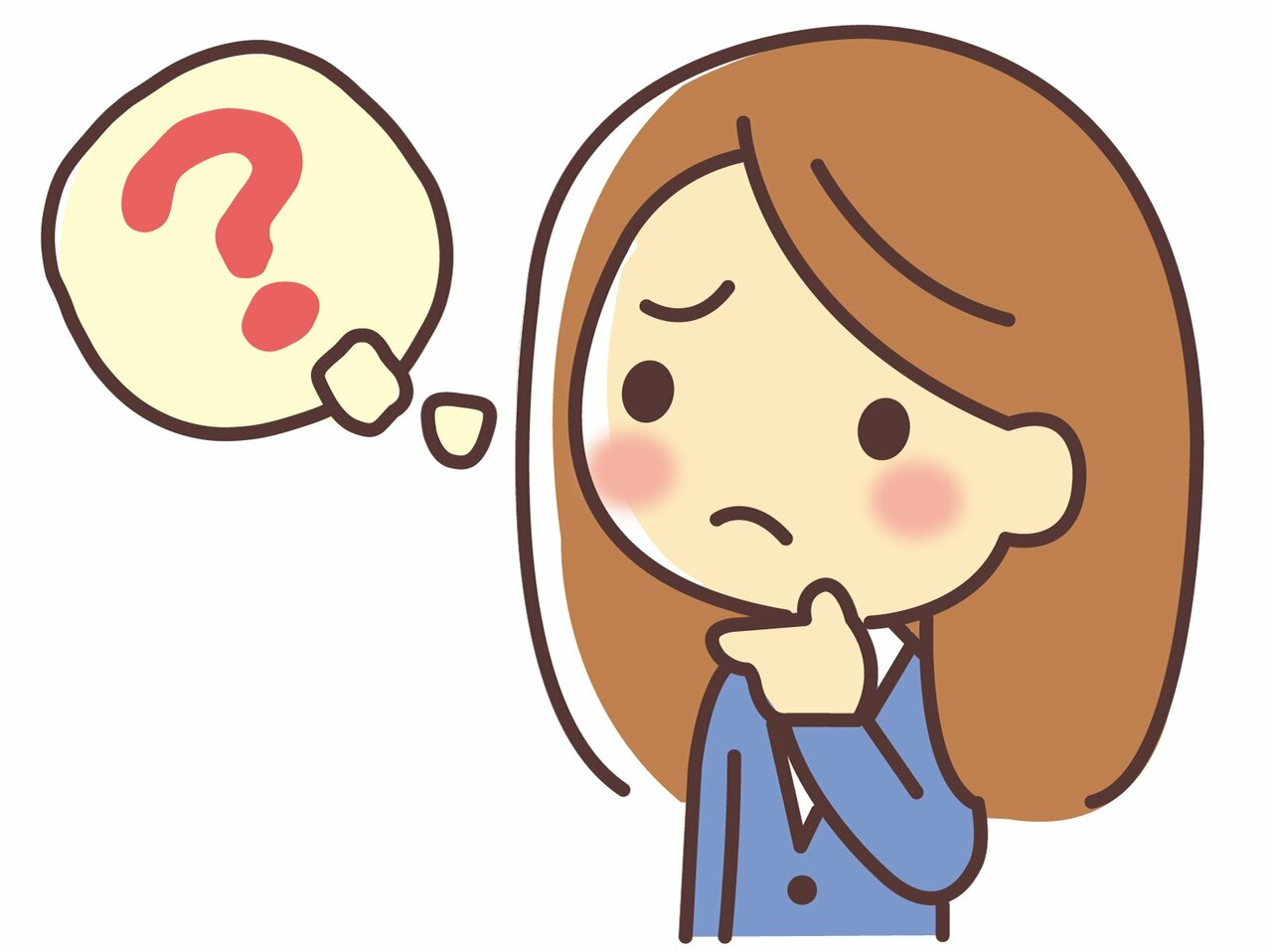英介の片方の耳のわずかな聴力が頼りの会話でしたが、なんの支障も感じることはなく、自然体で笑い合える時間がなによりも心地よいと思っていたようです。穏やかに、こんなにも幸せに過ぎていく日々がありがたく、また家族が増えたことで子どもとともに成長していく日常のすべてに、誠子は夢中になっていました。
英介も子どもとの時間を大切にしていましたし、誰の目にも、微笑ましい家庭に映っていました。けれども、少しずつ少しずつ、何かの影が忍び寄るように、何かがよじれ始めていました。仕事上のつまずきで英介はふさぎ込むようになり、家族と過ごす時間よりもひとりきりで部屋にこもったり、休日もひとりで出かけることが多くなっていました。
いつしか、誠子と視線を合わすことさえ避けるようになった英介のことを、誠子は誰に相談するでもなく、ひとり悶々としていました。
英介さん、どうしちゃったんだろう。なぜ、なにも話してはくれないのだろう。仕事でなにかあったのかな。それとも、わたしの何かが気に障っているのかな。
家族で楽しそうに写っている1枚の写真を見ながら、誠子はぼんやりとするのでした。さて、英介にいったい何があったのでしょうか。仕事でのミスが続き、穏やかで優しい英介は、自分の聴力の負い目を必要以上に自責し、罪悪感に陥っていたようです。その憂さはらしに初めて、ギャンブルに手を出したのです。
ある休日、誠子は母親に来てもらい、子どもと留守番してくれるよう頼みました。英介が出かけた後を、尾行してみようと思ったのです。ちょっとドキドキする誠子。英介は繁華街へと向かっていました。思っていた以上の人混みだったので、英介に気づかれることなく後を追うことができました。
英介はとあるお店に入っていきました。今でいうパチンコ屋の走りの時代でしょうか。誠子は恐るおそる、中をのぞいてみようとしましたがよく見えず、入り口を入ったものの、すぐに外へ出ました。お店の入り口が見える場所を探して、英介が出てくるのを待つことにしたようです。
待つこと数時間、なんと英介は女性と連れ立って出てくるではありませんか。なにやら楽しそうに会話している様子を見て、英介の笑顔を久しぶりに見た誠子でした。誠子は隠れるようにして人目を避け、その場から離れました。どうやって家にたどり着いたか記憶が定かでないほどに、誠子は動揺していました。