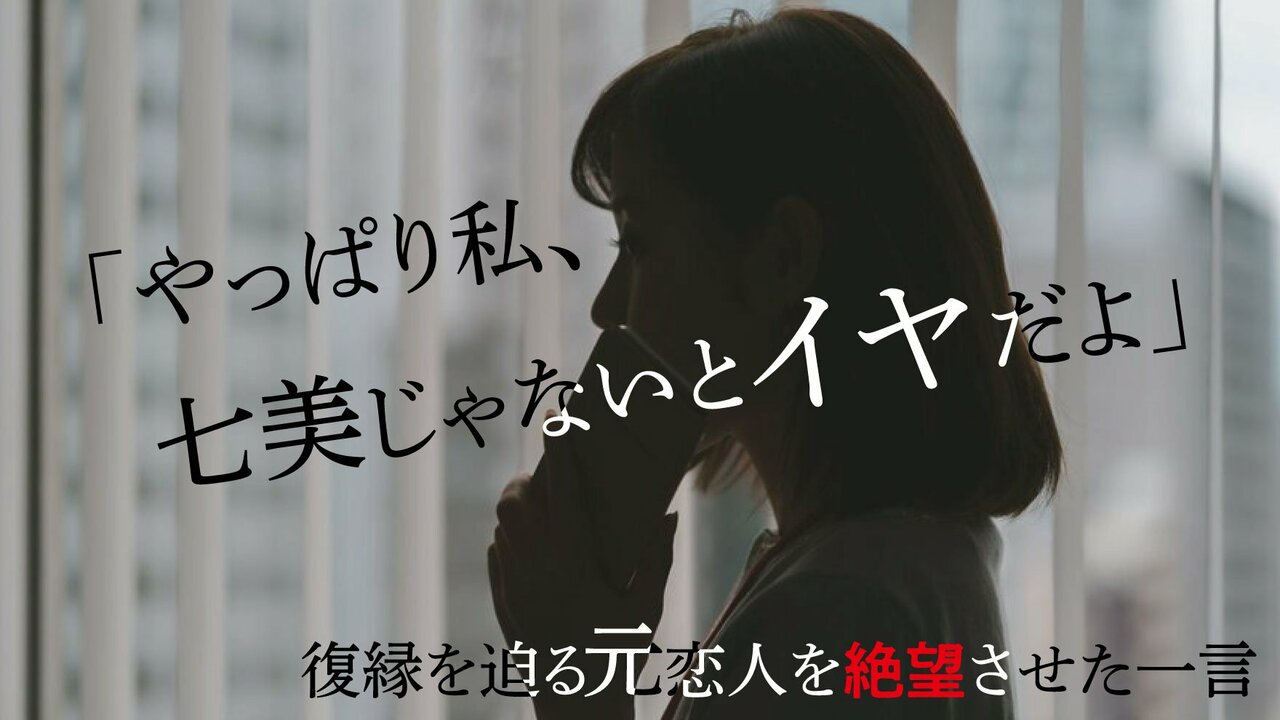同じ名前の鳥が鳴く
田所さんと私の家は反対方面のため、それぞれのホームへ見送り合う。最終から一つ前の電車に乗り込み、喜びと猜疑心を複雑に混ぜ合わせて座席に身を委ねた。健康意識の高い両親は、おそらくもう床に就いているだろう。
ぼんやり考えるうちに乗車時間の約二十分と徒歩数分の時間は過ぎ、玄関だけが明るいままの家の扉を開けた。前の恋人用に設定した着信音が鳴り響いたのは、自室に鞄を置いた次の瞬間だった。
彼女からの着信は、別れてからもできるだけ受けるようにしていた。けれど自分からは決して掛け直さない。それは暗黙の了解だった。
「やっぱり私、七美じゃないとイヤだよ」
彼女から復縁を迫られるのはこれで三度目だった。一度目、私は憤怒した。浮気みたいなことして自分勝手に離れておいて何を言うんだ、と思うままに言葉をぶつけて通話を切った。
次の日の朝、携帯の画面に溢れる彼女からの謝罪通知を見て、私は彼女を許すことにした。そうすることで、彼女の中にいる私を優位で善良な存在へ近付けようとした。二度目の提案のとき、彼女は電話口で泣きじゃくっていた。また思わせぶりなことをして恋人を怒らせて振られたのだろう。
大方予想はついていた。ゆえにそれを宥めて理由を聞いてあげることで、私は彼女にとっての絶対的な存在であり続けた。そしてその事実は、私をこのうえない優越感に浸らせた。
「ごめん、新しい恋人ができたの」
三度目にして、ようやく最も無難な理由を述べることができた。彼女が電話越しに息を呑むのがわかる。私はできるだけ上手にこの時間をやり過ごしたかった。
「どんな子?」
彼女の声は震えていた。そこに予想外の打撃を加えなければいけない状況は、恐怖というより憂鬱そのものだった。彼女が持っている私の表象は、これからあっけなく崩れ落ちる。私は深呼吸ではなくため息を吐いた。
「優しくて、真面目な、男の人」
人が言葉を失う瞬間は目以外の器官を通して伝わってくるものなのだと、そのとき初めて知った。私はテストが近いことを盾に一方的に通話を終了させた。彼女から電話が掛かってくることはもう一生ないのだろうと思った。