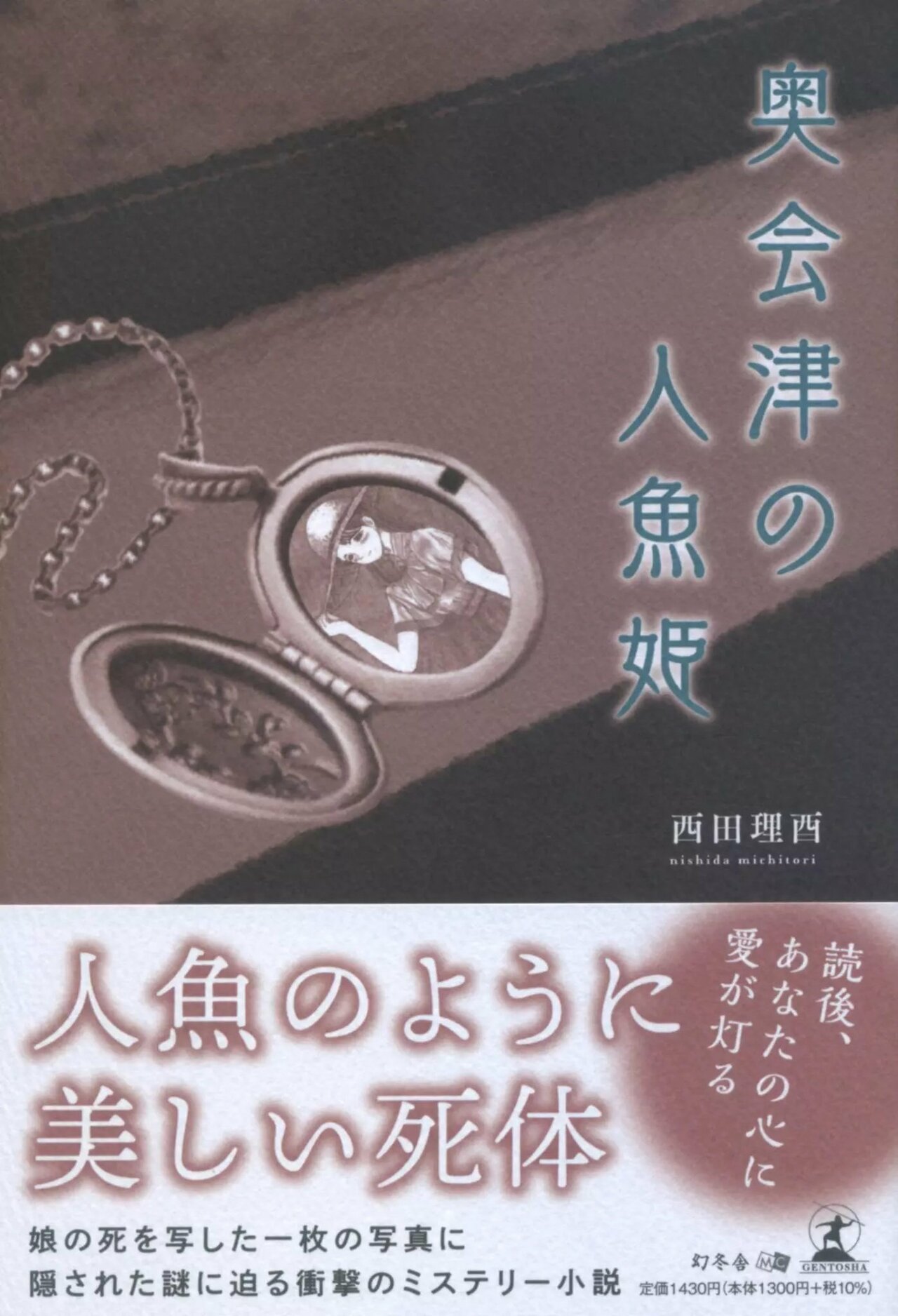この写真が誰の目にも触れずにこのままこの世から消え去ってしまうことに、言葉にならない寂寥感を感じながら、鍛冶内はせめて自分の中に記憶として留めておくことが死者への供養ででもあるかのように、ただ一心不乱に写真を見つめ続けていた。
「紅葉の葉は、写真の演出上、乙音が加えたものだが、それ以外はほぼこのままの状態だった。撮影を終えた後、俺と乙音は汐里を引き上げて、無駄だとわかっている蘇生措置を施した。でも汐里が再び目を開けることはなかった」
「まるで乙音ちゃんが、水の中に横たわっているようだ。写真では細部まではよくわからないとしても……確かによく似ている。さすがは双子だね」
「ああ……。誰もがそう言うよ。双子の中でも、特に乙音と汐里はよく似ていた。乙音の唇の右下にあるほくろ以外に、見分ける術がないくらいに」
「では汐里ちゃんが亡くなって、さぞかしお前も悲しんだだろうな」
「いや………………。正直ほっとした」
そう言った千景を、鍛冶内は驚いて見た。
千景は、苦々しさを噛み潰したような表情をしながら、こんなことをポツリと言った。
「その実、俺は汐里が嫌いだったからな」
目を大きく見開いている鍛冶内に、千景はさらに驚くべきことを告げた。
「お前に頼みたいのは、さっきまでここにいた娘が本当に乙音かどうかなんだ」