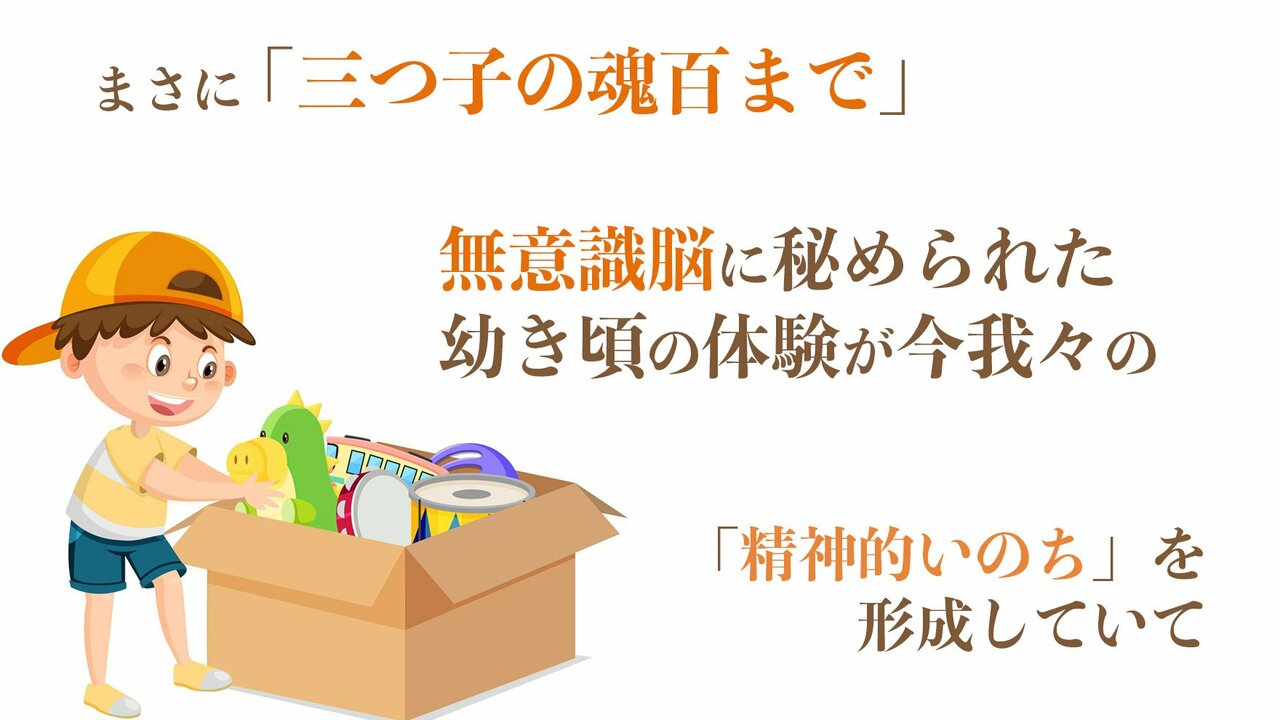2 大自然の営み
(1)生命の創造・進化
「原始の海にあったタンパク質やDNA、RNA、糖などが集まって、油でできた細胞膜で覆われた粒子が生命のもととなり、それが分裂を繰り返すようになったのです。――中略――このように生命の祖先と思われる細胞は一つの小さな粒子、独りぼっちの単細胞でした。ちょうど大腸菌や細菌のようなものでした」(岡田安弘著『生命・脳・いのち』東京化学同人1996)。
これは、40億年前に地球上に生命のもとになる細胞体が生まれたときのことを、今を生きる科学者が「こうではなかろうか」と描き出した推論です。無機物質から生命体がどのようにして誕生してきたのか、確かなことはまだ誰にも分かっていないのです。
まず何よりも、地球はどうして生まれたのか、細胞のもとになるタンパク質やDNA・RNA・糖・細胞膜等々がどうやって出現してきたのかという問いに対して、現代を生きるわたしたちにできることは、「こうではなかろうか」という推論だけなのです。ましてや、わたしたち人類の知恵でそれらのものを創り出すことはまだまだできないのです。
しかしながら、それでも45億年前に太陽のかけらの一つとして誕生したといわれる灼熱の地球(太陽から分かれたときには地球も高熱の物体であったといわれている)に、今こうして数限りない生物が生息しているという現実を、わたしたちはどう考えたらよいのでしょうか。
そこには、無機物質から生命体を創り出した何ものかが存在するはずです。その難題を実際にやり遂げてきた誰かが存在することは確かです。もちろんそれは、人間誕生ののちに人間の精神の内に思い描かれた“something great”(神とか)の所業などではないでしょう。
実はそれこそが、万物を生み成した大自然“Mother Nature”のナチュラルな営みなのです。ナチュラルな営みとは、自ずからにしてそうなってゆくという自然の摂理のことです。
“Mother Nature”の“Mother”という言葉を英和辞典(ジーニアス)で調べてみると、「〔……の〕源、起源」という訳が出てきます(図表2)。つまり“Mother”とは、すべての物・物事が「そこでできた」、「そこから生まれ出た」という源を意味する言葉であるということです。
そのことから考えても、大自然とは「万物を生み成した母なる自然」であるという解釈が成り立つものと考えられます。この場合の生み成すという言葉は、動物の分娩の生み成すではなく、自ずからにしてそうなってきたという解釈が適切なのかもしれません。万物を自ずからにしてそうならしめた“Mother Nature”の営みには、人知の及ばない奥深いからくりが秘められているようです。
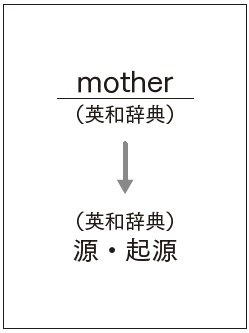
アメリカの生物学者スチュアート・カウフマンは、その著『自己組織化と進化の論理』(米沢富美子監訳日本経済新聞社1999)で、「分子生物学の驚くべき発展により、いまではこれらの自己複製的な分子系――合成された生命――を実際につくり出すことを、イメージできるようになった。私は10年か20年のあいだにそれが達成されることを信じている」と述べています。生命が人工的に創られるようになるだろうということです。
しかしながら、無機物質から生命を創り出すという営みは、人知を遙かに超えた営みだということでしょうか、スチュアート・カウフマンの論述から二十数年経った今でも、人工的に生命を創り出したという話は聞いたことがありません。
40億年前に大自然(自然の摂理)が成し遂げた生命創造のからくりは、まだまだ人間世界では「こうではなかろうか」という推論に過ぎない状況にあるようです。
人類の科学技術がもっともっと進化して、いつの日か物質と精神の融合地点(接点)まで観察できるようになったときに、ひょっとしたら無生物から生命体への明確な原理が見えてくるのかもしれません。そのときには、物質在り・精神在りの二元論ではなく、物質と精神は一連の自然現象として捉えることができるものと考えられます。