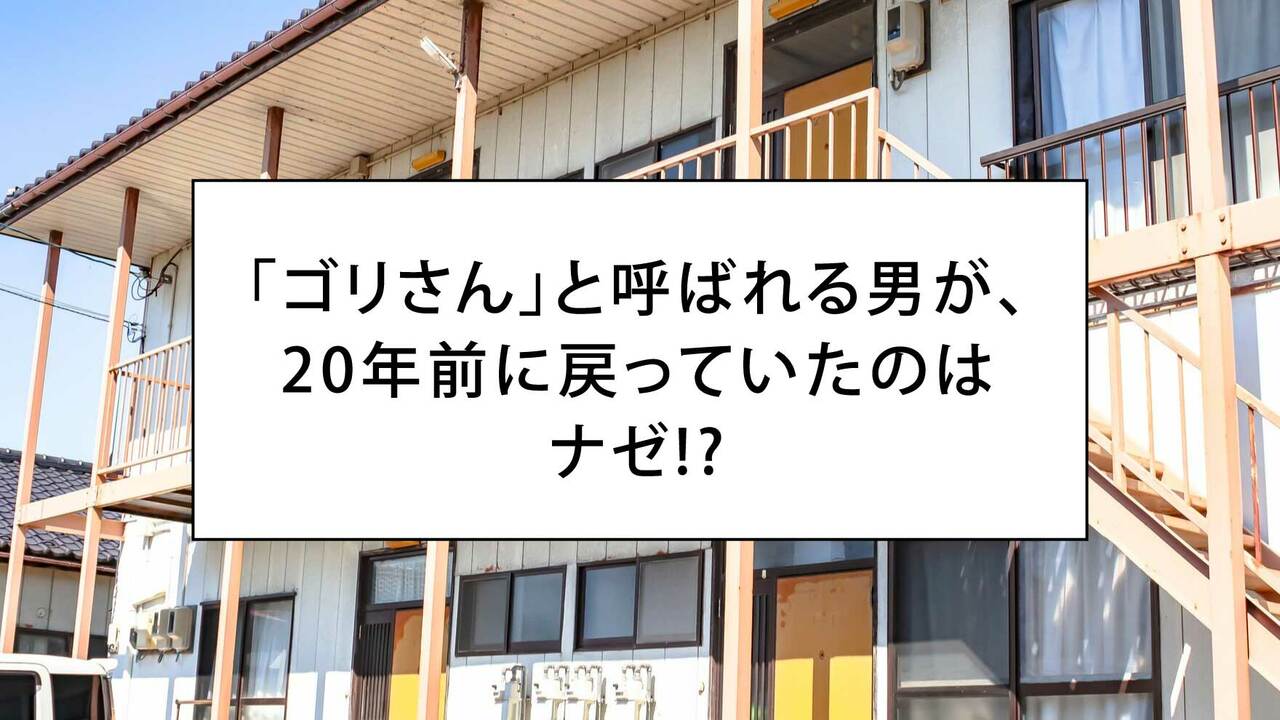実際ここの会社は、二十年前としては珍しい就業形態で、一応午前八時から午後五時という、いわゆる〈定時〉というものはあるのだが、午前八時から正午までの間に出社すれば良い、というフレックスタイムを採用していた。
しかしその一方で、毎月残業時間が百時間を超えることも珍しくない、今ならばブラック企業と呼ばれてしまうであろうほどのハードワークだったのだ。
「すみません、今日はそうさせていただきます」と言って俺は席を立った。
帰り支度をして外に出ると、この当時俺が乗っていた二百五十ccマニュアルミッションのバイクが、会社の駐輪場に置いてある。
何故か【車を買う】程度の贅沢が出来ないどころか、たまに食費にも困ったりする月があるほどに家計が逼迫していたので、せめて大好きなバイクくらいはと、ちょっと無理して買ったんだっけ。
ズボンのポケットから、キーホルダーに付けられた鍵束を取り出す。バイクのキーは、確かこれだよな。
バイクのイグニッションにキーを差し込んで回し、スターターボタンを押す。キュルキュルッとセルの回る音がして、バイクのエンジンがかかった。
俺はメットを被り、バイクに跨る。クラッチレバーを握り、ギアを一速へ入れアクセルを開け、クラッチをミートさせてバイクを走らせた。
記憶では、この当時住んでいたのは、バイクで十分ほど走ったところにある、六畳一間のアパートだ。
学生時代、親に反抗する気持ちはあったのだが、気が小さかった俺はグレることも出来ず、ただ周りの大人の言うことを聞いて真面目を装っていた。
そんな俺が、ささやかながらの反抗心で、高校を卒業すると同時に親元を離れ、一人暮らしを始めたのだけど、実家暮らしがいかに恵まれていたのか、実際に一人暮らしをしてみて身に染みたことを思い出す。