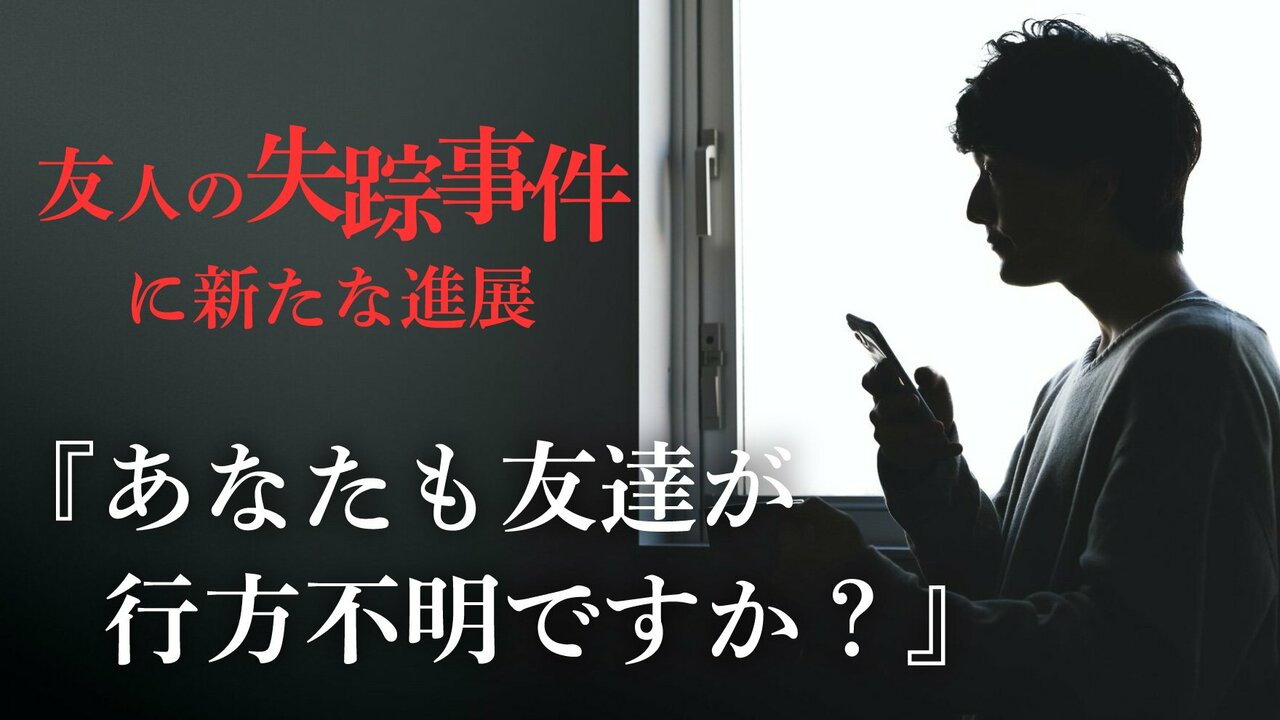2
「伏見警部補、また何か、怪しげなものを調べてるんですか?」
山城警察署の殺風景な刑事部屋の一角。眠気を隠しきれない目で、頬杖をついてパソコンのモニターを見る伏見に、谷山修一が言った。
「怪しげって言うけどな、遊んでるわけじゃないんだぞ」
伏見靖は、眠気で三重になった目を向けながら言った。
こういったやり取りは、この二人の間では珍しいものではない。
伏見は、山城警察署捜査一課の警部補で、年齢は31歳。サラサラした長めの髪をセンターで分けており、スーツは着るものの、ネクタイは締めない。目は鋭く、二重で、綺麗に髭を剃り上げたその顔は、イケメンの部類に入るだろうが、本人の中ではどうでもいいことと認識されている。見た目がいいのにやる気は見えず、有能な刑事ではあるものの、正義感に燃えるタイプでもなければ、切れ者というタイプでもない。
そんな伏見だが、ある特定の要素が絡む事件については、やる気を出す。
「そっちばかりじゃなく、こっちの仕事もしてくださいよ」
谷山が、呆れたように言う。
「いや、仕事はしてるだろ……」
谷山が言う“そっち”とは、霊や妖怪といった、普通の人ならありえないと一蹴するようなものが関わる事件を指す。高校2年のときのある出来事がキッカケで、霊や妖怪といった存在を信じるようになり、一見なんの役に立たなそうなその興味は、ただの有能な刑事では解決できない事件を解決するのに役立っている。もっとも、表向きには未解決事件として終わるものも少なくないのだが。
「そんなんだから、上司公認の変わり者って言われるんですよ、伏見さん」
「それは別に気にしてないけどな。俺が変わり者だから、普通の刑事には作れない人脈を作れたわけだし」
「その人脈って……いえ、やっぱりいいです」
「なんだよ」
「伏見さんが変なこと信じてる人なのは知ってますけど、なんでもかんでも変なことに結びつけて考える人ではないのは分かってますし」
谷山は、呆れたような、それでいて優しい表情で言った。
一見刑事には見えない谷山は、聞き込みに行っても、何かの営業と間違われることがよくあるが、見た目の雰囲気より中身はしっかりしており、伏見の数少ない理解者でもある。
「で、何があった?」
「また行方不明者です。関連があると思われるものが、先月からポツポツあったわけですが、今月に入ってペースが上がってます。不明者は男女問わず、失踪するような傾向もなく、中には、失踪した翌日に初デートの約束をしていたという女性もいます」
「自主的にいなくなった可能性は低く、何者かが関与していると見て間違いないってところか」
「そう思います。でもだとしたら、誘拐とかそういう話になりそうですが、どうやって連れ去っているんでしょう?不明者のほとんどは、家にいるときに失踪しています。それを連れ出すって……」
「誘い出してるのかもしれない。たとえばな。新たな不明者の周辺に話は聞けたのか?」
「これからです」
「それなら、俺も行く」