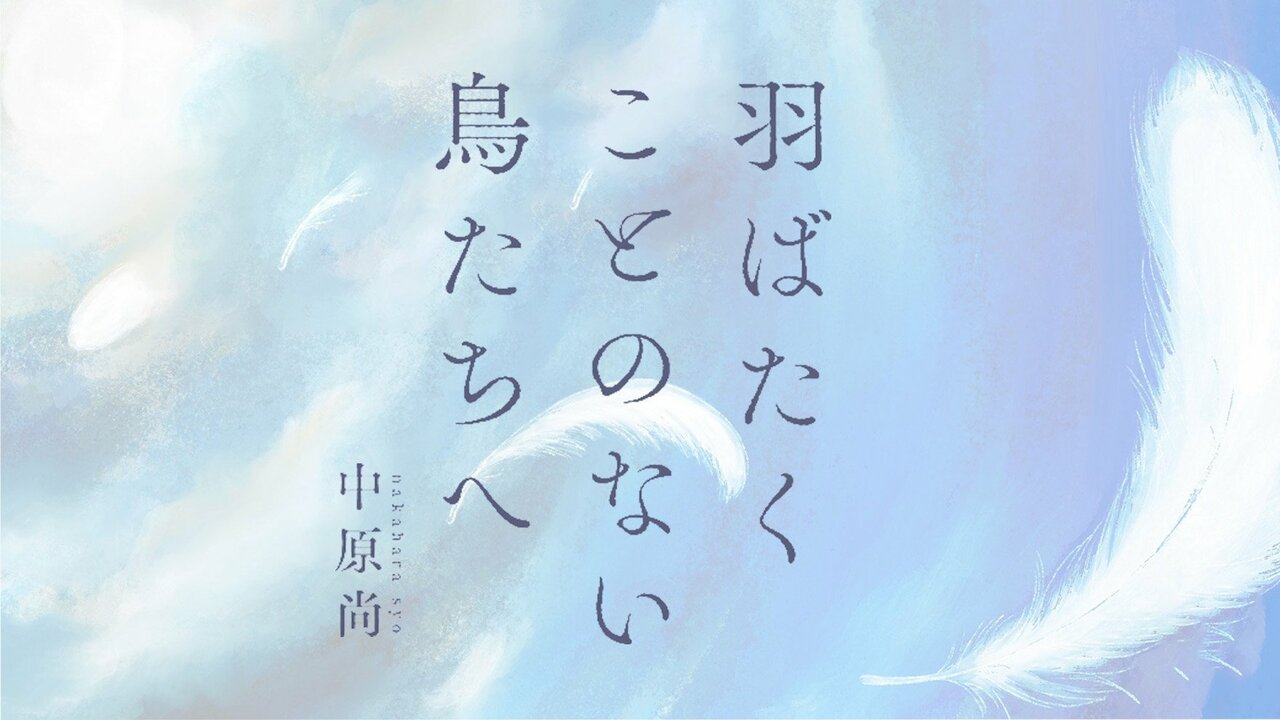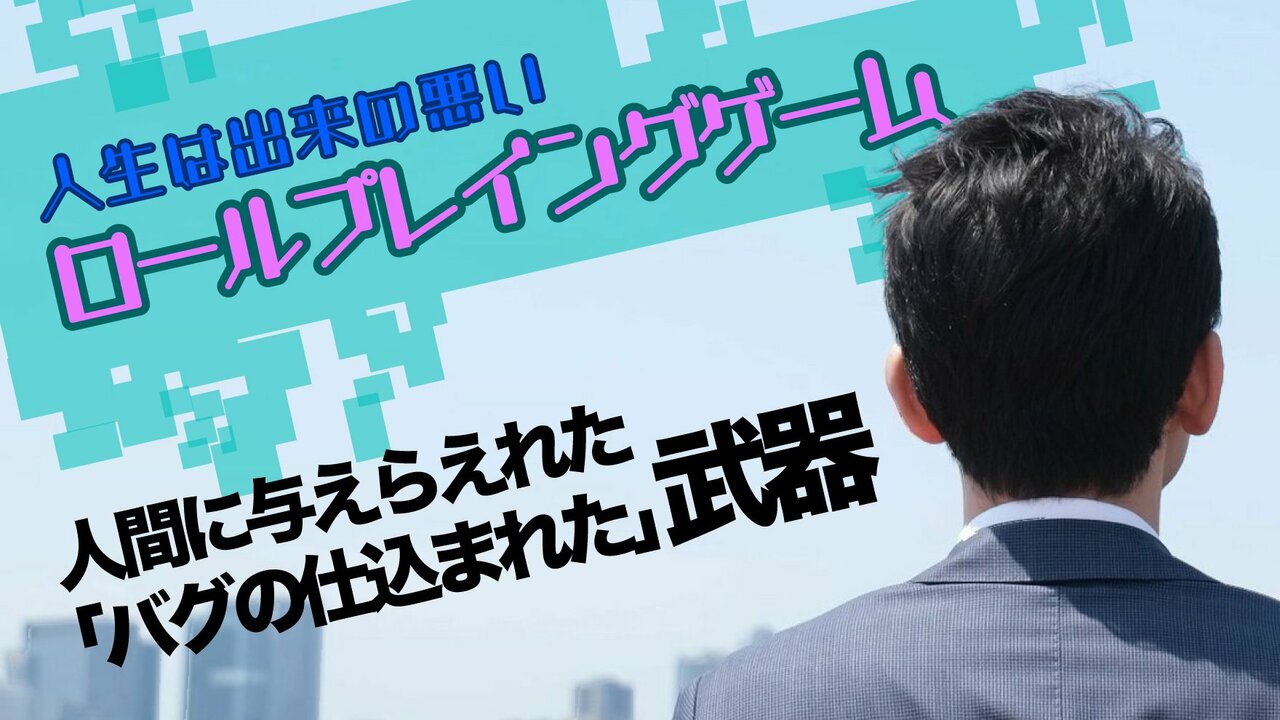【前回の記事を読む】【小説】「悪意と無縁の人生を送ってほしい」我が子に願う思い
十一月二日(東京都杉並区)
この牛丼は五万円だ。僕は今、五万円の牛丼を食べているんだ。少しでも空腹の足しにしようと紅生姜と七味唐辛子を丼から溢れるくらいに乗せた並盛の器を前に、そう言い聞かせた。前日から目星を付けて、早朝に店前の行列に並んでようやく確保した台は、僕の期待を粉々に打ち砕いてくれた。用意した千円札の束はみるみるサンドに呑み込まれ、僕は空っぽになった財布を手に銀行へ走り、口座の残金を全額引き出した。
まさに全てを賭けての大勝負だったが、僕の命運を託したスロットマシンは、「チャンス‼」とか「激熱‼」といった煽り文句をうわ言のように繰り返すばかりだった。理沙と約束していた伊豆への一泊旅行のために取っておいた虎の子も、全部溶けてなくなった。
仕方がない。ついに学生ローンのお世話になる時がきたようだ。
牛丼屋の外に出ると、まぶしい秋の光が目に染みて、視界が一瞬暗転したようだった。駅前の商店街は、たくさんの人々が忙しなく行き交っている。
買い物かごを提げて特売ののぼりを掲げたスーパーへ入っていく女性、しきりに腕時計に目を遣る落ち着きのないサラリーマン、小さく肩を寄せ合って歩く制服姿の男女。彼らの足取りには、一切の迷いがない。僕の目に映る人々は、みんなそれぞれ目的を持っていて、それを達成するために決然と歩みを進めている。家事であれ仕事であれ、彼らにはきっと為さねばならない明白な役割があり、そのための明確な目的地が存在するのだ。
翻って僕はと言えば、これから右に進もうが左に進もうが、どちらでも同じことだ。行き先を持たない僕の歩みは、移動ではなく放浪もしくは徘徊とでも呼ぶ方が相応しい。疑いない目的と目標を持って生きる彼らには、僕みたいな人間は存在しないも同然だろう。ここにいる人間の誰一人として僕のことを知らないし、僕に微塵の関心も抱いていない。彼らにとって、僕は「見る」に値しない存在であって、時空に漂うノイズに過ぎない。
別に不平を述べている訳ではない。むしろ、僕は自分がそういう存在であることを良い意味で解釈している。確かに、僕はこの世に全然必要とされない人間かもしれない。でも、目の前の人間はどうだ。彼らの人生に価値はあるのだろうか。目的と引き換えに自由を売り渡した奴隷なんじゃないのか。彼らは日々の生活のために生きている。手段と目的が転倒していることに気付いていない。本当の意味で生きていないのは彼らの方だ。働きアリのようにあくせく動き回る思考停止の人生は羨むべきものじゃない。憐憫の対象であるべきだ。