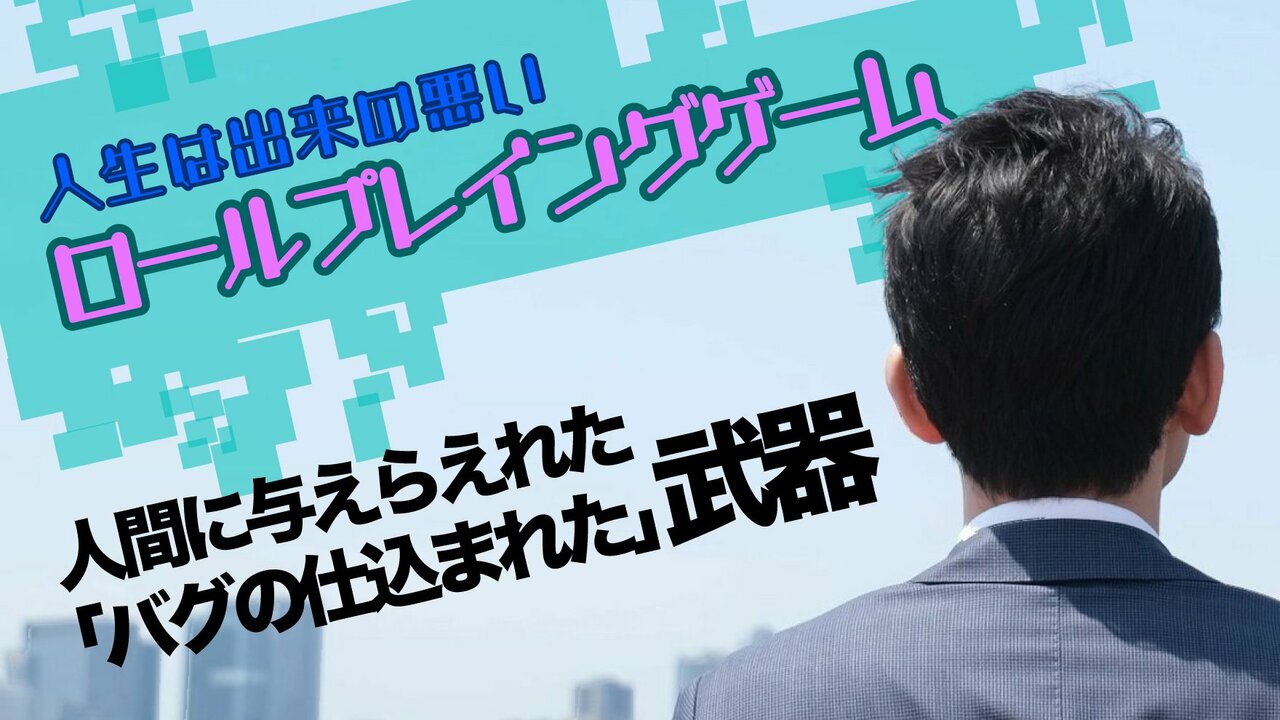財布の小銭入れを覗く。喫茶店で一杯のコーヒーを啜るお金すら残っていない。文字どおりの無一文だ。僕の足は自然と商店街の片隅にある公園に向かっていた。あそこならばお金は要らない。
真っ白な陽の光が燦燦と降り注ぎ、薄紫色のコスモスが一面に敷き詰められた花壇の内側で、何組かの親子が銀色に輝くブランコを漕いだり、カラフルなジャングルジムによじ登ったりして秋の平和な昼下がりを謳歌している。僕は公園の隅っこにぽつんと置かれた日陰のベンチに腰を下ろし、パーカーのポケットをまさぐってタバコを取り出した。遠くの母親の一人が嫌悪感と警戒心を露わにした表情でこちらを睨んでいるのに気が付いたが、相手は僕と視線が合う寸前に素早く目線を逸らせた。そうだ、それでいい。僕はタバコに火をつけた。
*
「生きよ、堕ちよ」。昔の哲学者だか小説家だかが言った言葉。それは、人間存在の全てを許し、受容してくれる蠱惑的な言葉だ。それは、倫理や哲学では掬い取れない、ある種の宗教的な響きさえ湛えている。この箴言の前では、人間のあらゆる愚行も蛮行も一般化され、浄化され、ありのままの人間本性の一部として救済される。人間は悪を為しても良い。むしろ、悪を為すべきだ。なぜなら、それが人間であり、生きるということなのだから。
でも、魅惑的であるがゆえに、僕の意識は警鐘を鳴らす。騙されてはいけない、そんな言葉に心を許してはならない、と。この言葉には自由に関する狡猾な罠が潜んでいる。そのような甘言を拠り所としてはならない。