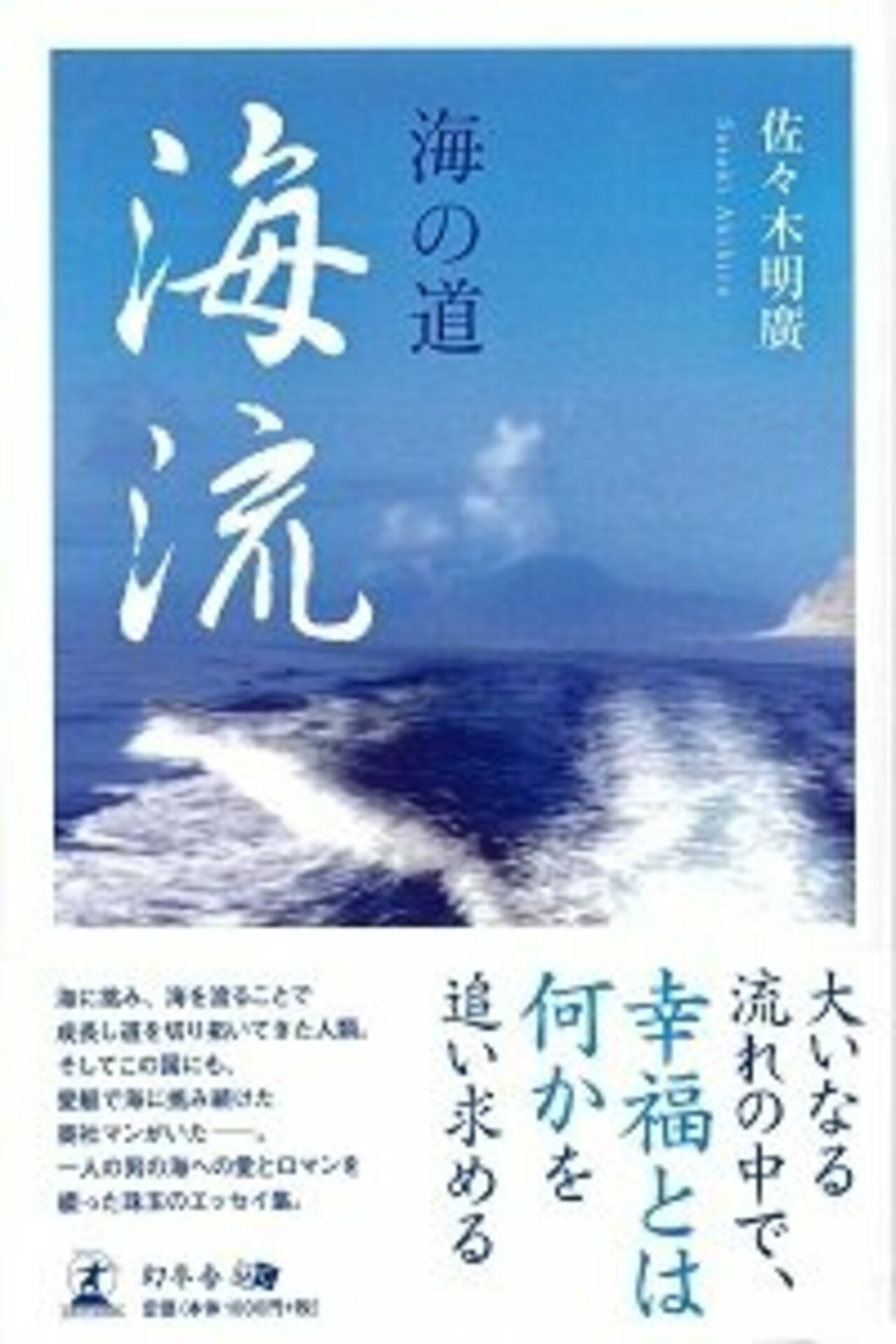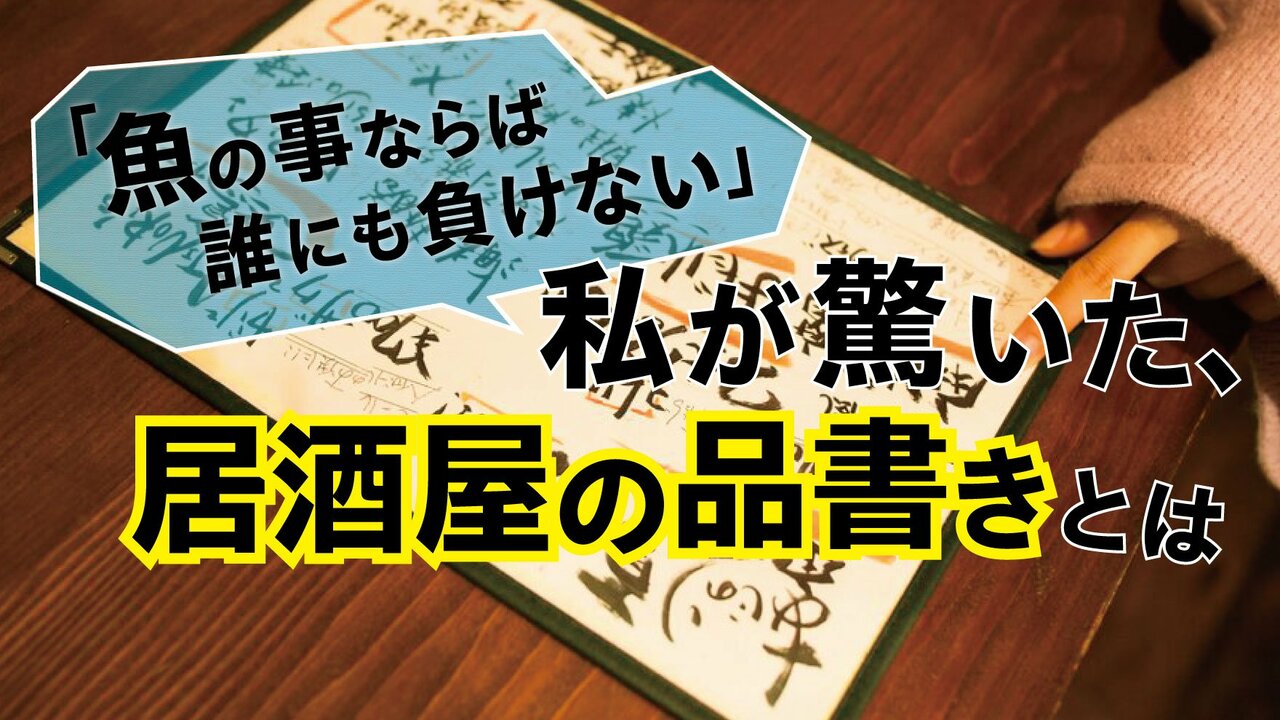その翌日、突き出しに何やら焼き鳥らしい小皿を出してくれたので恐る恐る食べてみると、どうも魚と思われた。今まで経験のない食感だったが旨かったのでこれは、と聞くとマンボウと言う。更にその翌日どうやら干物らしい食材を酢で締めた付き出しが出た。これまた経験のない味であったが実に旨い。まさかと思って目をやると、参ったかとばかり得意げな顔をしている。
やはりマンボウであった。要は、マンボウは部位によって料理の仕方を変えていると言われたが料理はまさに芸術である。その後も彼は毎晩のように変わった突き出しを準備して私を待つようになったがどうやら私は彼の創作料理の味見役となってしまった感があった。しかし、それも私の楽しみにもなった。
(二)おばちゃんのこと
ここで店の主、おばちゃんを書かねばこの章は成り立たないが、その前に私の海の仲間のことに一寸触れることにしよう。北海道室蘭の太平洋に面する電信浜の近くで生まれた私は幼少の頃からその海で遊び育った。その美しくも荒々しい海は私の海の原点となり、いつかは艇で大海原を駆け回り南の島に渡ってみたいという夢が膨らんでいった。
そしてその夢を叶えるため、伊豆の戸田でエンジンを搭載できるゴムボートを進水させ、その後モーターボートをトレーラーに載せて石廊崎を目指し、更には百七十五馬力二基掛けのクルーザーで伊豆七島の島々を航海した海の仲間が私には居たのである。
仲間の呼び名はトレーラー時代に富戸の喫茶店「シーガル」に大変お世話になった縁から海の仲間「シーガル」と呼び、艇もシーガル号と呼ぶようになっていったが我々にはシーガル一号から六号に至る艇名が物語るように長い歴史があった。
当時、その海の仲間と語り合う場所は会社の所在地赤坂を中心に銀座や通勤ルートにある自由が丘であった。しかし、私が三軒茶屋に会社を興したことから味とめに仲間が集まるようになった。そして、その集合場所の合言葉はいつの間にか「三茶の奥座敷」ということになってしまった。
おばちゃんはその頃八十歳位になっていて座敷の端にどんと座って仕入れ、客の座席案内、そして最後の勘定とまさに一人三役で店を取り仕切っていた。店は古く、座敷の上りぶちの手前が土間の時代もあったそうで、優に築五十年以上経っていると自慢気に言われていた。一方、私には二階の床が抜け落ちはしまいかという不安があった。
大勢客が入った日には一階が三十名程で飽和状態となり二階の仏間も開放して更に三十名程詰め込むこともしばしばであった。私がカウンターの角にこだわったのは丁度その上が二階に上がる階段となっているのが音と構造でわかっていて、万一、二階が抜けても私だけは生き残ることができるであろうとの読みがあったからである。