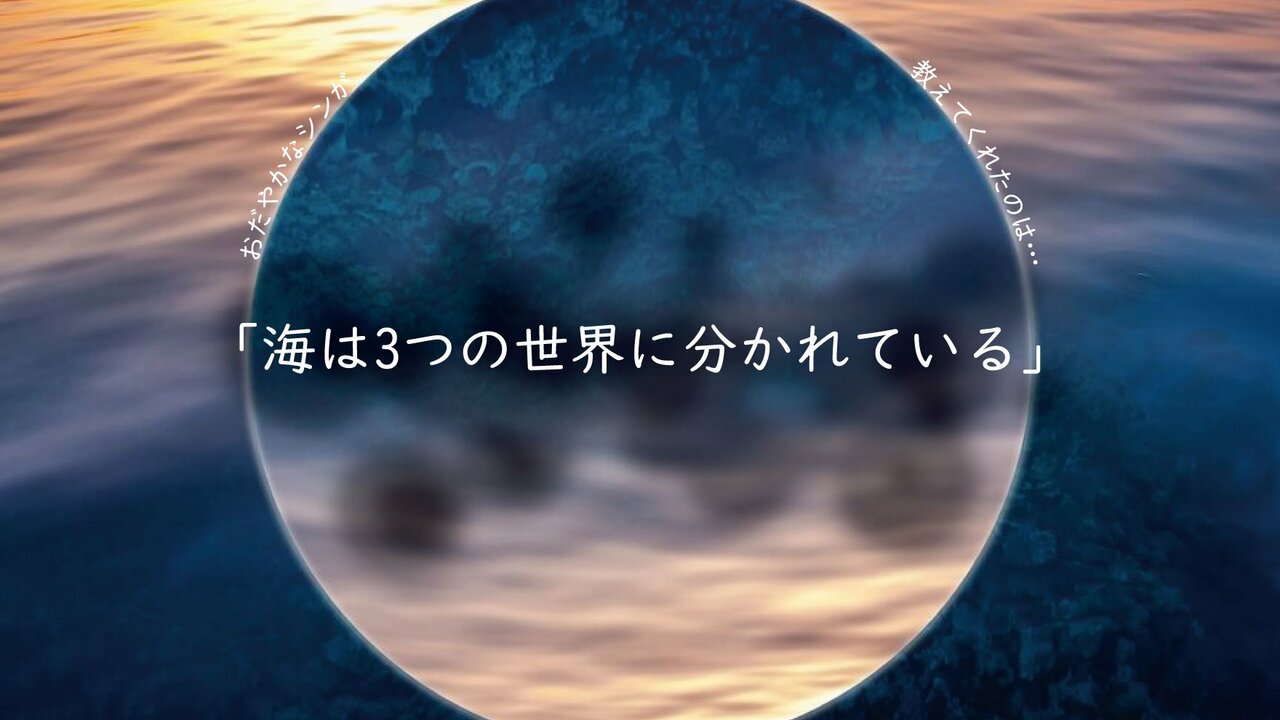(2)北の海へ
ある日のことでした。ひとりで遊んでいた坊やは、水底の砂に、もつれあってキラキラゆれているまぶしい光の網を、ふとしたひょうしにするりとくぐり抜けてしまい、知らない海に迷いこんでしまいました。
見わたすかぎりの青い海、頭のてっぺんからしっぽの先まで、じ~んとつめたい青い海に、坊やはたったのひとりぼっち。ずっと遠い沖のほうまで、島もなければ鳥の影ひとつ見えません。
照っていたおひさまが時々ふっと、雲のかたまりの中にかくれてしまうと、ま昼の海はきゅうに夕暮れのようにかげってしまいます。ギザギザの波が、右からも左からも近づいてきて、大きくうねりながら、坊やの頭の上を音もなくとおり過ぎていきます。
ここ、どこかなぁ、かぁさぁ~ん! とうさん、どこ? だあれもいない、とってもつめたい、ボクこわいよ~。
「でもボク、このうみ、どうしてかなぁ、なんだかしってるみたい」
坊やは、あとからあとから近づいてくるギザギザの波を、どこかで見たことがあるような気がしてなりません。
どこだっけなぁ、え~とね、え~と、え~と。あッ、もしかして?
そうです、そうだったのです。ここはとうさんがいつか話してくれた、はてしなく広い、北の海だったのです。