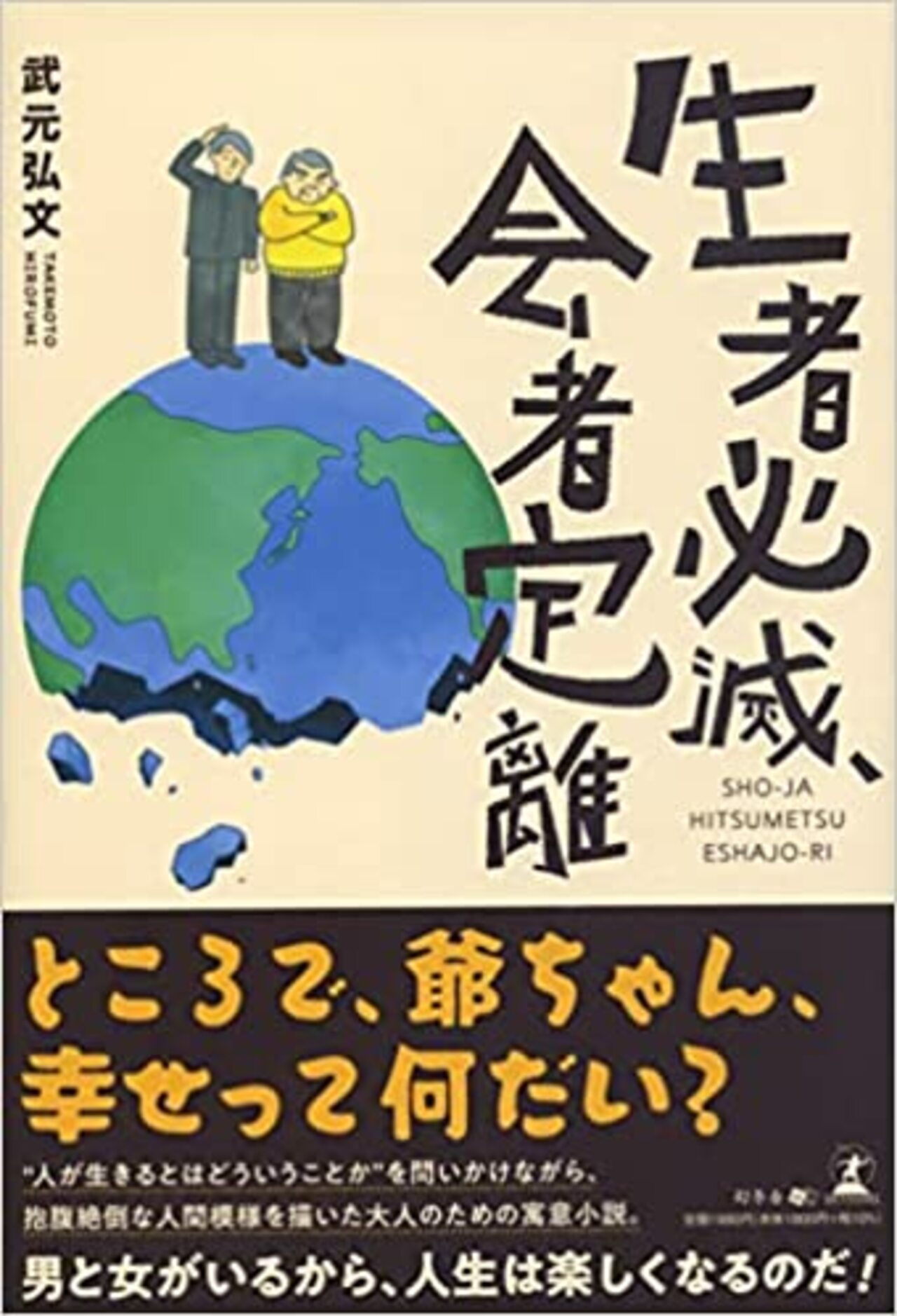あっという間に三ヶ月がすぎ、夢のような新婚生活から目が覚めたお鶴。色男の文左衛門のことだ。いずれは他の花の蜜を吸いに行ってしまうだろう。賢いお鶴はそう思った。でも、この夢のような日々を何とかして末永く続かせたい。命ある限り文左衛門に愛されたい。早速、母、千里に尋ねる。
「母様は、どないしとったんや」
「男はみんな蜜蜂や、甘い蜜でも飽きれば他の花に飛んで行ってしまうのや」
「なのに長い間、父上とどないしてうまくやってきたんや?」
「それはな、相手を思いやる気持ちと丈夫な体なのや」
「当たり前のことのようだけど……」
「そうや。でも、長続きさせるのはなかなか大変なことなのや。新婚の頃は夢中だった交わりも、惰性のままに放っておけば、義理マンの一つで済まされてしまうのや」
「旦那様もそうなのかしら」
「……?」
返事の代わりに千里は桐箪笥から枕絵を取り出し、お鶴の目の前に広げる。客と花魁が、目の前で痴態の限りを演ずるのを禿の頃から見てきたお鶴。体位の多くはすでに見知っていたが「ぅわぁー、こんなに仰山あるのかえー」と、四十八手に驚く。
「母様、父様にみんなやってもらいなさったのかえ?」
千里は〈押し車〉を指さしながら「とても、とても。これなんかは、女郎が客を喜ばせるためにやっていたのであろうよ。要は交わりに工夫を凝らし、変化をつけて旦那様を飽きさせないことなんや」
「さよか。では、おいおいやってみることにいたしましょう」
「でも、全部をさらけ出してはあきまへん。蜜を吸い尽くした雄は他の花に飛んで行ってしまうによって」