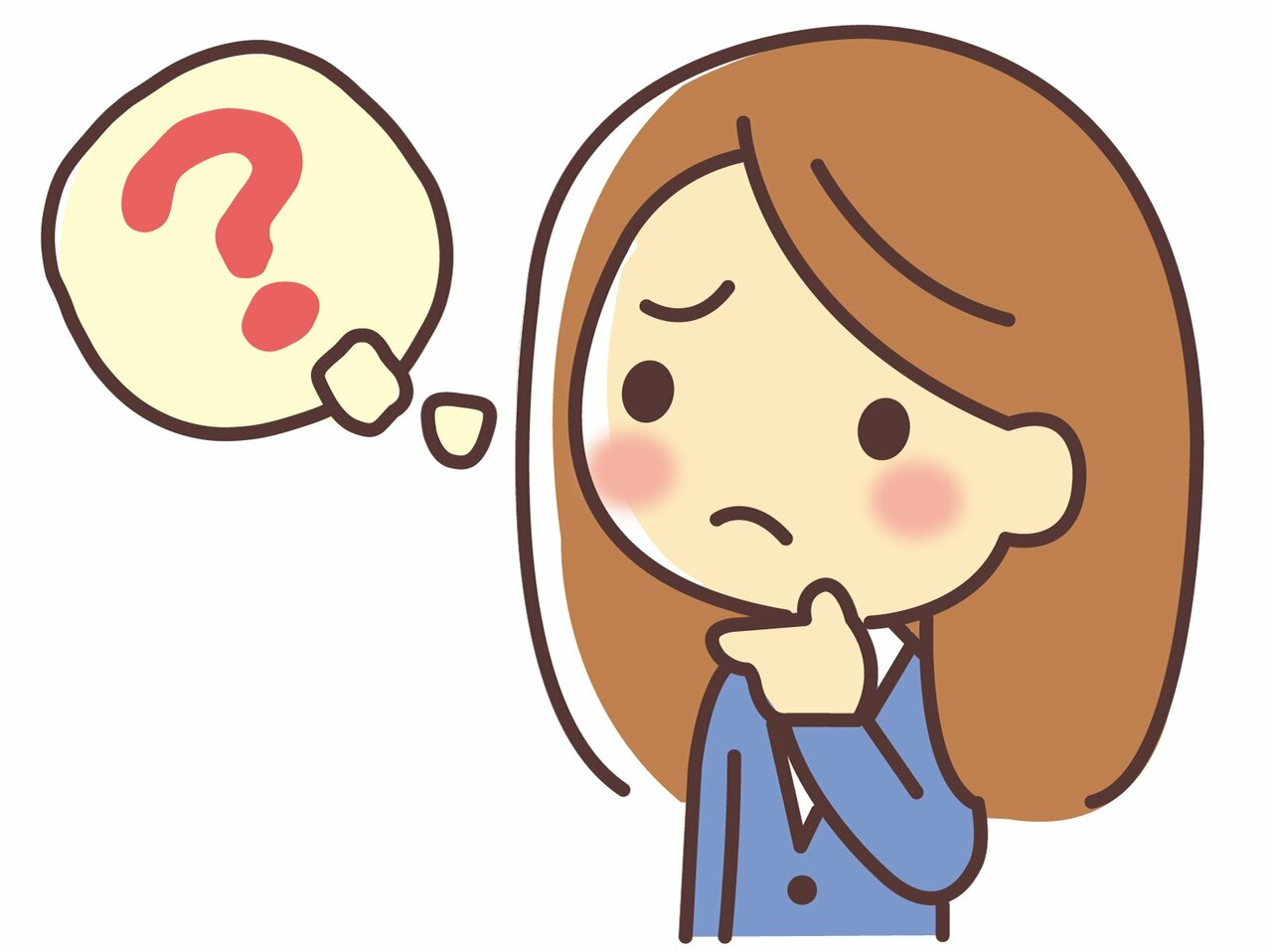さて、いよいよ彼の乗った列車が駅へと到着するであろう時間よりも早く、彼女は待ちきれず駅へと向かっていました。それこそ、満面の笑みで。
再会できることがうれしくてめかしこんだ彼女は、鼻歌交りで颯爽と歩き、黄色い蝶々が後を追いかけるように舞っています。誰が列車の事故を予測できたでしょうか。遠い異国の地で、大事故が発生したことを。
ニュースさえない時代に、電報もない時代に、事故が起きたことなど知る由もありません。列車が到着するはずの時間を過ぎても、一向に列車が到着する気配はありませんでした。駅では、迎えに来ていた大勢の人たちが、列車の到着をまだかまだかと待っています。
だんだんと顔の表情に陰りが見え、ざわついてきました。
いったいなにがあったのか。状況がわからないまま、待っていた人たちは徐々に渋々、家へと戻ることを余儀なくされました。
きっとどうしようもない急用ができて、彼は電車に乗り遅れたに違いない。彼女はそう思って、その日は帰宅しました。
それからというもの、彼女はその列車が到着するであろう曜日の時間帯を見計らっては、駅まで迎えに行くことを繰り返すことになったのです。もう何回、駅まで通ったことでしょう。待てども待てども、彼の姿を見つけることはできませんでした。
列車が到着するたびに、彼女は最後のお客さんが降りるまで待っているのですが、どこにも彼の姿は見当たりません。
今日も乗っていなかったの? いったい彼はどうしちゃったのかしら。そういえば、彼からのその後の手紙もありませんでした。手紙が届くはずがありません。手紙が届くとすれば、それは天国からの手紙ということになるからです。彼女は到底、そんなことになっているなんて思ってもいませんでした。彼の帰りをただひたすらに信じて、彼女は待ち続けました。
きっと戻ってくる! 「待っててね」って言われたのだから。そう信じるしかない。きっとなにかの事情があるはずだと、彼の死への疑いすら彼女は持ちませんでした。