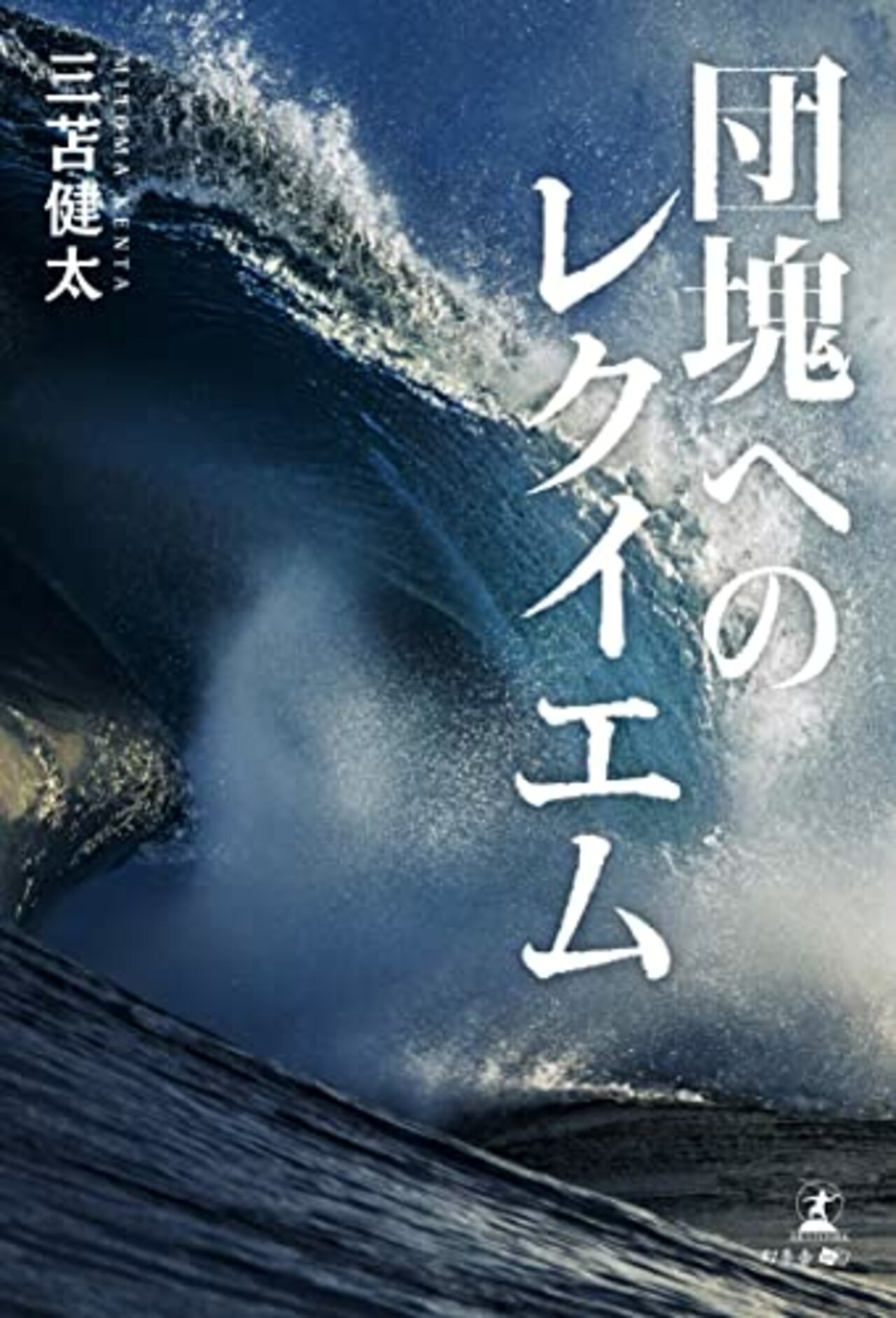2
左沢と学級委員は俯いて沈黙していた。校長たちは真一の自殺の原因は学校内にはないと断定している。しかし、それは十分な根拠に基づくものではなく、責任の回避や転嫁を目論む校長たちの身勝手な作り話であることは、十四歳の左沢にも容易に察しがついた。
「心当たりはないかな」
校長は、左沢を一瞥したあと、目で学級委員に発言を促した。
「ありません、まったくありません。教室でも、特に変わったことはありませんでした」
学級委員は少し考え、頭を振りながら答えた。校長も教頭もわが意を得たりとばかり、無理して作った厳しい顔で大きくうなずいてみせた。
(また調子のいいこと言いやがって)
左沢は小さく息を吐きだした。学級委員のいつものご追従だ。
「左沢くんはどうかな。君には、水沼真一くんとは幼いときからの友達で同じ塾にも通っているということで来てもらったのだが」
「放課後のことで心当たりはありません。むしろ……」
左沢は言い淀んだ。脳裏にリーゼントのふたりの顔が浮かんだ。真一はあのふたり組にいじめられていた。これは、学級委員も知っていたはずだ。
「むしろ何だね」
校長が眼光を鋭くして畳みかけてきた。
「あのふたりからは聴取済みだ。確かにいたずらはいろいろしたようだ。しかし、どれも自殺するようなひどいものではなかった」
言ったのは担任だった。担任は怒ったような顔をして左沢を睨んだ。思わぬ担任の剣幕に、左沢は出かかった言葉を呑み込んだ。