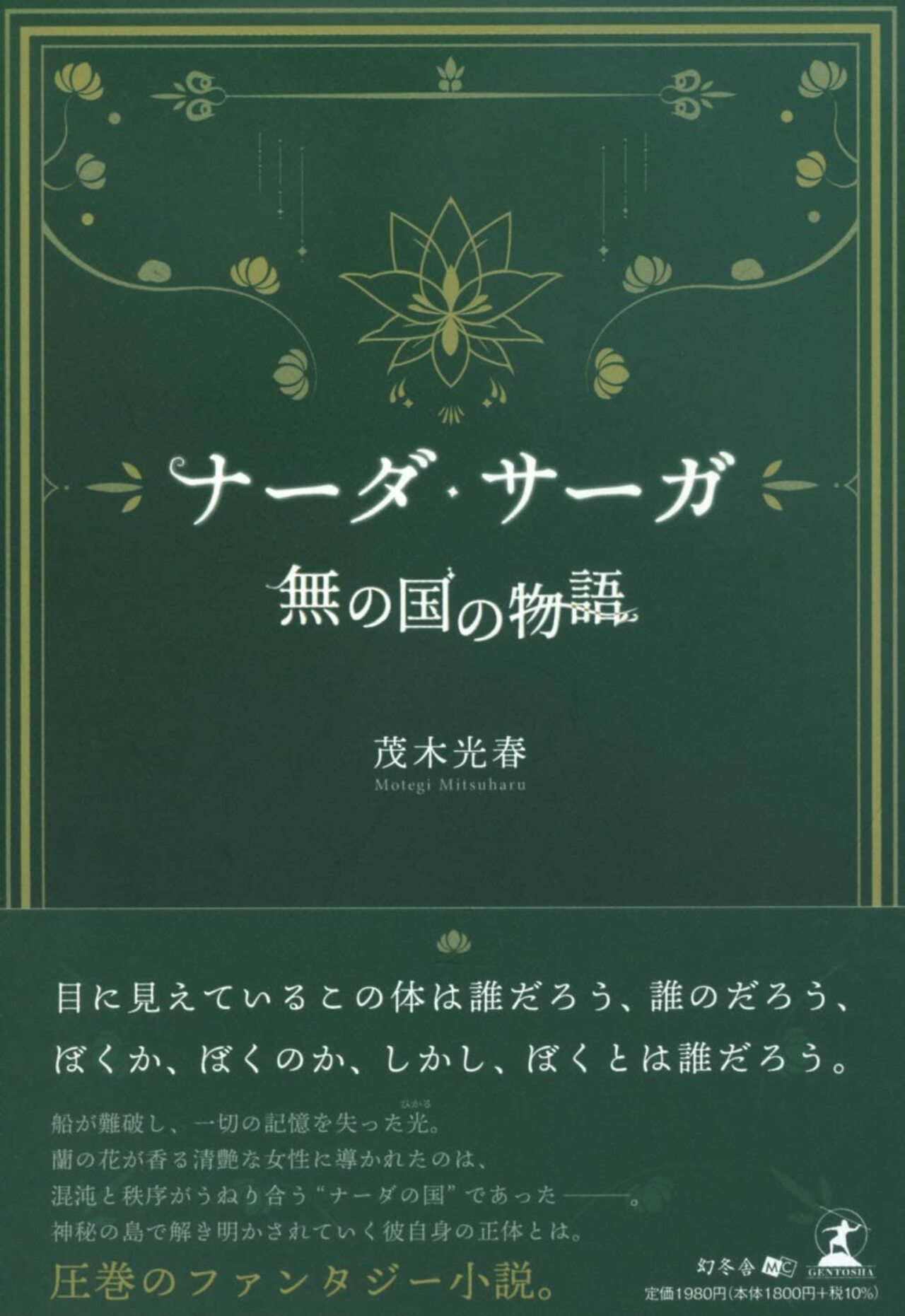辺り一面、白い陽炎だ。砂浜の無数の砂の先端に、光の粒々とした滴が極小の王冠となってきらめいている。砂浜はどこまでも続いている。果てしない青い海と果てしない青い空と果てしない白い砂浜と。そして衣服は切れ切れに破れ、切り傷だらけ、打ち身だらけのほとんど裸同然のぼく、あるのはそれだけだ。
どうしてぼくはここに居るのだろう。どうしてここに海藻の切れ端のごとく砂浜に横たわっているのだろう。朦朧として、内も外も、果てもない空白である。
ぼくは立ち上がる。そして歩き出す。何歩か、前に進み出る。しかし、記憶がない。思い出されて来るものがない。空白を引きずっているだけだ。百年の空白か、千年の空白か、その空白の澪の先端を、今こうしてよろよろと震え出しているばかり。虚無体というか虚空体というか、それがぼくと称し、ぼくというかすかな最後の記憶の破片のごときものに取りすがって歩いている。
ただ、痛みだけはある。肘や腕や膝や頭の痛みだけはある。流された痛み、流されて来た痛み。何百年も何千年も流されて来たごとき痛み、それだけはある。そんな痛みが、ぼくなのかもしれぬ、ぼくと言わせているのかもしれぬ。痛みが、痛みつつ、ぼくと感じ、ぼくと称しているだけなのかもしれぬ。ぼくとは、極薄の、痛みの破片、痛みの金箔にすぎないのかもしれぬ。
見えて来た。左手の砂浜を上がった真向かいに、大きな石の群れが、岩でもなく自然石でもない、切り出された、崩れた、石垣が。地面に半ば埋もれ、半ば露出し、斜めに傾き、横に倒れ、何段にも積み重なった石垣の並びが見えて来た。
奥へと徐々に高く、何段にも何列にも並んだ石垣の奥に、何本もの石柱が、それによって支えられていたとおぼしい屋根も破風もなく、露出し、崩れ残って、建っている。その奥にはかつての宮殿か神殿か、その遺跡を思わせる石造りの壁や床の跡が、至るところに、並び、転がり、広がっているのだ。
ぼくは、傷ついた空白体、痛む虚空体を引きずって、そこへと歩を進めた。なぜか広大な石造りの遺跡を目の当たりにして、わが姿を眼前にしているごとき、摩訶不思議な親しさを覚えた。百年の、千年の、わが内なる荒廃が外部に今初めて露わになっているがごとき思いを抱いたのである。
しかも、その時、一個の妙なる花の香りが漂って来るのが感じられた。懈怠の、懶惰の、濃密な花の香り。熱帯の寄生蘭のごとき、強い重い甘美な匂い。それを一度吸えば、百個の夢幻が通り過ぎるがごとき、時の煮詰まった、妖しい匂いが感じられたのだ。
どこから匂っているのだろう。どこから匂って来るのだろう。花の姿は見えない。遺跡のごとき崩壊した建物群の周囲には、たしかに樹木は見えている。しかし、花は見えない。まるで空気そのものが一個の名状しがたい匂いを放って、漂い、蒸れているのか。
それとも、すでに形を失った目に見えない存在が、それでもなお、匂いだけは、その存在の追憶のごとく、その存在の遺跡のごとく漂い、うごめき、佇立しているのか。
あるいは、ここは一切香世界とでも言う世界であって、どのような存在も、存在としては姿なきものでありながら、それぞれ一個の香りをもって存在しているがごとき、不可思議な時空間に巻き込まれているというのか。