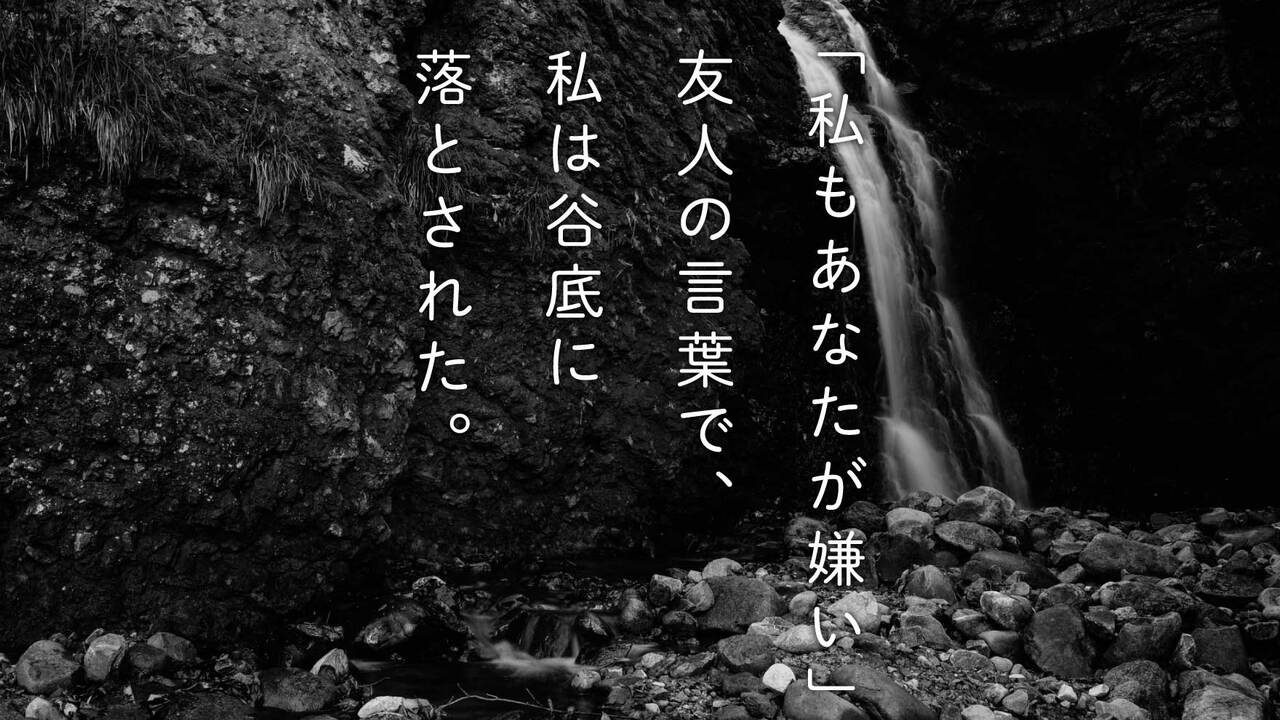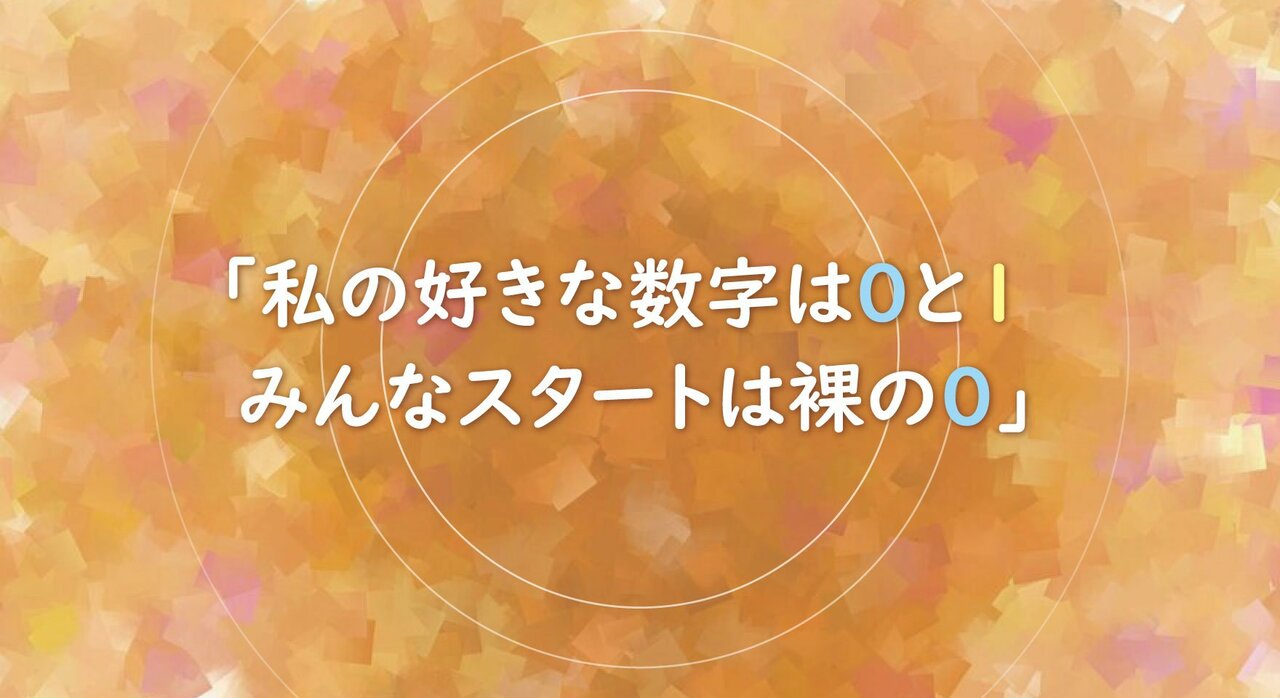掟
父は寡黙なひょうひょうとした医師だった。私の結婚式は最後の晩餐の様に盛大だった。その頃、父の容体はあまり良くなく入院していた。式は遠方だった為、父は結婚式に出席できる体力はなかった。友人は遥か彼方に居て、話す事すら出来なかった。最後に打ち掛けを着たのだが、その着物は父が見立ててくれたと母から聞いていた。
余り話した事もない父だった。縁側で白いシャツに片ひざをついている父の横顔は、いつも寂しそうだった。病院に父の顔を見に行った時、思いがけず父が別れ際に笑って握手をしてきた。私は、涙を見せまいと必死に堪えた。
普通なら嫁入り前の娘は、残り少ない家族との日々を大切に思いながら食事を共にするのだろうか。家は静かで、母は、父の看病と私の支度に本当に忙しかったと思う。夜中チョキチョキとハサミの音がしていた。
嫁いで電話で話した時「ほら、着物の端に四季柄、訪問着って書いてあるでしょ、それを着るのよ」と母が言った。
ハサミの音は、私が困らない様に着物の柄や種類を白い紙に書き夜な夜な作業をしていくれている音だった。
結婚式の花嫁はどんな気持ちなんだろう。着物を出すと、父に私の振り袖姿を見せたかったと今でも思う。
熱のある母を電車で見送る時は、本当に切なかった。結婚式の話しを列車で話す相手もいない。私は帰宅した母に、一通の手紙を置いておいた。「あなたの娘で良かったです」と。
母は若草物語の様に大切に育てられた4女。身体は余り強くはなかったが、体操の選手だった。お洒落でモンペの型を人とは違う形にしていたらしい。母は大層人気者だった。
ある日、父の具合が良くなく父が苦しい。父が母に注射を打って欲しいと言うのだ。母は看護師ではないので注射など打てる筈はない。だが、母は、苦しむ父に注射を打った、と私に言った。その話を聞いた時、私は母の顔をまざまざと見た。肝の座った人で、いざという時には尻込みをしない強靭な心の持ち主だと心底思った。
食卓は静かで喋りながら食べていると早く食べなさいと諫められ、食卓に行くのが遅いと料理が下げられていた事もあった。母は旬の物をよく出した。つくしの卵とじ、新聞紙を広げて銀杏を食べたり、焼いた松茸をフーフー言って食べた。子供向けのお料理が並べられていた事はなかった。
我が家には掟があった。
掟とは、娘は勤める必要はなく早く嫁ぐ事である。
私は、東京から戻り程なくしてラジオ局でリポーターをした。色々な地方を回りその土地のお祭りや特産品などを取材する。その様子を生放送で話す仕事だった。ある時はベテランの雑誌社の方とご一緒してリポートの仕方を教わった。
熊本の帆掛け船では、すぐに船酔いをしてしまい帆が上がった時、ようやく酔いが覚めリポートにならなかった事もある。狭いスタジオの朝の生放送で明るく流れる秒の世界に私の胸は踊った。
今でもDJがしたいと思う。誰かの耳に私の声が届き、ひと時の時間を共有できるラジオの世界は素敵だ。