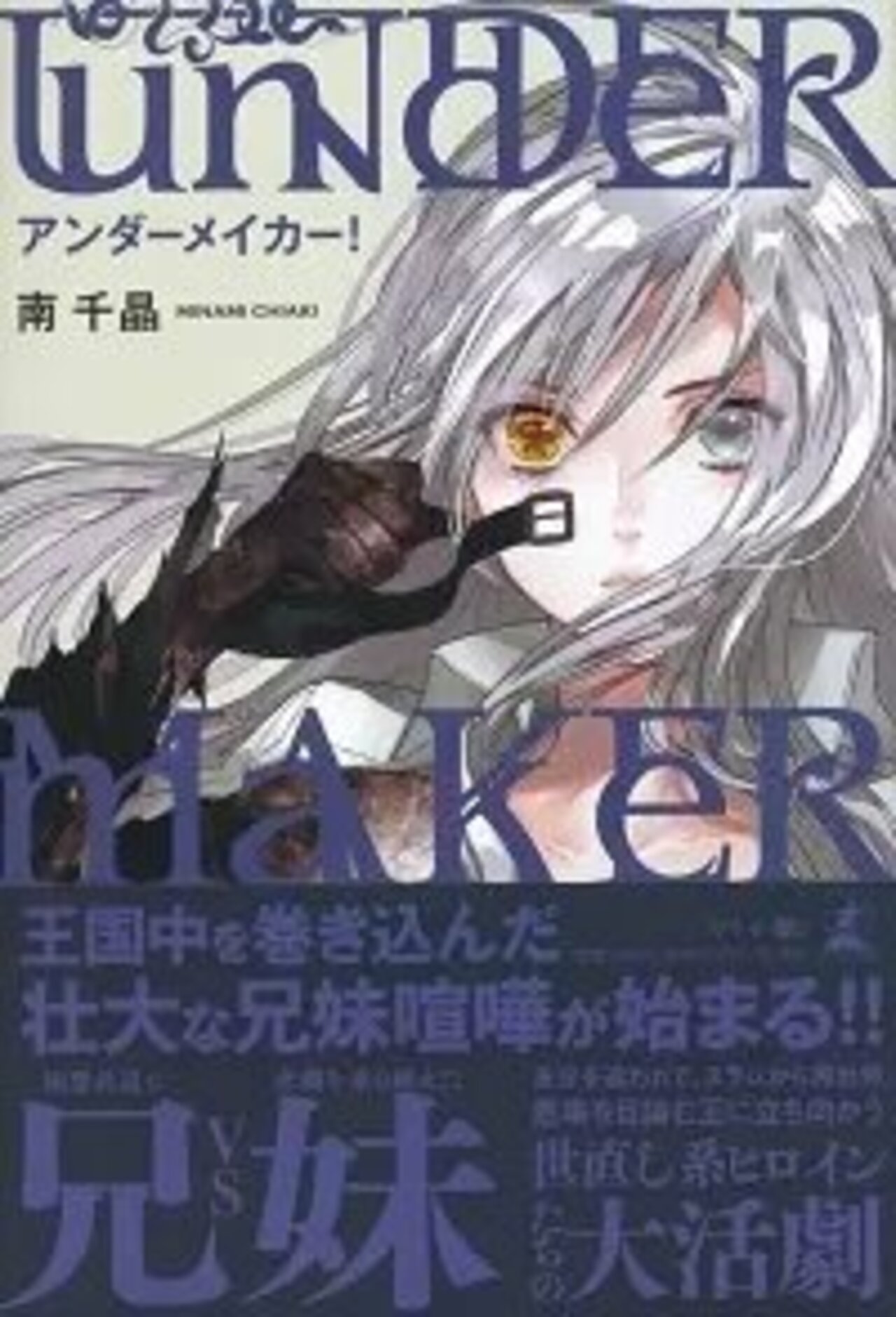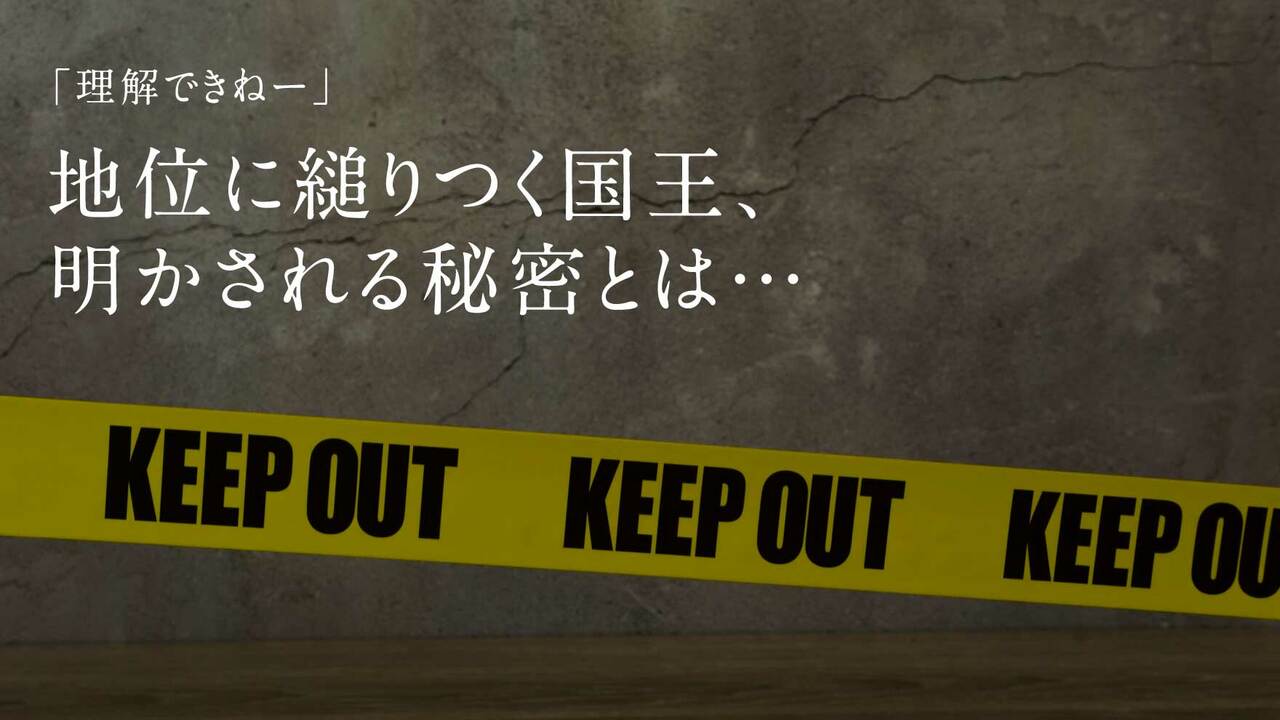「……このような状況は、七年前以来でございますね」
「あの時の方が酷かったさ。焼け野原みたく炎が上がってたんだしよ」
「あ? なんの話だよ?」
「いや、なんでもない。それより、ちゃんと道案内しろよ」
「わぁってる。こっちだ」
くねくねと何度も廊下の角を曲がり、階段を登り、また何度も角を曲がって―位置としては西の方角に当たる部屋の前に辿り着いた。
「ここがあの女の私室だ」
身長の二倍はあるかと思われる木製の大きなドアを引けば、ギギと重い音を鳴らしながら扉は開いた。桃色の絨毯は気品を感じさせ、天窓とレースのかかったベッド、洋風で豪華な化粧台、バルコニー、浴室、寝室に続く扉等。そして一行は迷わずクローゼットの設置された隣の寝室へと向かう。
「………」
「………」
誰もが言葉を失くした。
「キマリ、じゃねぇの?」
「まだ分かんねーだろ!」
「いや、だって浩輔」
「衣服が一着もかかっていないのでは、確定であろう」
そう、壁一面のクローゼットの中には、衣服が一着も残っていなかったのである。だが、こんなにも大量の衣服を一人で持ち運びできるとも思えない。どこかに荷物として運んだのでは―と推測し、彼女は宅配の送り状を探す事にした。それすらも処分されているなら無駄な行為ではあるが。
足は自然と鏡台の隣に置かれているゴミ箱に向かい、腰を下ろして中を漁り始めていく。浩輔はイライラしているようだったし、栗栖と殺女は室内をそれぞれに調べている。そして、そんな彼女の後ろにはいつの間にか桐弥が立っていた。
「何か思う事でもあるのかね?」
「ゴミ箱の中も鑑識に出したか?」
「いや、そこまでは」
「ほれ」
ぐじゃぐじゃに丸められたゴミを、彼女は広げていく。
「見つからないとでも思ったのかよ、浩輔のおかんは」
「気が急いていたのかもしれんな」
広げた紙に納得してみせると、それを背中越しに桐弥へと渡した。
「……送り状か。住所は―」
配達業者から渡されたのであろう本人控えの紙。そこには行方不明になった荷物の宛先が書かれていた。……が、桐弥は彼女がコレを見て平静でいられる姿が信じられなかったようだ。
「葬儀人、これが本物だという証拠は?」
「浩輔に聞くのがいいんじゃね? 母親の筆跡ぐらい分かるだろ。分かんねーなら、筆跡鑑定にでも出せばいい」
そしてまたゴミ箱を漁っている彼女の手に、もう一枚の紙きれ―元は手紙であっただろう紙が無残に破り捨てられていた。
「“…海川の……を渡せば…しない……”―だめだ、なんの事か分かりゃしねぇ」
他にも切れ端はあるようだが、文字としての役目を果たしていない破られ方をしており、この場で解読は不可能だろう。
あとは数本の髪の毛と使い切った口紅、中身のない香水ぐらいのものだった。