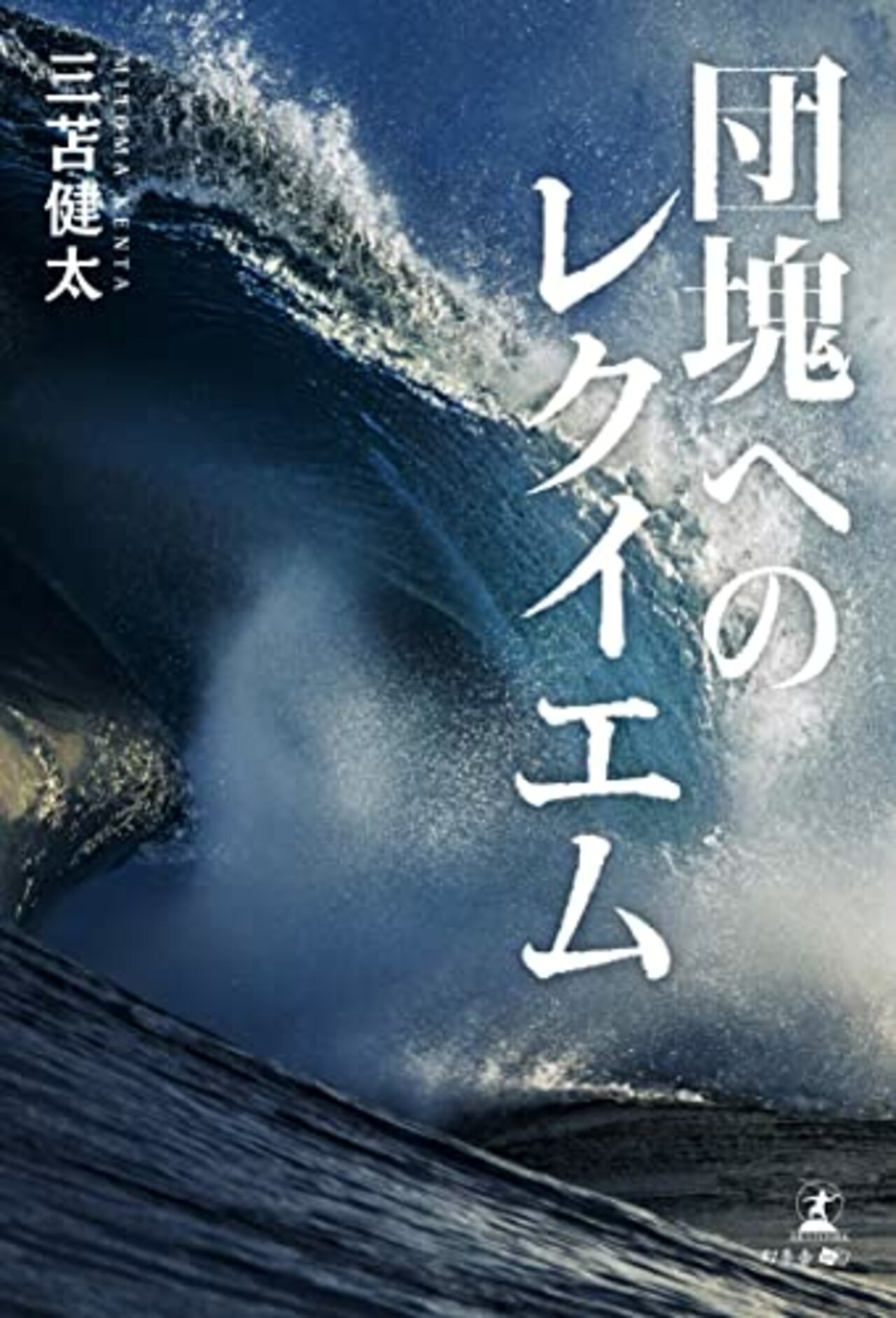左沢が中学二年生の二学期の最初の日にあのおぞましい事件は起きた。左沢がその事件を初めて耳にしたのは、始業式の最中のことだった。
(うちの学校の生徒が自殺したらしい)
体育館に集まった全校生徒の数人の口から出たこの言葉は、瞬く間に館内に広がり大きなざわめきになった。意味不明の奇声をあげる生徒もいた。演壇の校長や窓際の先生たちが抑えようとするが、収まりそうにない。
左沢は背伸びするようにして真一を捜した。やはりいない。始業のチャイムが鳴ったとき、教室に真一の姿がなかったことに、左沢は嫌な胸騒ぎがしていたのだ。
(もしや真一では)
左沢は佑太を捜した。生徒の群れから頭ひとつ抜き出た佑太はすぐに見つかった。佑太は隣の生徒の言葉に小さくうなずいているだけだ。左沢とは別のクラスで、今日、真一が登校していないことを知らない佑太は、このざわめきを真一と結びつけてはいない。
(真一ではありませんように)
左沢は祈った。しかし、その祈りは空しかった。予感したとおり自殺したのは真一だった。始業式のあと、担任が苦渋の表情とともに、絞りだすような声で、その事実をクラスの生徒に告げた。
「理由はなんですか」
女子生徒が立ち上がって怒ったような顔で尋ねた。
「まだ何もわかっていない。校門には報道関係者が押し掛けてきているが、余計なことを喋っちゃいかんぞ。いいな」、と担任は念を押し教室中を見渡した。しかし、重苦しい空気が教室を覆っているだけで、返事をする者もうなずく者もいなかった。担任を含めてクラスの全員は、真一の自殺の原因を薄々感づいているはずだった。
左沢は最後部の席のふたりの男子生徒を見た。ふたりとも窓に向かって横座りになり、ふてくされた顔をして、そろってリーゼントにした髪を櫛で撫で上げている。左沢は、急に怒りがこみあげてきてふたりを睨みつけた。ふたりも目線に気づき睨み返してきた。小さいほうのリーゼントはしきりに指を鳴らすしぐさをしている。威嚇のつもりだ。
不穏な空気に気づいた担任が、慌てて教壇から下りてきて、リーゼントのふたりと左沢の間に立った。
「とにかく、今は何もわかっていない。いいな」
担任は、左沢だけを見て、もう一度「いいな」、と力を込めた。
あとでわかったことだが、真一は遺書を残さず、自分の部屋の二段ベッドの棧に紐を掛けて縊死していた。