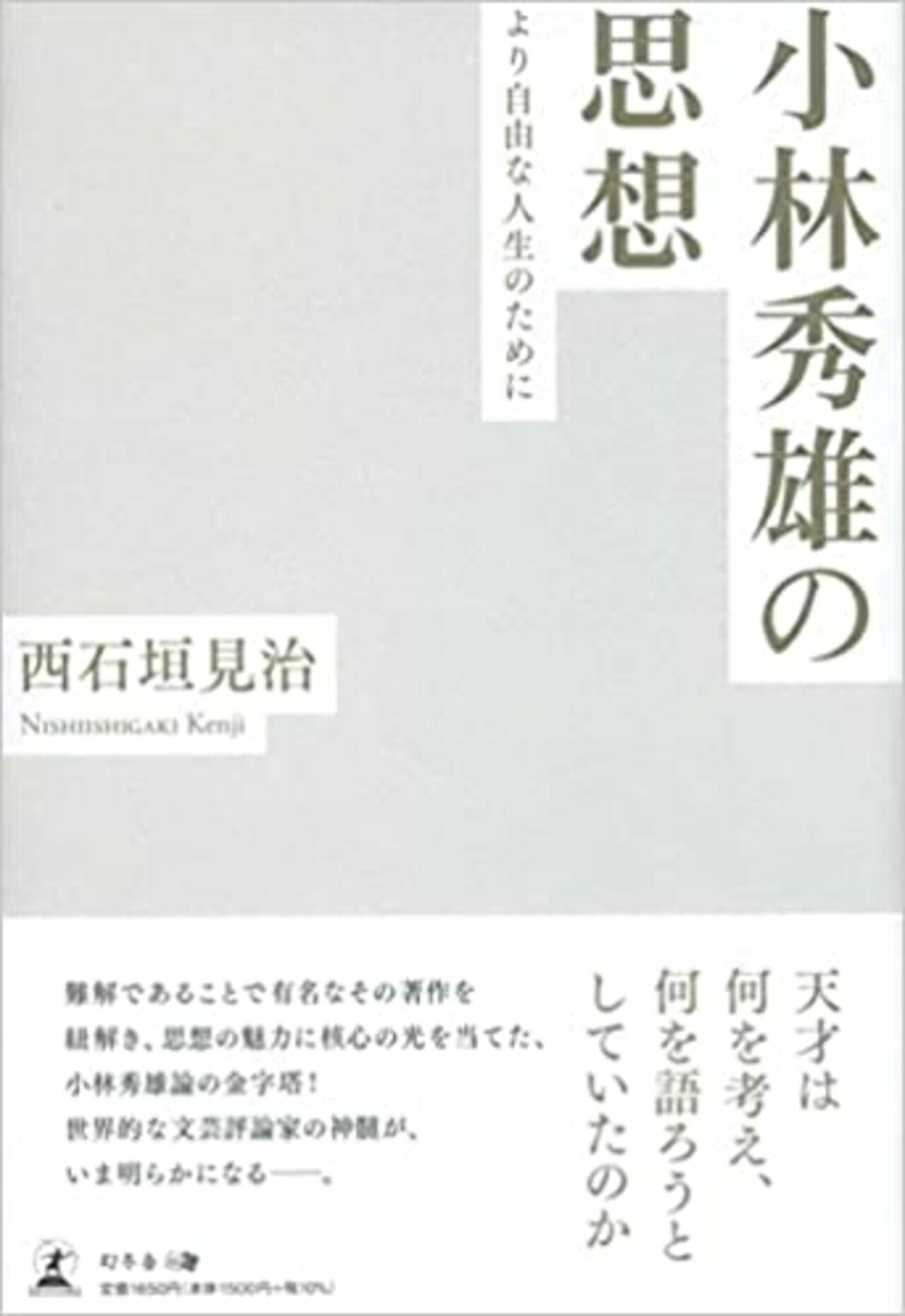文明開化の造語である「常識」は、それ以前から歴史的に格別視されてきたこと
このような、常識の反省的本質の奥深さについては、明治の文明開化において、“常識”という造語を当てる以前から、その照応する意味内容に関し、洋の東西を問わず、格別な注意が払われてきたのである。
そもそも原語である、欧米の「コモンセンス」がそうなのである。それは、ギリシア哲学の理想主義の伝統の流れから、その理念を汲んでいて、デカルト哲学が「高邁の精神」とペアで有名にしたこともあって、すでに、人心に広く訴えるものであったのである。
そのため、例えば、アメリカ独立戦争の引き金となった、トマス・ペインの著作において、その題名に利用されるほどであったのである。
そこでは、常識は、めいめいが努力して己自身の内部に新たに発見すべきものとして、それゆえ、第三者的には、その内面的な努力を呼びかけ、あるいは手助けることがせいぜい可能なものとして、位置づけられているのである。
「人間としての真の本性を身に付けて、いなむしろそれを捨て去らないで、現在を乗り越えて大きく視野を広げていただきたい。」(『コモンセンス』小松春雄訳、岩波文庫)
又、一見遠くに離れて見える「神智学」の分野からも、秘教めいた照明を“常識”の側に投げ掛けて、その精神的鉱脈の通底が内々に照射されたのである。
これは、東洋の精神思想史においても同様で、それが、周知の「中庸」という言葉なのである。わが国でも、「常識」といういわば欧風の受け皿に引き継がれるまでの間、その別格の意味のアイデンティティが、伝統的な位階秩序において、事実上の“玉座”を占めてきたのである。
「天下国家も均しくすべし、爵禄も辞すべし、白刃も踏むべし、中庸は能くすべからざるなり」(『中庸』)
中庸という名の常識の玄妙な働きは、多様かつ深浅さまざまな照明の光にさらされつつ、孔子以来、二千数百年にわたって、東洋思想の伝統の流れの深みを支配してきたのである。