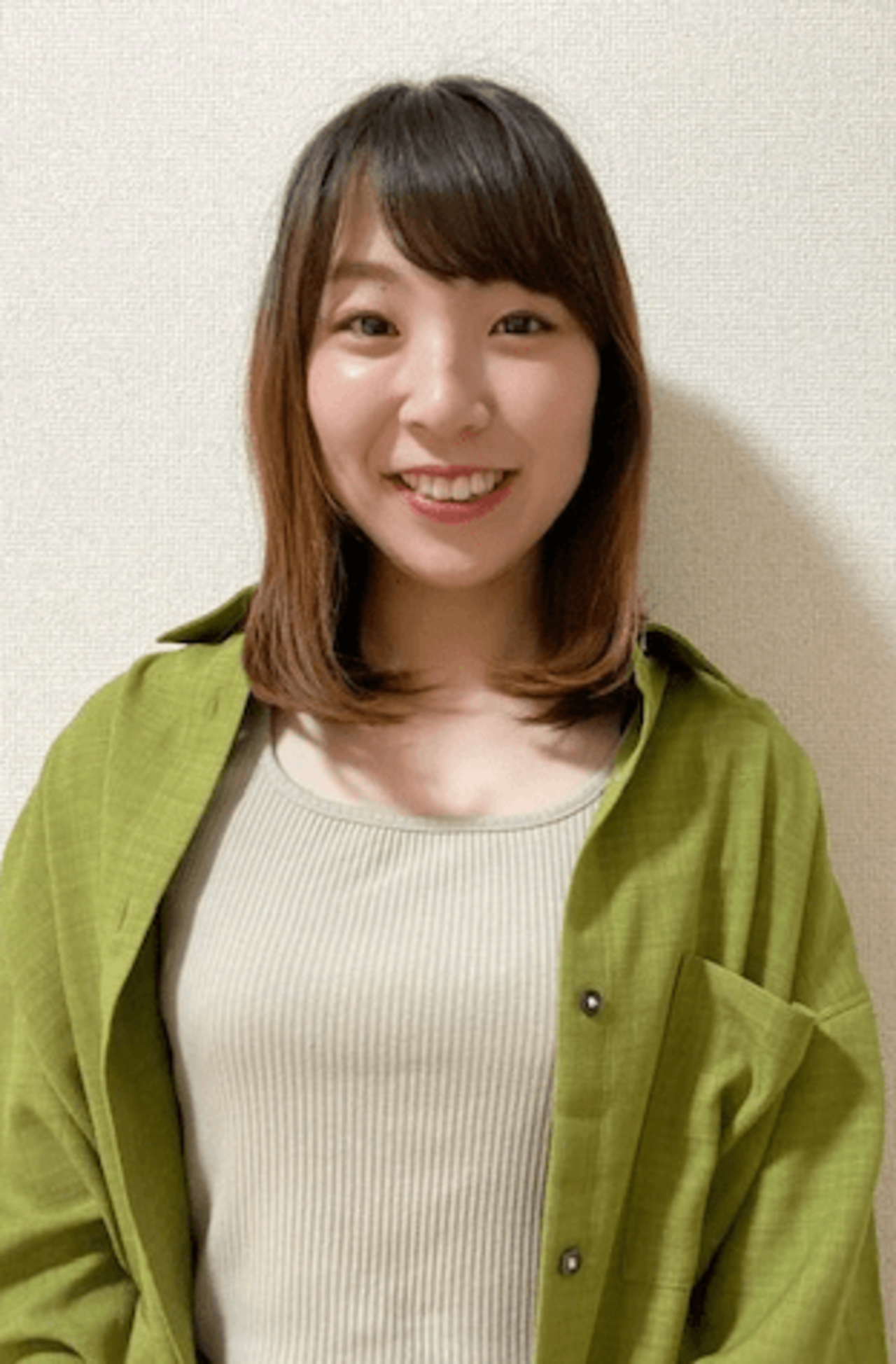さらに大学生の姉が帰ってきた。都会の大学へ進学したが、感染症対策のため、大学がしばらく休校になるらしい。バイトもできない、友だちと旅行にも行けないとブーブー文句を言っている。二階の廊下ですれ違いざまに、
「これ、原宿で買ったの」
そう言って一枚のTシャツをくれた。薄いデニム生地のTシャツにポッケやらボタンやら色んなものがくっついていて、ぼくには見たこともないデザインだったし、これを着ているぼくも想像できなかった。
「え、これぼくに?」
“ありがとう”という言葉の前に思わず聞いてしまった。
「そうだよ」
真顔でぼくの目をじっと見つめた姉は、三秒もたたないうちにふふっと笑い、
「彼氏には小さすぎたの」
といたずらな目で答えた。
「そんなことだろうと思ったよ」
そう言いながらも彼氏の次にぼくのことを思い出してくれたことは嬉しかったのでそれに対しての“ありがとう”を心の中で言っておいた。若干にやけた顔を隠すために首をすくめながら足早に部屋へ戻る。
クローゼットを開けると、その派手なTシャツは衣装ケースの一番上にしまわれた。
母は変わらず忙しそうだ。毎日家族四人分のごはんを作り、洗濯をし、姉の愚痴を聞き、父のパソコンを時々覗いている。ぼくには何も聞かずにいてくれる。
久しぶりに家族四人で過ごす日々が続き、ぼくの日常が家族四人の日常になっていった。
その日の晩ごはんはカレーライスだった。
「またカレー?」
姉が言う。なんだか懐かしい。ぼくたちがまだ子どもだった頃は週に一回はカレーだった。
「野菜もとれるし栄養満点なのよ」
母のこの返事もずっと変わっていない。
たしかに、ホウレン草、ジャガイモ、玉ネギ、ニンジンのゴロゴロ具合と隠し味のコーヒーから出るコクが絶妙にうまい。
オレンジがかったあたたかみのある食卓の電球が三人の顔を照らしている。その前にはできたてのカレーが並べられ、はやく食べてよと言わんばかりにほくほくと湯気がのぼっている。最後に母が席に座ったところでいただきますをする。