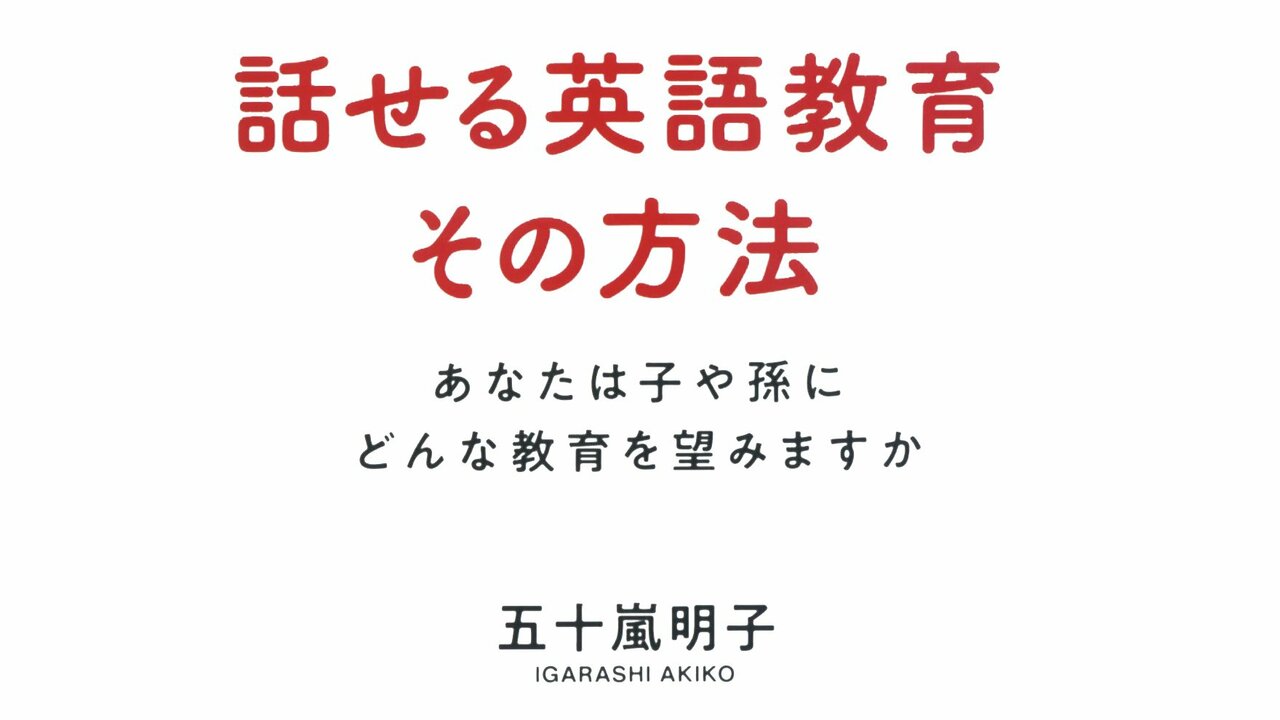【前回の記事を読む】英語教育論争の実態…大正時代の英語学者「低学年への英語教育は弊害あり」
大正から昭和にかけての授業風景
次に紹介するのは、大正中頃から昭和初期にかけて、旧制中学校で実際におこなわれていた訳読の授業の様子です。
旧制中学校における退屈な授業風景を澤村寅二郎(1885年~1945年英文学者、1910年東京帝大英文科卒、文部省在外研修員として渡英、1923年東京高等学校教授、1927年東京帝大助教授、1944年退官:著者注)が多少戯画化してはいるが、目に浮かぶように再現しているので、長いが引いておく。
鐘が鳴って生徒が教場に集まる。教師が教壇に現れて、生徒は礼をする。教師は出席簿を読む。生徒たちは互いに談笑したり、鉛筆を削ったり、書物やノートを出したりしている。
教師は「今日は何ページの何行目から」と言って、閻魔帳を見て一人の生徒を指名する。生徒は立ってreadingをする─どもりながら、一緒に読むべき単語と単語とを切れ切れに離したり、あるいは切り離す単語をくっつけたり、発音を間違えたりしながらある分量を読む。何しろ意味が十分に分かっていないのだから無理もない。
そしてそれを聞いているのは教師と少数の真面目な生徒だけで、他はやはりヒソヒソと話をしたり鉛筆を削ったりしている。厳格な先生ならば、そういう生徒を叱ったり、一方readingをしている生徒の読み方を訂正し、あるいは出来る生徒に発音やaccentを尋ねたりするであろう。
しかしreadingなるものはたいていの場合、語句を音の流れや音のpatternとして取り扱うよりも、単語を単位とした分解的なもので、教師の訂正は単にreadingしている生徒に対した個人的なもので、しかもその生徒は後でしなければならぬ訳読に気を取られて、その訂正に大して注意しない。
いわんや他の生徒たちも結局は訳が重要なので、試験も多くの場合訳さえ書ければよいのであるから、ほとんど注意を払わない。だから時間を食う割合に一向効果がない。
また教師が無責任な呑気な人ならば、生徒のreadingに対して教師自身もあまり注意を払わず、結局それは生徒の訳す分量を決めるためのようなものとなってしまう。
やがて生徒の訳読が始まる。生徒は何とか語句に訳をつけて責任を免れればよいので、自分の言う事が結局どんなたわ言であろうと、教師に小言を食わないことを限度として、何とかお茶をにごす。他の生徒はどうせ後で先生が好い訳をつけてくれることは分かっているし、殊に訳をしている生徒が出来ない生徒ならば、そんな者の言うたわ言に耳をかしはしない。
今どこをやっているかという事だけ分かっていれば、先の方の自分の当たりそうなところを見たり、また既にその準備が出来ているなら、次の時間の数学の問題でも考えるか、それともノートに先生の似顔でも描いている。
そこでいよいよ先生のreadingが始まる。しかし生徒の待っているのは先生のreadingでなくて訳である。大多数の生徒は十分に調べていないから、この先生の訳を筆記するのが、時間中の最も重要な仕事である。先生の訳がすむと次の生徒が当たって、また同じ事を繰り返す。
かようにして生徒が耳にするもの、少なくとも注意して傾聴するものは、日本語である。英語は単に目によって漠然と認識され、訳読のヒントを得るための印として取り扱われるのみである。たとえ英語を耳から聞くにしても、それは印刷されたものを眼でたどっていながらのことであるから、音としてそれに注意を払わない。(『訳読と翻訳』、p.13-14)
今でもこれと大して変わらない授業が行われているのではないか。(『日本の英語教育200年』伊村元道著/大修館書店2003年刊/62~63頁より)
最後の一文は、2003(平成15)年にこの本(『日本の英語教育200年』)を上梓された伊村元道先生のご推察ですが、心当たりのある方が多いのではないでしょうか。