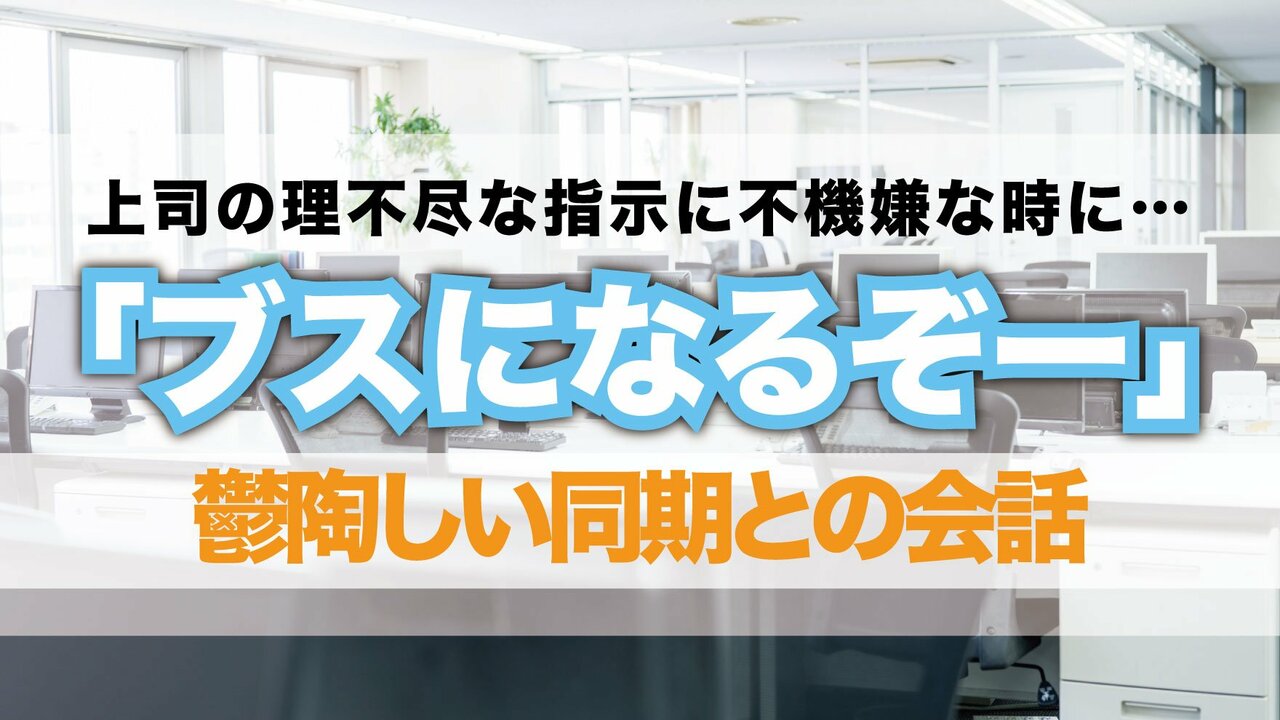入力作業を始めようとすると、水元さんが休憩しようと美雪を誘った。もう昼だった。美雪は休憩室の窓際の席に座ると、ふああっ、と大きく伸びをしてそのままバタンとテーブルに突っ伏した。
「ちょっと、大丈夫なの?」
水元さんが本当に心配そうに言った。
「……微妙です。仕事もプライベートもこれでいいのか? って思っちゃって……」
本心だった。自分の仕事はこれだと言い切れるものがない。彼にふられた理由もよくわからない。全てが中途半端な気がして、そんな自分が嫌いになりそうだった。
「美雪ちゃん、もしかして自分にはなにもないとか思ってる?」
水元さんがお手製の卵焼きを美雪に食べさせながら言った。美味しかった。砂糖と塩の加減が絶妙で、毎日でも食べられそうな味だ。
「……あ、美味しい。ごちそうさまです」
美雪は言われたことの意味がわからず、卵焼きをほおばりながら水元さんを見つめた。
「私の卵焼き、けっこういけるでしょう? ふんわりしてちょっと甘くて。これなのよ。お弁当にはいつも入っているものだと思ってる。だから入れ忘れちゃったときは物足りなくてすごくさみしい。美雪ちゃんは私の卵焼き」
水元さんはそう言って、にっこり笑った。美雪がきょとんとしていると、切れ長の涼しげな目を近づけてきて囁いた。
「彼氏のことだってさ、その彼がいなくなったら美雪ちゃんにはもう誰もいないの?」
水元さんはいたずらっぽく笑って、ほら食べなと言って卵焼きをもう一つ美雪の口に押し込んだ。美雪は口をモグモグさせながら、水元さんの言葉の意味を考えたがわからなかった。でもなぜだか、忘れてはいけないことを言ってもらった気がした。美雪が自分と水元さんの二人分のお茶を淹れて事務室に戻ると、なんだかざわついていた。
「どうしたんですか?」
美雪は小声で水元さんに聞いた。
「佐藤チーフのお母さんが心筋梗塞で倒れたんですって。今、電話があったみたい」
水元さんも小声で答えた。佐藤チーフは美雪を見つけると早口で言った。
「菅さん、悪い。このノベルティグッズのサンプルを各店舗の店長宛に送ってくれないかな」
余裕のない声だ。佐藤チーフは苦手だが、身内の大事はやはり気の毒だ。
「わかりました」
美雪はすぐに答えた。佐藤チーフは慌ただしく病院へ向かった。ほかの業務と並行して店長宛に文書を作成し、ノベルティグッズのサンプルを梱包するのは案外大変だった。サンプルが小さな物で助かった。水元さんが手伝ってくれてありがたかった。それでも全て梱包し終わったのは定時の少し前だった。