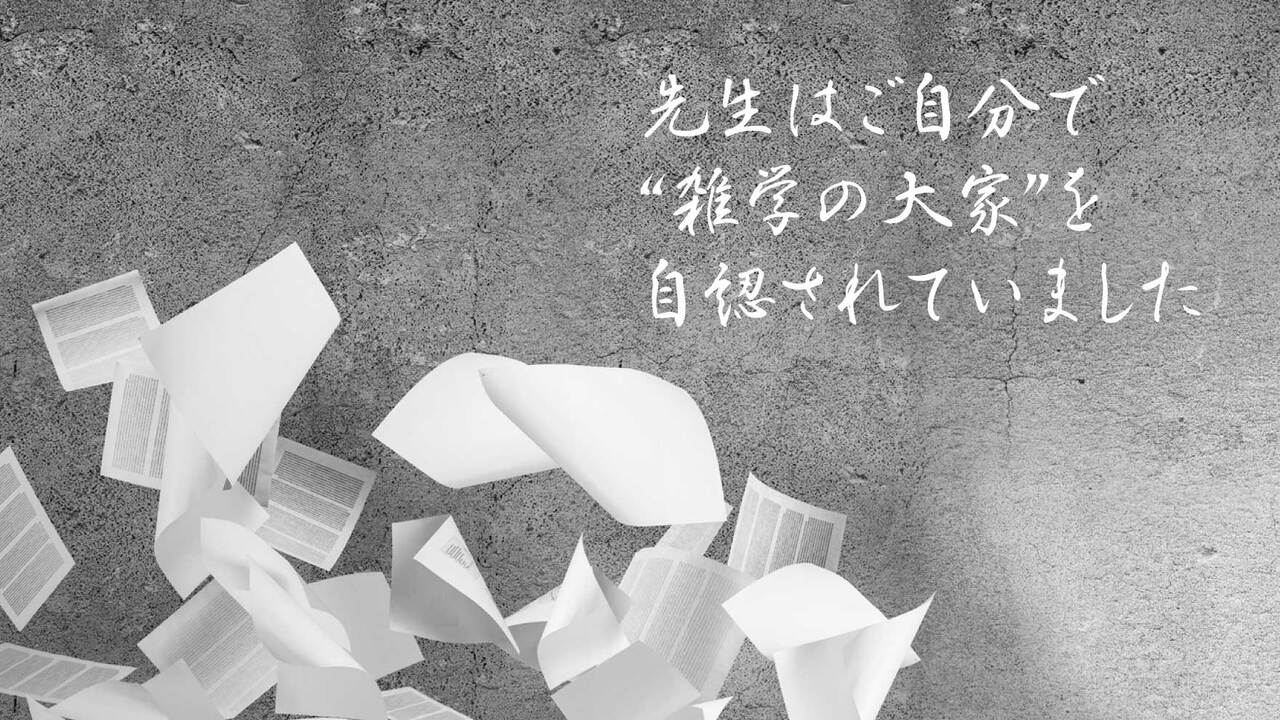プロローグ
「お宅に美術品を買いに来るお客というのはどんな人たちなんですか?」
「主に会社社長かパチンコ屋か開業医、まぁ言ってみれば金回りのいい人たちなんでしょうな。変わり種としては新興宗教の教祖とか。斉田先生は最初うちのお得意ではなかった。でも東洋古美術にはまるようになられてからはうちに頻繁に見えていました……というより昼間はいつ仕事するのかと思うくらいずっとうちの銀座の店に入り浸っておられましたな。
いえ、迷惑だなんてそんな、とんでもない。あの方がうちの店にいると聞きつけてやって来るお客さんが結構いましてね。ついでに何かしら買っていってくれる。こちらにとっては有り難い存在だったくらいです。しかも話が面白くてしょっちゅう人を笑わせていました。
そういえばこんなことがありました。ある時斉田先生のお知り合いがうちの店で先生とばったり顔を合わせてその顔を見て思わずびっくりした。両目の端に鳶だか鷹だかの羽の飾りのついた風変わりなお面をつけていたんでね。思わずドキッとしますよね。初めは誰だか分からなかった。仮面を外したんで斉田先生だと分かった。皆で大笑いですよ。
何でもシチリア人の知り合いから貰ったと言っておられました。そのシチリア人とは国際推理作家クラブで知り合ったとかで、やはりミステリー作家だったそうです。斉田さんは来る人ごとに、それをつけて驚かせて喜んでいました。斉田先生の目黒のお宅にもたまに寄せていただきました。いつも夕方からお客がやって来てわいわいがやがや、来る客も同業の作家から始まって俳優、TVタレント、会社の役員、大学の先生など多彩で毎晩がパーティーでしたな」
出版社社員の男が言葉をはさんだ。
「あの斉田さんの仕事場に掲げられた額入りの“寛山泊”という字を揮毫した書家をご存知かな? 河井凌雪ですよ」
古美術商は続けて、
「とにかく顔の広い方でしたね。先生はご自分で“雑学の大家”を自認されていました。晩年は中国の古美術にも造詣が深くなられてね。いや、“晩年”という言葉を使うのは抵抗がありますね。亡くなられた時はほんの五十代半ば、私とあんまり変わらない。
でも本物を見抜く目はありました。持って生まれた審美眼というか……あの人が『これはいい』というものは鑑定がつく前のものでもやはりいいものでしたよ。少しずつ勉強されて唐三彩、宋の磁器、明の赤絵や掻き落とし、古い景徳鎮窯にもお詳しかった。
私は冗談めかして将来うちみたいな店をやりますかと聞いたら『そうだな、年がいったら隠居仕事にそれもいいかも知れない』なんて笑っておられましたよ」