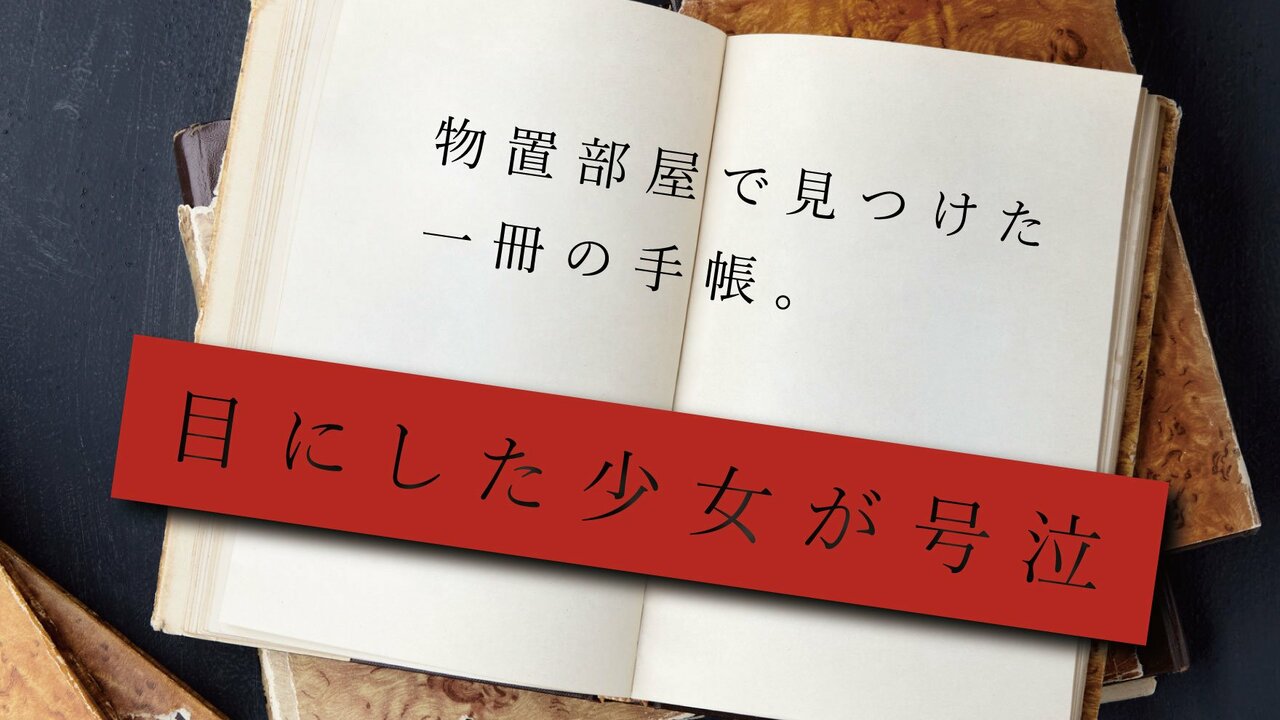「これは、県の将棋大会で、準優勝した時の表彰状やなぁ」
お父さんが将棋を趣味としており、それなりの腕前ということは知っていたが、そこまで強いと聞いてさすがに驚いた。
「えっ? お父さん、すごいやん。本当?」
「実はね。将棋は頭をようけ使うらしいけん、頭ようないとできんのと。実里は頭がいいけん、お父さんになろうたら、強くなるかもしれんなぁ」
「ふうん。でも、家ではいつも酔っぱろうとるのにねぇ。じゃあ、右端のは?」
「あれは、青年団の団長を長く務めた時にもろうた表彰状やなぁ。お父さん、長いことしよったけんね。お祭りや餅投げの時には、団長がみんなの前で挨拶するんやけど、その挨拶がえらくてねぇ。『ミチさんとこの息子さんは、挨拶が上手やなあし』ってよく褒めてもらいよったんよ」
「ふうん。お父さんも一応すごいところがあるんやねぇ。でも、今のお父さんは、お酒飲みすぎやない? おばあちゃんからも言うてや」
「仕事、頑張っとるけんねぇ」
「ふうん」
「実里、栗、食べなはいやぁ。うまいでぇ」
おばあちゃんは思い出したように、再び栗をほじくり始めた。
そんなおばあちゃんだったが、お母さんにとっては赤の他人だった。おばあちゃんの昔ながらの非効率とも言えるやり方に対して、お母さんの文句は絶えなかった。
洗濯物の干場が坂を下った川の辺りにあるから、遠くて仕方ないだとか、お鍋を外の洗い場で洗って、そこに干したままにするから不便でたまらないだとか、家中に神棚やら仏壇やらが配置されているから、御供物をする度に勝手に人の部屋に上がり込まれて迷惑だとか、そういった類の不平が積み重なって、毎日の共同生活に大きなストレスを生んでいた。
おばあちゃんもおばあちゃんで、お母さんの働きっぷりに対して陰口が絶えなかった。洗濯物を溜めるとか、食器の洗い物をすぐ片づけないとか、神棚や仏様を祀らないだとか、そういった類の不満が折り重なって、長男の嫁の評価に大きな減点を生んでいた。
二人は直接言い争うことはなかったが、私は、おばあちゃんとお母さんの間に隔たりがあることを肌で感じていて、そのことをいつも憂えていた。