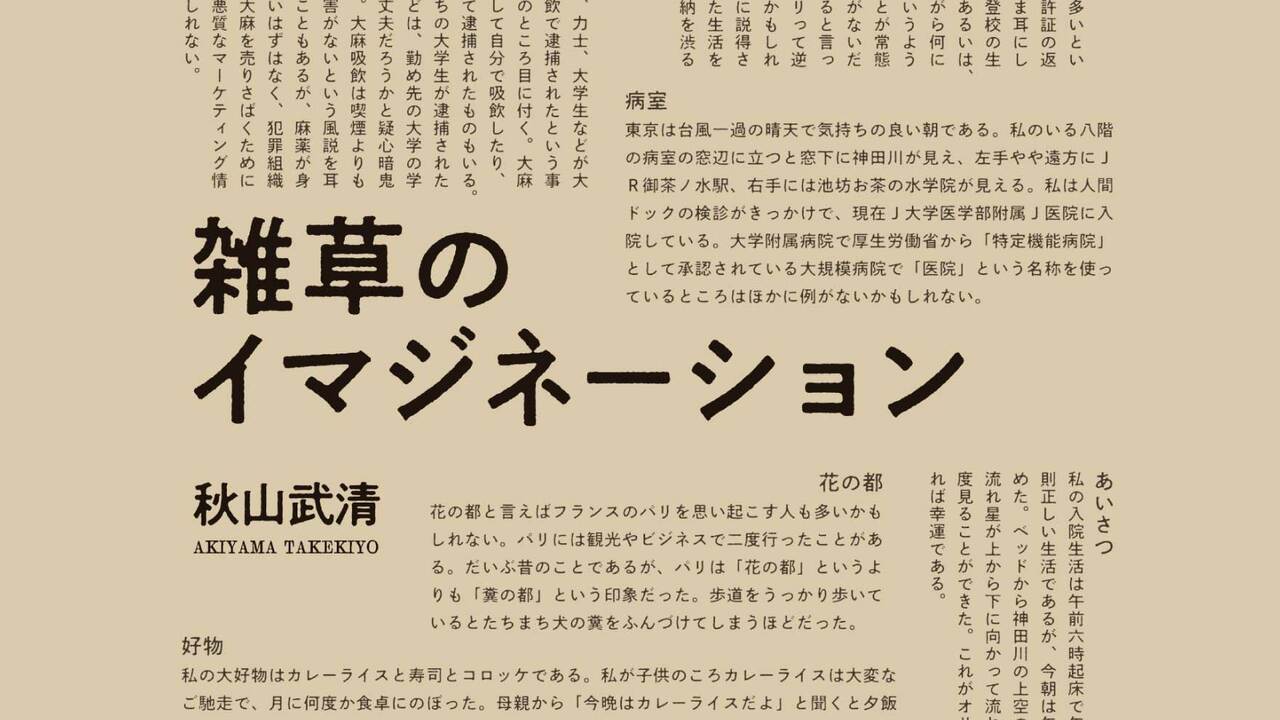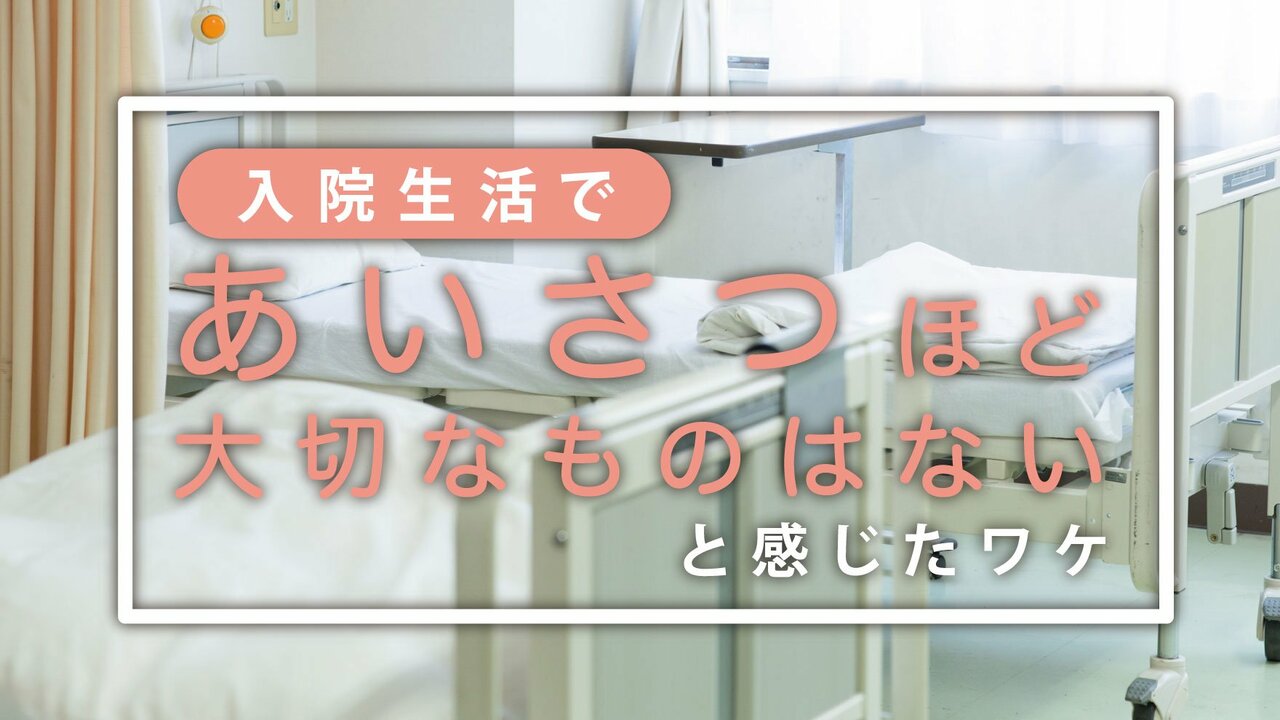民主化なき発展?
「ビジネス英語」の系譜
日本の「ビジネス英語」は横浜の居留地に商館を構える外国商人(外商)と、そこに出入りする日本の商人との取引で用いられた英語を嚆こう矢しとする。
横浜の商館見学に出かけた福沢諭吉は蘭学を学んでいたが看板の英語が読めなくてショックを受け、早速に英語の勉強を始めたという。
片言の英語で外商と交渉しなければならなかった商人の苦労は想像に難くない。当時の英会話の需要は相当なものだったらしく、アメリカ帰りの中浜万次郎(ジョン万次郎)による英会話書を初めとして多数の英会話本が出版された。
日本人は英会話が下手だと言われるが、もしも居留地貿易がそのまま続いていたら、「必要は話しコトバの母」ということで今頃は英語はしゃべれて当たり前ということになっていたかもしれない。
しかしながら居留地貿易は圧倒的に外商に有利だったので、居留地貿易から脱却するための貿易人の養成機関として商法講習所(一橋大学の前身)が明治8年に設立された。商業教育制度の体系が整備されたのは大正期になってからであるが、ビジネス英語の教育は輸出入取引の知識と技能を提供するものとして、貿易実務などとともに商業教育の一環として実行されてきた。
ビジネス英語はまず英国式のCommercialEnglishが導入された。これは主に外国貿易用であり、専門業者同士の通信が中心であった。昭和期に入ると米国式のBusinessEnglishも導入された。
これは主に国内取引用であり、一般消費者を相手とする通信が中心であった。英国式はフォーマルなやや硬い文体を特徴とし、米国式は口語的な文体を特徴とした。英国式をお手本とした日本人の英語を米国人は硬すぎると批判することが多いが、それは米国人の視点によるものである。
日本では第2次世界大戦後は次第に米国の影響が強くなり、ビジネス英語もその例外ではなかった。
「良いビジネス英語」は難しい言葉や専門用語を使わないで、やさしいコトバを使用すべきであると主張され、指導された。
しかしながら、ビジネス英語は「ビジネスの促進遂行を目的とする英語による動的な言語活動である」という本質をついたコンセプトからすると、それは偏った見解のように思われる。
コミュニケーションの当事者は、例えば専門家対専門家(B2B)、専門家対素人(B2C)、素人対素人(C2C)に分類できるが、B2Bは日本や英国の貿易取引を典型とし、専門用語の多用によってコミュニケーションの効率が図られる。
B2Cは米国などの通信販売を典型とし、やさしいコトバの使用で効率が図られる。C2Cはガレージセールなどの不要品の売買を典型とし、日常用語で売買が行われる。このようにコミュニケーションの当事者よって使用される言葉の姿は変化するのが普通だから、B2Bでやさしいコトバばかり使っていると経験の少ない新参者と誤解されかねないのである。
言葉も時と場合によってそれなりの品格が求められるのである。