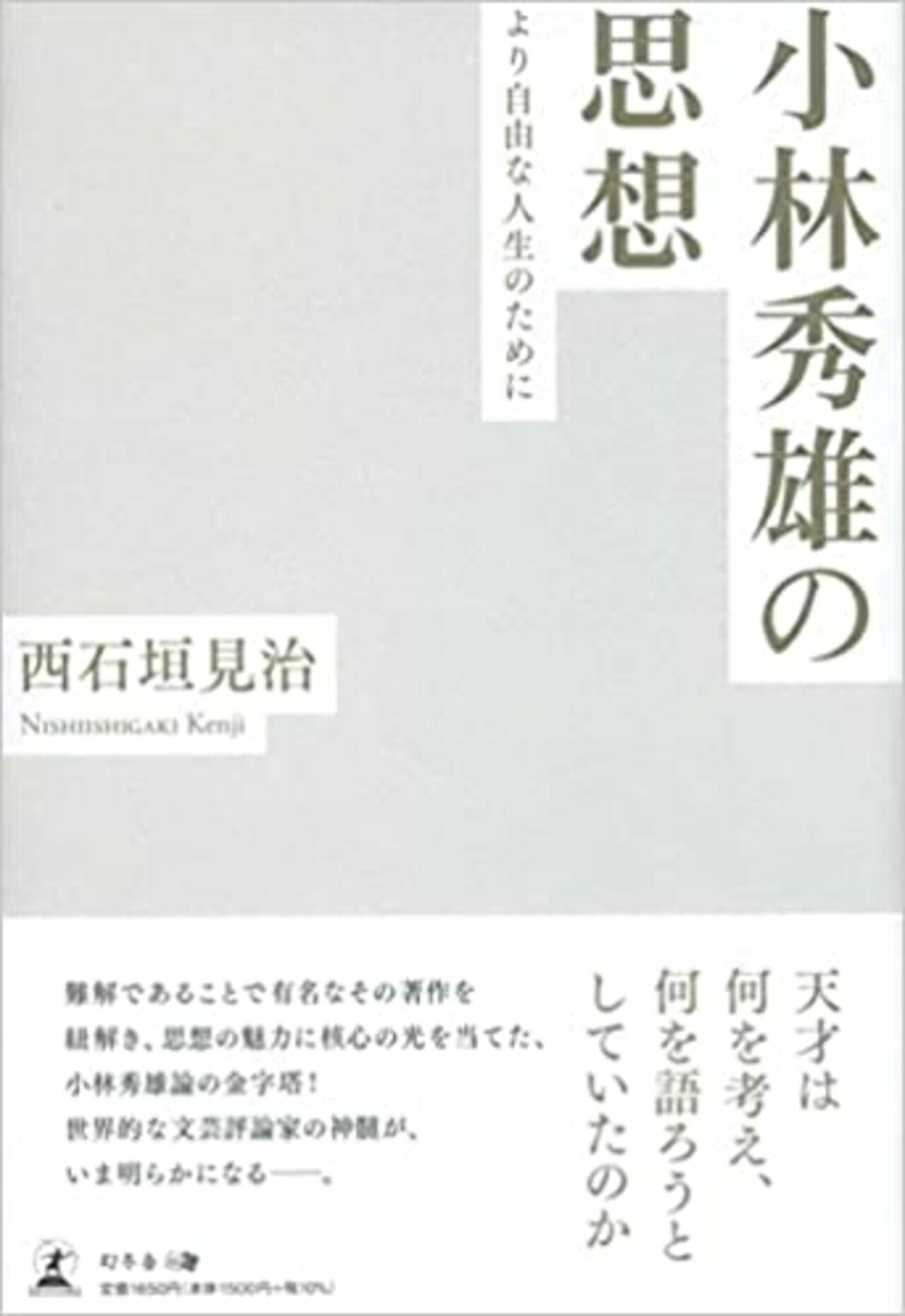【前回の記事を読む】デカルトが「明晰なる無知」の自覚を絶対に手放さなかった理由
「明晰なる無知」と学問は同根で、常識に根差していること
大切なことは、デカルトの「無智の自覚」は、学問遍歴の過程でいよいよ深まったことであり、当時の学問が「根を失ってことごとく死んでいると判断できる自分の自由」の自覚と、コインの表裏にあることである。
事物や秩序の所与性の無意識的自明さが照破されて、その暗黒に没っした内実深くへと、批判の照明が投げ掛けられるのである。浮き彫りになったのは、時代の学問や知の、外見とは対照的な陳腐化した無稽さや、因習的な無意識性なのである。
認識が、その場所で初めて純粋に客観的たり得るはずの、意識ないし存在の普遍的な深みにおいて、当事者的な確信や合理的・理性的な根拠が何一つ存在しないのである。
その隠れた内情が、デカルトの内部の眼にひそかに照射、暴露されて、その容赦のない認識の光の下に、それらを逐一検証し、判断する自由ないし自由の機会がもたらされるのである。
そして、これは単に過ぎ去った、歴史の知の一コマの問題ではなくて、今日においても小林の眼に映じる、知の旧態依然たる光景なのである。
知が、常識との結びつきを断たれて、根無草さながらに、意識の表面世界を漂っているのである。あげく、己の本質的欠陥を埋うめ合わせるべく、科学の権威に筋違いの補償を求めて、肥大化した、異様な科学観さえ生み出すのである。
「科学の発達は、単に科学的技術を発達させるのではない。思想を大きく変えます。周知の様に、十九世紀も半ばごろになると、科学万能の時代が到来します。
デカルトの『普遍数学』の観念が、異常にふくれ上がって、世界観という名で世界を覆うという事になる。そういう事については、彼にはただ自分が夢にも考えなかった『無法極まる哲学』だという言葉しかないに違いない。」(同)
「私は屡々思ふ事がある、もし科学だけがあって、科学的思想などという滑稽なものが一切消え失せたら、どんなにさばさばして愉快であろうか、と。合理的世界観といふ、科学といふ学問が必要とする前提を、人生観に盗用なぞしなければいいわけだ。科学を容認し、その確実な成果を利用している限り、理性はその分を守って健全だろう。」
(『偶像崇拝』小林秀雄全集第十巻「ゴッホ」新潮社)