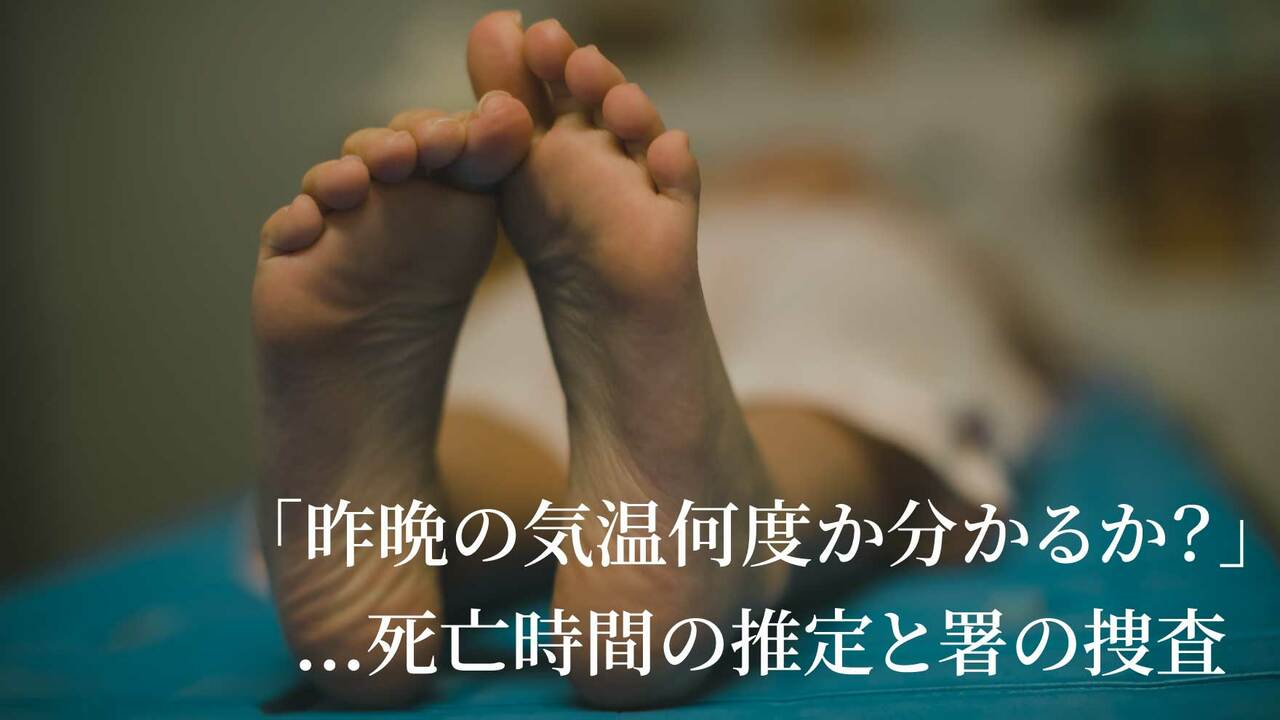検視官の判断で遺体は署に搬送されるが、搬送してもすぐには検視ができない。着衣、身体、爪を中心とした微物とDNA採取などで、ゆうに1時間以上は待たされる。
ただ、世間がいう程、明らかな殺人死体の検視は難しくない。何故なら100パーセント司法解剖事案であることから、死因の判断は不要だからだ。検視で一番悩むのは病死であることの判断が難しい場合や、明らかな外因死でも他者の介在があるのかが不明の場合である。
検案以外に環境捜査(周辺の捜査)を尽くしての検視が必要で、その判断が一番悩むし、ストレスも多い。何もかも不明で解剖に回せば無能の烙印を押され、解剖医からはバカのレッテルを貼られる。そのせめぎあいが難しいながら、この仕事にやりがいと充実感を感じるところでもある。
吉岡は搬送の間に一課長のところへ赴き、他者がいることから、仕事上の会話となって説明した。
「課長、ざっとしか見ていませんが、胸の下付近を服の上から一突きですね、殺しで間違いないでしょう。ナイフ様の凶器で、木製の柄に分厚いタオルが巻かれています。刺した時に自分の手を傷つけないためかと思います。何か通り魔的な凶行じゃなくて、計画的というか、強い殺意が窺われます。たぶん後ろから抱きつくように被害者に覆いかぶさり、口をふさいだ後に突き刺したんじゃないですか」
そう言った時、広域管理官の崎山と顔が合った。
広域管理官とは、捜査一課の特捜班の取りまとめ的な立場にある。いちいち班長に口うるさく指示する者や、班長を信頼して調整役に徹する者など様々だ。崎山が睨みつけるような仕草で何か言い掛けたが、吉岡は無視して続けた。
「突き刺した被疑者は、そのまま被害者を通路まで引きずり横たえたと思います。被害者は右横臥で、丸まったような姿勢です。太ももと胸部との間隔が10センチから20センチくらいの体勢です。死因は出血によるショック死と思われます。この出血の量から見ると、刺されて即死亡ではないでしょう。当然何が起こったかも知れずに、声を上げる体力もないまま亡くなったと思われます。眼瞼部分から頬骨付近にかけて化粧が線上に剥がれています、涙でしょう、可哀そうに。これが私のこれまでの見立てです」