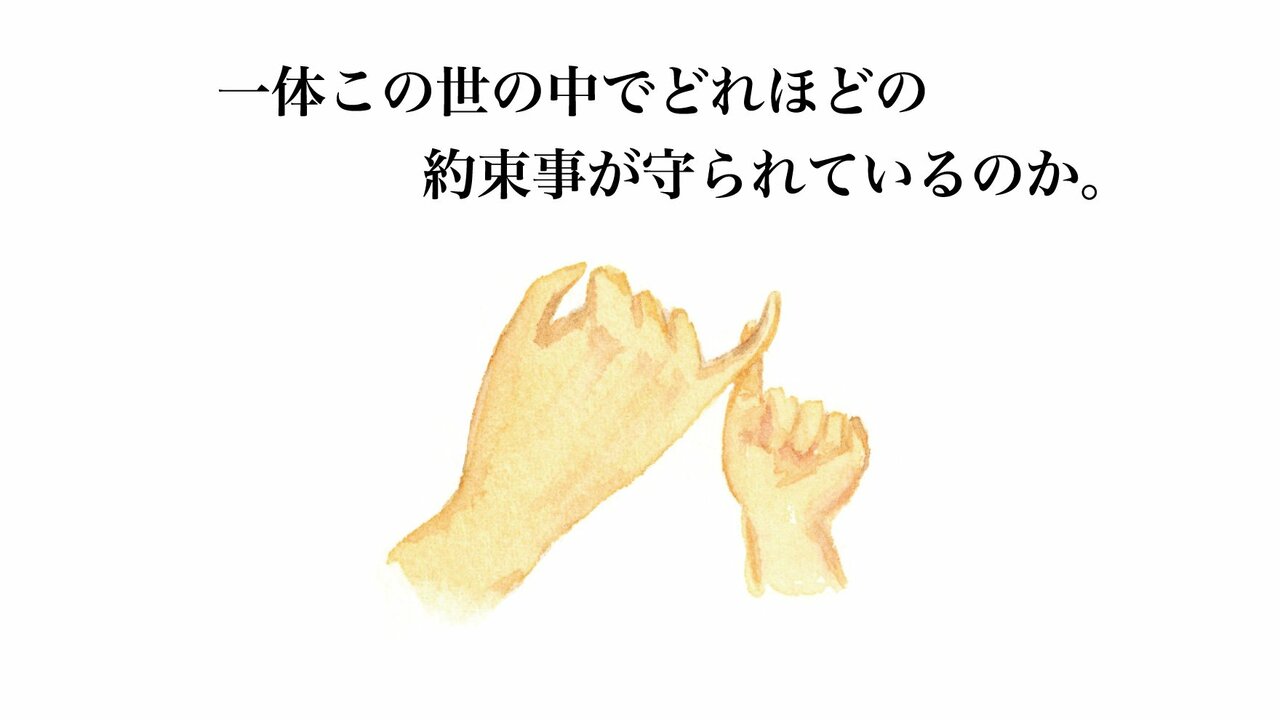【前回の記事を読む】終末期ケアへの宣告…それでも病室で噛り付く玉蜀黍は夏の味がした
覚悟しなければならない時期
このとき病院へは兄と二人で行くよう打ち合わせを進めていたが、哲生から「風邪を引いて行かれなくなった」と連絡が来たので、結局布由子は一人で高速バスに乗った。
病院に着いて洸太と絵里と顔を合わせたが、諭は突然子どもたちが度々訪れるようになったことを訝しんでいる、と後で沙織から聞いた。病室から出て三人で歩いていると、すれ違った年配の男性が「坂口諭君の息子さん?」と洸太に声をかけてきて、二言三言交わした。
布由子よりやや年上と思われるが、黒い髪が豊かで精力的な眼差しのその人は、親会社の会長であるらしい。カリスマ的な存在の会長の前では緊張するので、諭は見舞いに来られるのを嫌がっていると聞いていた。一年以上の闘病を続けていてもなお社長職の返上を迫られないのは、その人の温情なのかもしれない、と布由子は想像した。
布由子は白金台から目黒まで一駅だけ地下鉄に乗るつもりだったが、洸太が「目黒まで歩こう」と言うので、甥と姪と三人で目黒駅まで歩いた。洸太はスマートフォンを片手に、流行りのゲームで野生のモンスターを捕まえるのに夢中だった。夕日が沈む前のうだるような暑さが残っていたが、瀟洒なマンションや庭園美術館の緑が豊かな目黒通りの街並みには、きらきらとした光の粒が踊っているように見えた。
十五分ほど歩いて日が暮れたのでどこかで夕食を食べようと、洸太の選んだ居酒屋のような店に入った。彼らの通う大学と高校の話を聞いていると、洸太は大学院を出た方が建築士として自分が望む就職に有利になるので、どうしても院に進みたいのだと言う。
諭たちと同様に洸太に働いてほしいと願っていた布由子は「院卒が有利」に対して半信半疑だったが、その場で反論はしなかった。高校三年の絵里はデザイン系の学部を志望しているという。未来への希望と、父親を失うかもしれないという精神的であり経済的な不安。その狭間で揺れている二人はときに世知に長けた大人ぶっているが、幼子のように頼りなくも見えた。
二人と別れて沙織が予約してくれていた目黒駅前のホテルにチェックインすると、ほっとするのも束の間、弓恵からメールが届いて「諭さんのお見舞いに行きたい」と訴えてきた。