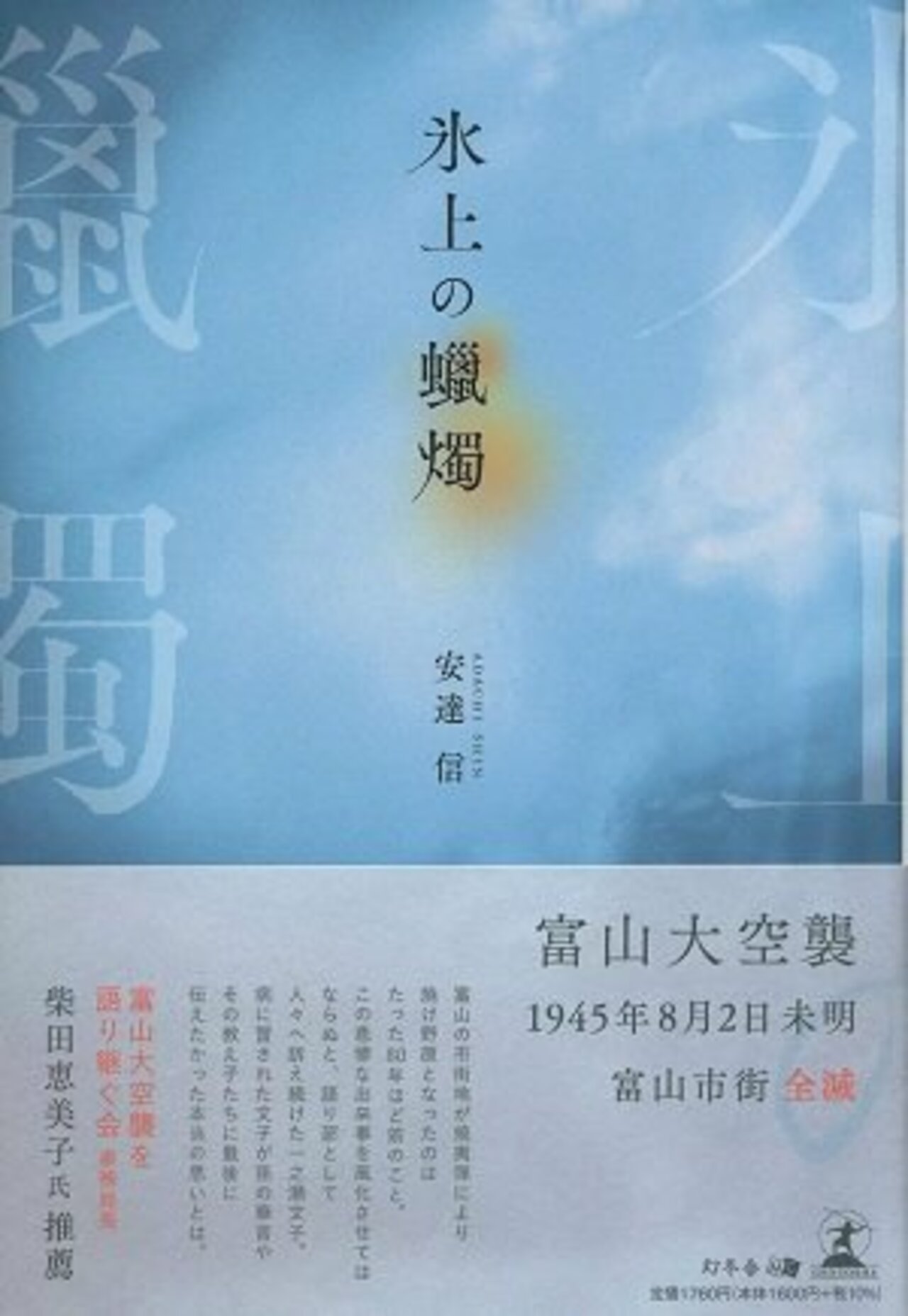【前回の記事を読む】【小説】レイプの情景がトラウマとなって、“うつ”状態に…
一闡提の輩
非常勤講師の小島と瑠衣は、大学の廊下で挨拶する程度の面識であったが、前から好感を抱いていた。推薦してくれた先輩は、小島に習っていた。その先輩は、瑠衣にこのように助言してくれた。
「小島先生はその学生に合った奏法を伸ばしてくれるわよ。フルートに限らず楽器の音色って個人個人微妙に違うでしょう。テクニックも大事だけど、なんといったって最後は音色が勝負だから……。持って生まれた特長ある音色を活かすためには、どの作曲家のどんな曲がいいのかをトコトン学生と話し合い、指導してくれるいい先生よ」
と事細かく説明し推薦してくれた。
「瑠衣ちゃん、内緒ね。坂東先生と小島先生は、門閥っていうか系統っていうか、習ったボスが違うのよ。坂東先生はドイツ派で小島先生はフランス派なのよ」
と先輩は瑠衣に裏情報を教えてくれた。瑠衣は、坂東から小島にレッスン担任変更を願い出ることを心に決め、父に報告することにした。なぜなら、坂東が年一回主催する「坂東フルート音楽教室発表会」に毎年必ず父は聴きに来ており、楽しみにしていたからである。迷った挙句、瑠衣は坂東との出来事を先に告白することを決心した。瑠衣は、父が仕事から戻ってきて夕食を終えたときを見はからって声をかけた。
「お父さん、聞いてほしいことがあるの……」
「うん、わかった。お風呂に入ってから瑠衣の部屋に行くから」
と言って父は風呂場に向かった。瑠衣は自分の部屋に戻り、暗がりの中いろいろな局面を想定してみた。坂東との一部始終を報告すると、父の性格からいって直接大学や警察あるいは知り合いの弁護士に相談するであろうことは容易に想像できた。瑠衣のことを一番心配し、親身になって考えてくれるのは父であることは十分すぎるくらいわかっていた。瑠衣にはそのことがわかりすぎているがゆえに、父に頼りすぎてはいけないとの思いも交錯し迷った。
レイプされたあと、瑠衣はインターネットで性暴力に関する相談窓口を検索した。そこには地方自治体からNPO法人、独立行政機関など様々な組織の活動内容や相談手順が掲載されていた。それぞれの組織に共通して、被害者本人の意向が最大限尊重されること、プライバシー保護が絶対条件である旨がうたわれていた。しかし、そういった組織に相談するのであれば、わざわざ父の力を借りるまでもなく自分で行動していたと瑠衣は思った。瑠衣は、なぜ父に「聞いてほしいことがあるの……」とつい口走ったのか自分でも気持ちの整理がつかなかった。
「どうしてだろう?」と思いあぐねているうちに、瑠衣は坂東から受けた性暴力がフラッシュバックしているような感覚に陥った。それを打ち消そうとするもう一人の自分がその場にいるのに気づいた。坂東との悪夢のような出来事とは真逆にある父との楽しかった思い出を誇張することによって、二重写しのように“善と悪”が駆け引きしている光景が頭を駆け巡った。それはまるで振り子のように善と悪が行ったり来たりしているように見えた。