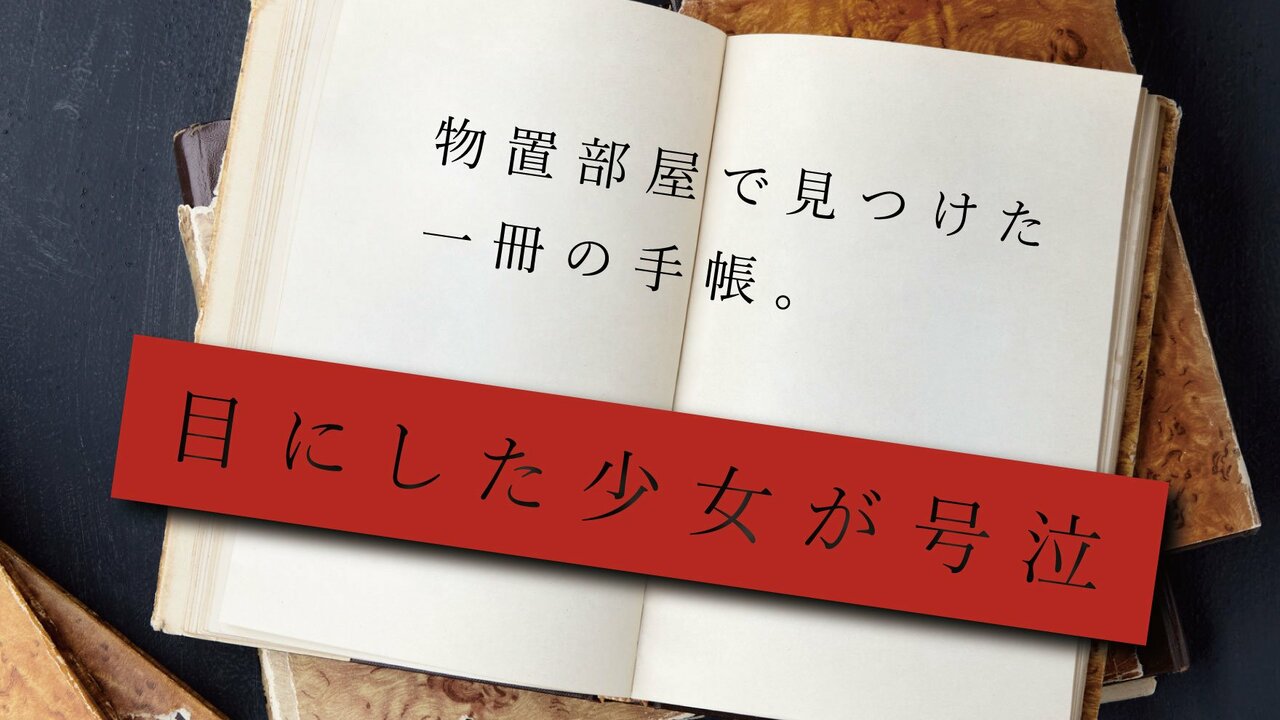二
困るくらいお調子者の私は、自分の意志とは関係なく、大酒飲みの父を持った。私の幼少期の父の記憶、それは、酒を飲んでいる姿に始まり、その姿で終わると言っても過言ではない。
お父さんは、毎日、朝から晩まで飲んでいた。実際には、早朝に学校に向けて家を出ていた私が、朝から酒を飲む姿に遭遇することはあまりなかったはずなのだが、「朝から晩まで酒を飲む」というのは、誰かから聞いたのか、休みの日に見たのか、私の中ではお父さんの代名詞のようになっていた。
お父さんが自分で選ぶのは専らビールだったが、アルコールが入っていればなんでも飲んだ。そして、家中の酒を飲み干すまで飲んだ。「浴びるように酒を飲む」という表現は、お父さんのために生まれてきたのではないかと思うほどだった。
お中元やお歳暮の時期になると、中身がぎっしり詰まりすぎている缶ビールのケースや、立派すぎる大きさの日本酒や焼酎の瓶が届いた。
ある冬の朝、霜で濡れた庭の百日紅の木の下で、大の字で寝ているお父さんが発見されたことがあった。前日の昼すぎに、受け取ったばかりのお歳暮を機嫌よく開けていたお父さんの姿が思い出された。あれだけあった細長い缶ビールは、きれいさっぱり空になっていた。よくよく考えれば、真冬によく無事だったものだ。
お母さんはその贈り物が届く度に、「ありがた迷惑よ」と言っていた。余談だが、私はこの贈り物のおかげで、小学校に上がってすぐ、「ありがた迷惑」という単語の使い方を習得した。先生が出した宿題に、「ありがた迷惑よ」と言って、げんこつをもらったことがあった。