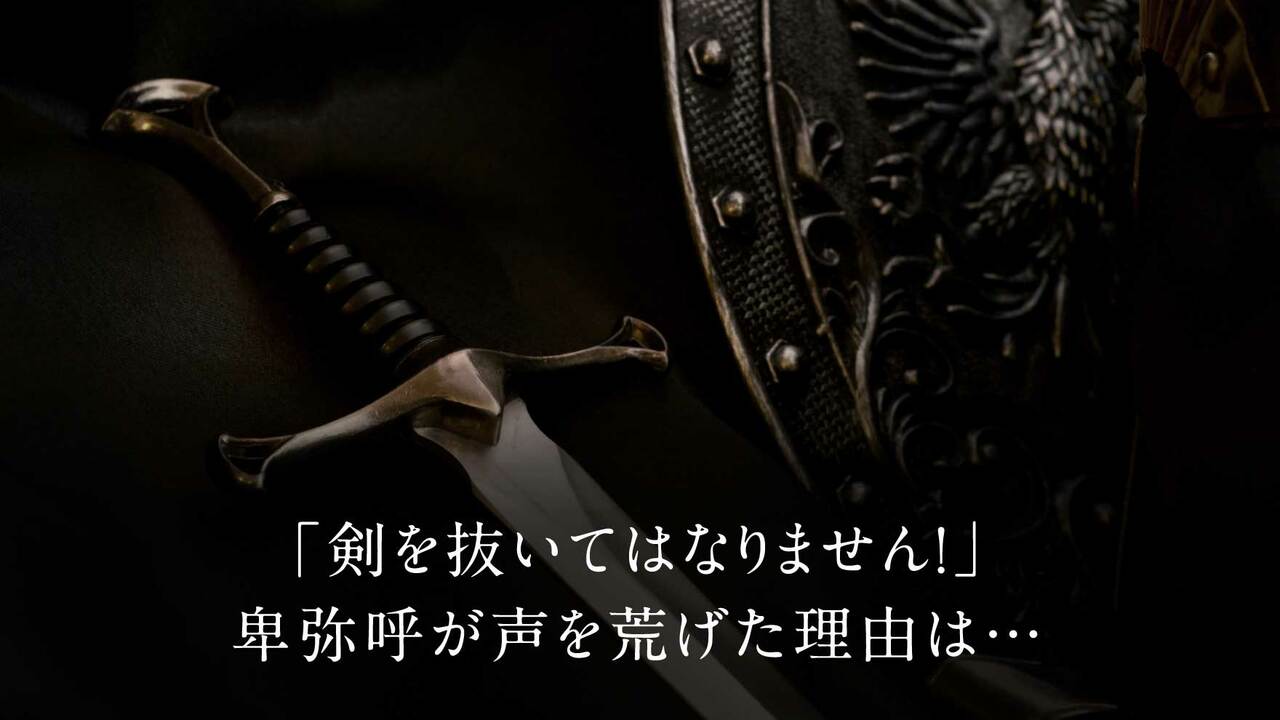柩の蓋にスコップを押し当て並行に動かし、要領よく礫石を掬い取っていく、用意周到、もとより作業の手順は決まっていたようなのだ。徐々に柩の全容が見え出すと、これもまた明日美の推測通りの箱型石棺だった。縦が約2メートル、横1メートルほどで表面は磨かれ、白く透明感があり、柩もまた無駄に大きくもなく女王の威厳と気品に満ちていて希代の美しさである。これまで柩の容姿に感激を覚えたなどという経験はなく、被葬者の意思を受けて埋葬した人たちのこだわりを感じた。
かといって重い蓋を持ち上げるのは危険が伴い無理と思われる。ところが決まった手順に従ってたんたんと作業は進んでいくのであった。蓋をスライドさせるのだ。そのスペースを作らなければならない、もう少しばかりの時間が必要となったとはいえ、その間も質問は続いていた。
「副葬品はどんなのが入っているのかなぁ。女王様だから綺麗な装飾品が多ければいいんだけどなぁ。そんでもってこれも盗掘じゃないよね、お父さん」
「明日美、お前も聞いただろう、お願いした通りに始めてちょうだいって。奇妙な話だが、被葬者の依頼でしている発掘作業だ。大丈夫だろう、たぶん」
箒で柩の蓋を掃きながら佳津彦は苦笑いを浮かべている。
悪い言い方だが墓を暴く手はずは整った。二人ははやる心を抑え、ツルハシの先を蓋の横にある隙間に差し込み、まずはテコの原理を使い隙間を広げた。それでもまだ中は見えない、次はツルハシを逆さまに持ち替え、広げた隙間に柄の部分を差し込んで、再びテコを使いスライドさせるようにずらしていく。程々に開いたところで柩の縁を支点にして、作用点を蓋の裏側に斜めに置き、かけ声と同時に持ち上げるように少しずつずらしていくのだ。