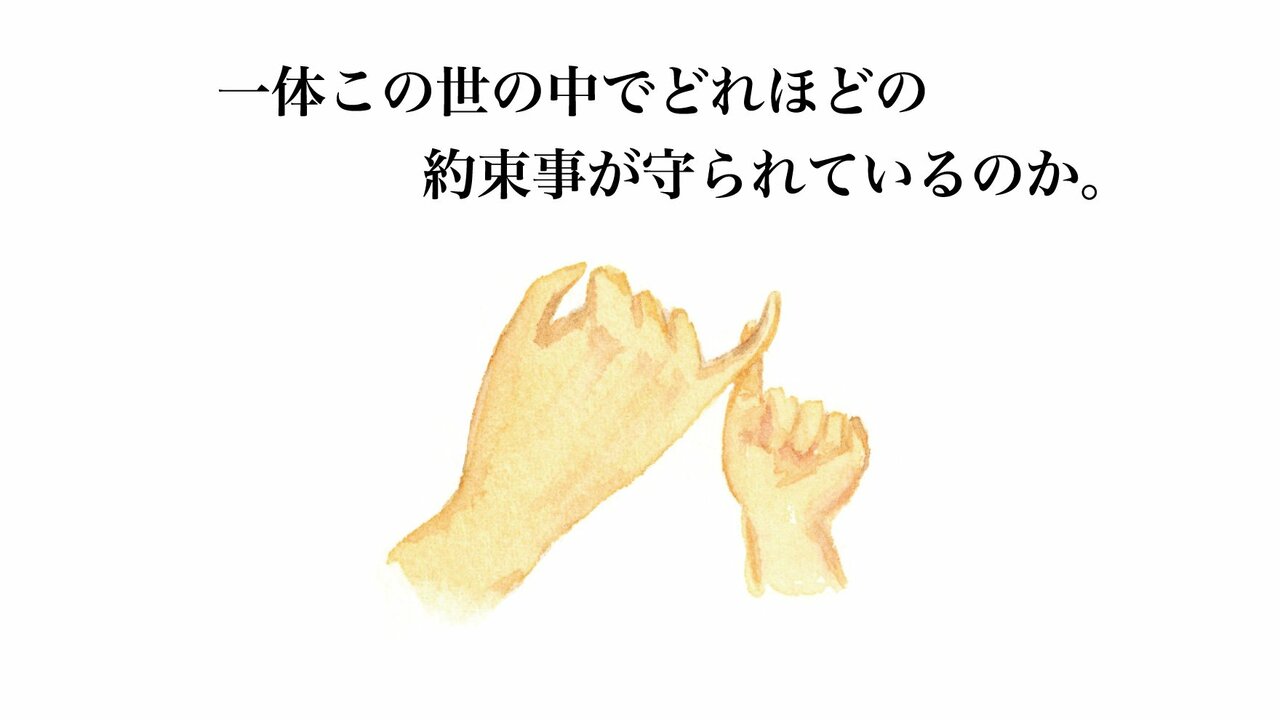【前回の記事を読む】【小説】白血病の弟へ贈る本をどうしても選べなかったワケ
諭の病気
郷里の両親は布由子より三歳年上の兄夫婦と同居していたが、兄哲生の妻は三年前にがんの一種で亡くなった。母は一年前から右半身不随になり週五日デイサービスに通っている。父は家の周りの畑仕事や母が家にいる間の介助を行い、兄は会社勤めの傍ら家事全般を担いながら八十代の両親の面倒を見ている。
同じ市内の嫁ぎ先に住む布由子もできるだけ実家の手伝いに行くようにはしているが、自身の仕事上の責任も重い立場になっており、夫の両親と同居する自分の家庭もあるので、手伝う時間には限りがあった。その上に弟の病気を知らされたときは信じられなくて、布由子は小さな悲鳴を上げた。
なぜまた実家の家族に不運が襲うのか。なぜ一番若い諭がそんな目にあうのか。兄の哲生もやはり弟のメールに動揺し病状を案じていたが、両親のいる家を空けられなかったし、彼らに末っ子の病気を告げることも憚られた。
布由子は諭のメールを受け取ってから兄とも夫とも相談し、とりあえずその週末に一人で東京へ行くことにした。長野県南部のI市から新宿まで高速バスで三時間半かかるが、昨年布由子の息子の陸が都内に就職したので上京する機会も増えている。交通系ICカードを持つようになって、布由子も都心でのややこしい鉄道各社の乗り継ぎが苦にならなくなった。
スマートフォンの地図アプリを頼りに、若松河田駅から炎天下を五分ほど歩いてたどり着いたのは、高度専門医療を担う近代的な高層の病院だった。教えられていた七階の病室はクリーンルームで、案内どおりに前室で私物をロッカーに入れ手指消毒をし抗菌マスクを着用してから入室すると、ベッドに座ったまま「やあ」と声をかけてきた諭は拍子抜けするほど普通に見えた。
元々色白であり顔色はいいとは言えないが、「びっくりしたよ。どんな調子なの?」と恐る恐る尋ねる布由子に、自身の病状をにこやかな表情で語った。すでに抗がん剤投与が始まっているらしいが、主治医は骨髄移植を前提に治療を進めているとのことだ。
「子どもたちは?」
「まだ知らせてない。弓恵に知られると面倒だからね」