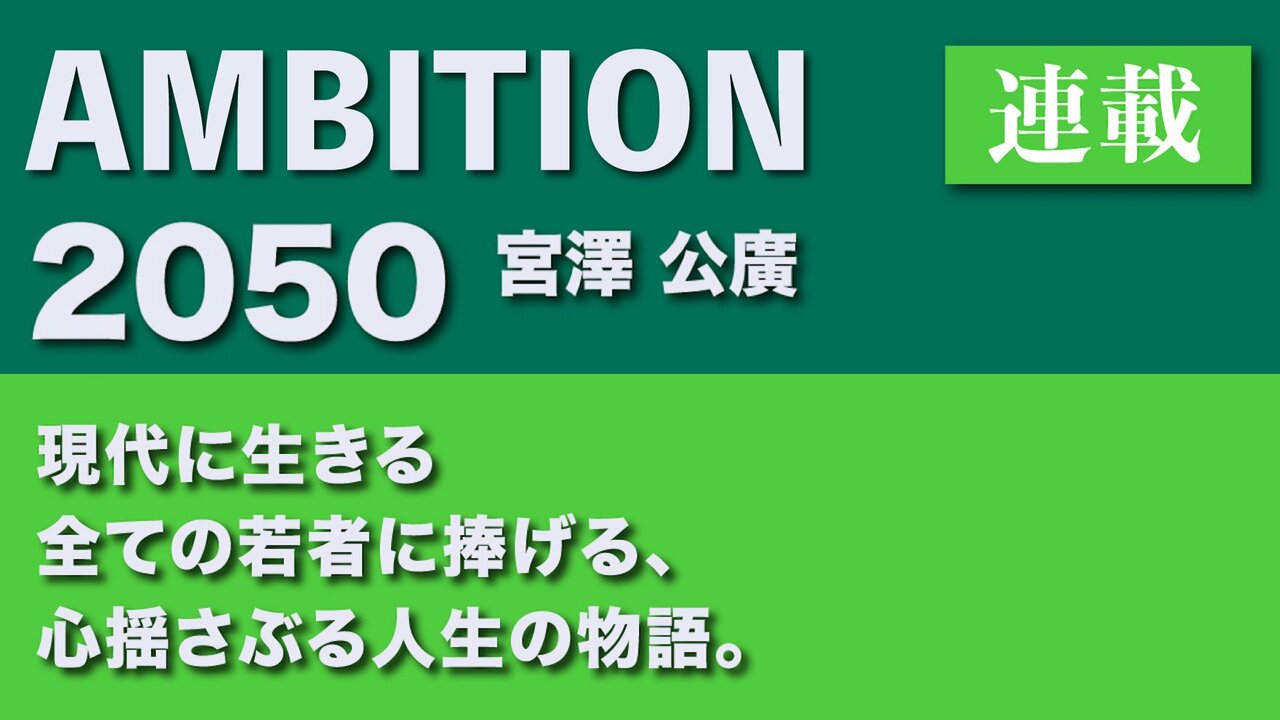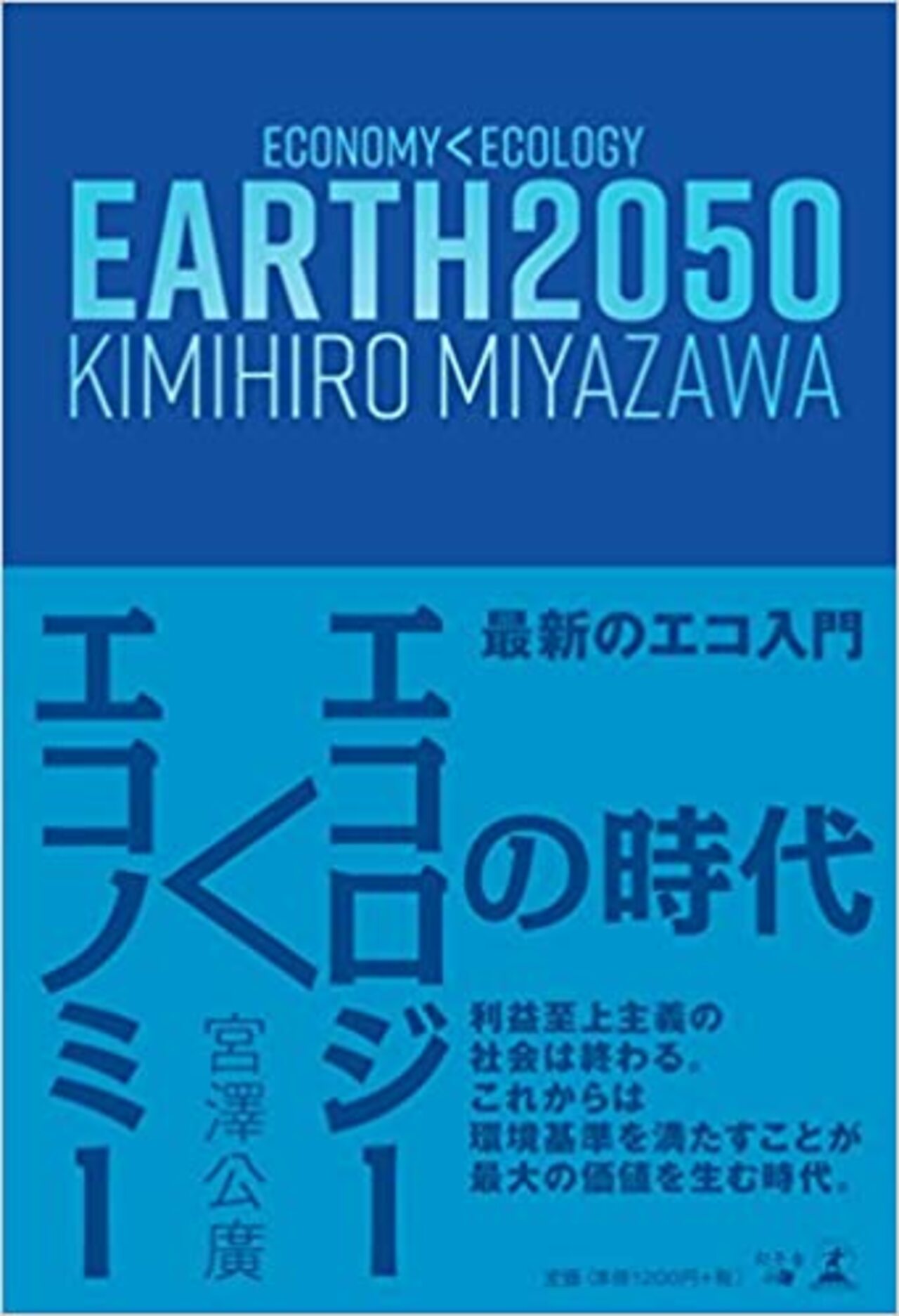第二章 奔走
【1】
宮神が入社したユニオン通信社は、日本を代表する総合国際通信社として知られている。新人記者は地方支局に配属されるのが業界の慣例だ。大抵は五年から十年の間に数ヵ所の支局を異動して回り、経験を積んでいく。
宮神が初めて配属されたのは、宇都宮支局だった。地方支局はとにかく記者の数が少ない。場所によっては五名に満たない支局もある。そのため、事件・事故から町ネタまで、さまざまな分野をカバーせねばならない。
宮神もご多分に漏れず、警察担当ながら高校野球も餃子祭も取材するという慌ただしさだった。記者になった当初、一番面食らったのは、デスクの秋山に原稿の書き直しを何度も命じられることだった。
報道記事には迅速性が求められるが、正確でなければ何の意味もない。加えて、背景にまで思いを馳せる想像力も不可欠である。今でも忘れられないのが、未成年の少年がスーパーで窃盗事件を起こしたときのことだ。記事にするなら、少年の氏名、年齢、住居、場所、時刻、被害状況といったデータを把握していれば書ける。
しかし、秋山はそれでは納得しなかった。少年の家庭環境、友人関係、通学している学校と、詳細を知りたがった。再取材を命じられて警察署に電話をかけるが、ひとつの情報を仕入れて電話を切ると、秋山から別の質問を浴びせられ、怒鳴られる。何度も確認の電話を入れて煙たがられたが、デスクが納得するまで追加取材をした結果、少年が貧しい家庭で育ってきた事実がわかった。
「万引きひとつするにしても、人によって動機はさまざまだ。同じ未成年の少年でも、家庭が困窮しているから仕方なく食べ物を盗む子もいれば、いじめっこの命令で泣く泣く窃盗を働く子もいる。ボンボンの息子だったら、ちょっとしたスリルを味わうために万引きをする可能性だってある。こうやって背景を知ることで、記事の書き方が変わってくるんだ」
秋山にそう言われると、頷かざるを得なかった。短い記事なので、取材した材料をすべて文字にすることはできない。実際に配信した記事も、初めに書いた記事と大差はなかった。
だが、貧困にあえぐ少年の顔を思い浮かべながら書く記事には、いくらか気持ちが込もっているようにも思えた。警察発表やプレスリリースを鵜吞みにしていたら、いい記事は書けない。秋山から直接言葉をかけられたわけではないが、暗にそう言われた気がした。
以来、宮神はとにかく足を使って現場を回った。警察担当のため、大きな事件が起これば夜討ち朝駆けで幹部の自宅を訪れる。もちろん、突然顔を見せても相手にされるわけがない。
普段から各署に足を運び、顔をおぼえてもらうのが先決だ。そうすることで、ここぞというときに重要な情報が聞き出せる。
阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が起こった一九九五年の秋、宮神は松山支局へ異動となった。この一年の報道機関のあり方は、ある意味で狂騒的だった。自然災害と人的災害という違いこそあれ、ふたつのトピックは、連日のように多様な角度から報じられた。
阪神・淡路大震災は、人々の危機意識を高めるトリガーとなった。抗うことのできぬ自然災害によって、何気ない日常が一瞬で崩れ去ってしまうことを知らしめた。
たくさんの命が失われ、神戸の街が悲しみに暮れるなか、全国からボランティアが結集して復興のために力を尽くした。傷口は大きかったが、人間の底力に涙腺が緩むことも少なくなかった。報道では被災者に対する配慮が欠けている面も散見されたが、同業者による読み応えのある記事も多く目にした。
翌々月、災害に対する曖昧模糊とした不安が醸成される中、地下鉄サリン事件が起こった。新興宗教団体の信者たちによる衝撃的な事件に、中央の報道は連日加熱していった。
だが、宮神はそのエスカレートぶりに、どうしてもついていけなかった。記者が被害者に同調する気持ちは痛いほど理解できるが、報道がただの加害者叩きになってしまってはならないはずだ。だが、当時のマスコミは宗教団体に対する憎悪に満ちており、先入観で信者たちを異物と決め込み、社会から排除しようとする方向へと振り切れているように思えた。
大学時代に感銘を受けた「無知の知」は、こんな時にこそ役立つと思った。善悪を論じるのではなく、事件の背景を探りたい。思い込みを取り払って関係者に取材したい。きっと何か別の切り口があるはずだ……。
宮神は事件から遠い四国の地で、歯嚙みする毎日を過ごした。「想像しろ」今でも宇都宮支局の秋山の口癖を思い出す。
自分は一人前の記者になれているのだろうか。宮神は、すっかり冷えてしまった深煎りのコーヒーを飲み干し、自問自答しながら次の取材先である県庁へと向かった。