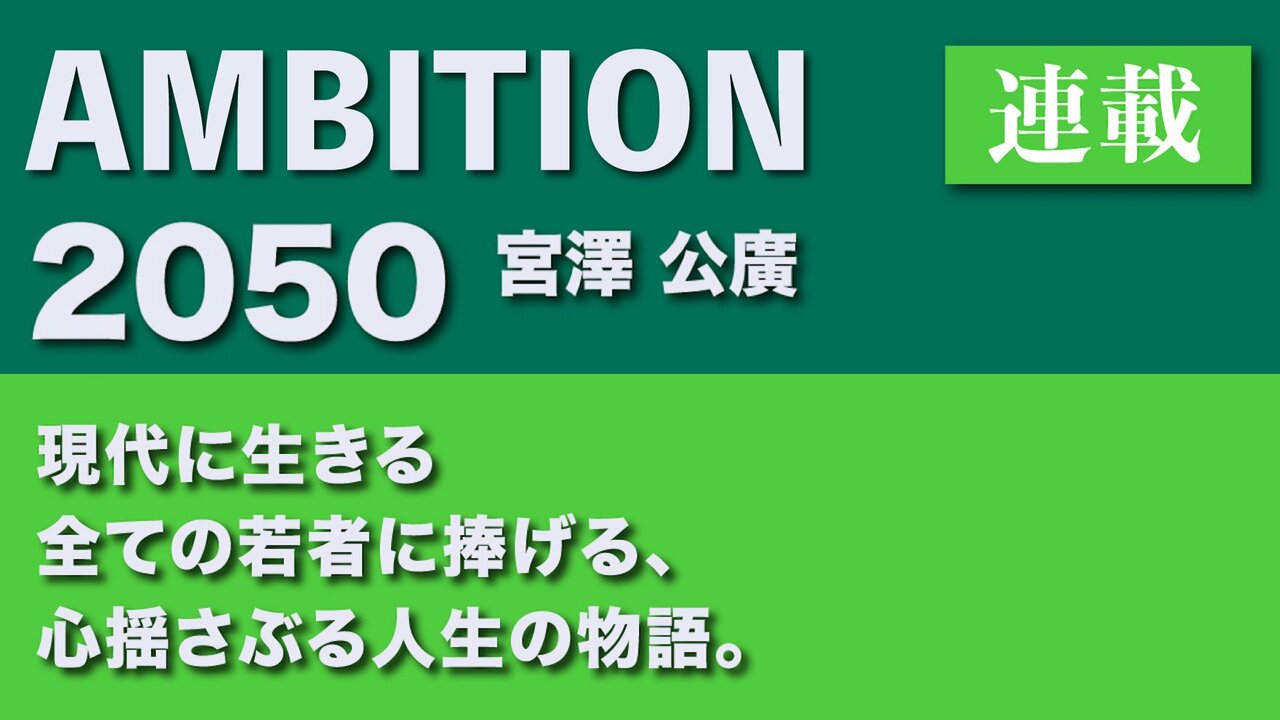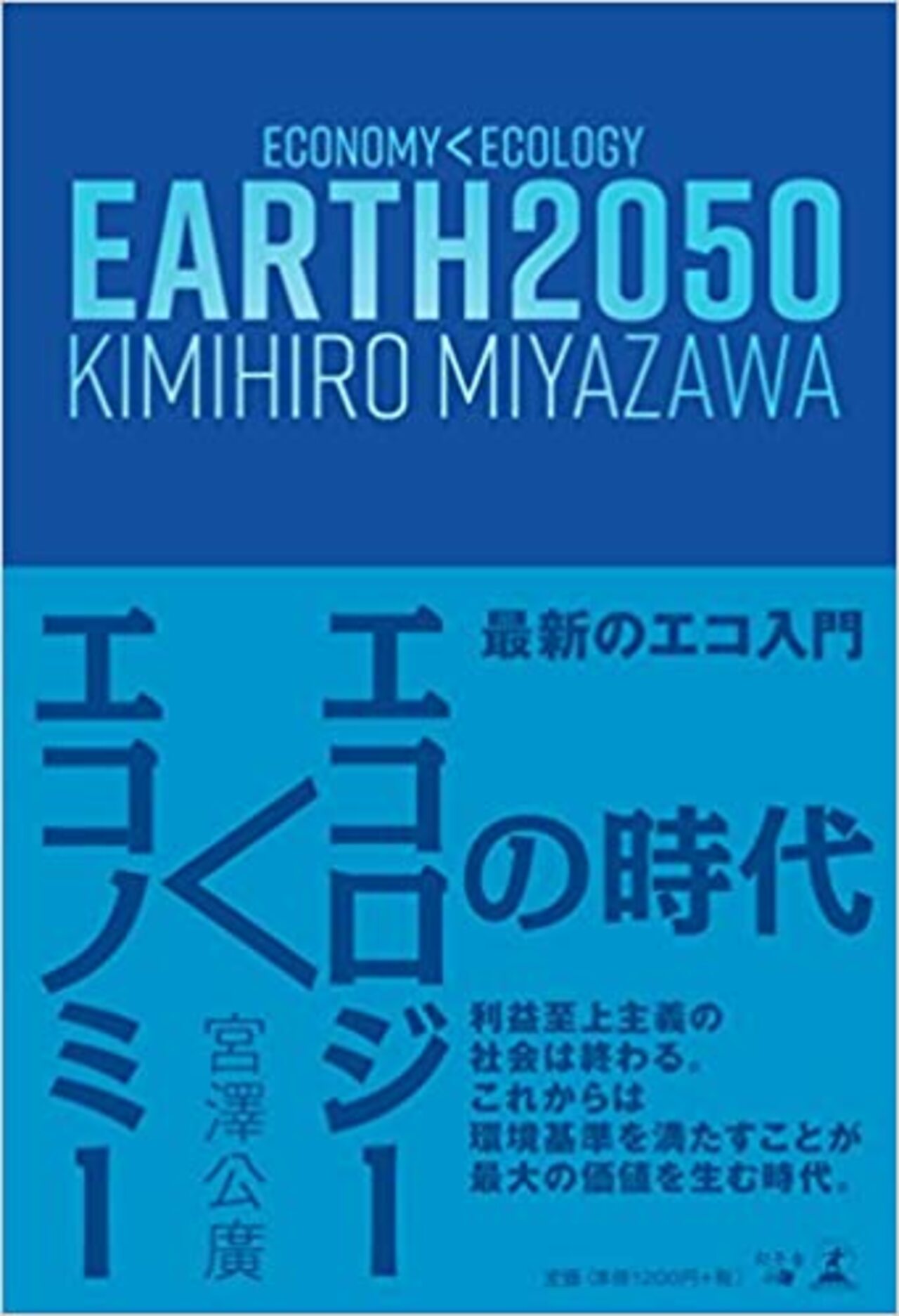第二章 奔走
【1】
薄暗いバーでスツールに座っている。目の前では、ピアノ、コントラバス、ドラムからなるジャズトリオが演奏をしている。軽快なピアノの音色が心地よく、軽く目をつむって音楽に身を委ねた。
ふいに、ピアノの主旋律がまったく聴こえなくなった。バランスとして、ドラムのボリュームが大きすぎるようだ。目を開いてみると、さっきまでドラムを叩いていたスマートな男性が、半裸のモヒカン男と入れ替わっている。
モヒカン男は、まるでロックバンドで演奏するように全身全霊でエイトビートを刻んでいる。うるさくて頭がガンガンしてきた。せっかくの酒がまずくなる。
宮神はバーのマスターに注意を促してもらおうとするが、その姿は一向に見つからない。どうにか演奏を止めさせねば。宮神はそう思うものの、足腰に力が入らずうまく立ち上がれない。ドラムの音はさらに大きくなり、宮神を苛立たせる――。
はっとして目を覚ますと、大音量で目覚まし時計が鳴り響いている。時刻はすでに八時を過ぎていた。いつもなら県警本部の記者クラブに顔を出している時間だ。昨晩、酔って帰宅した際に、アラームを鳴らす設定時刻を一時間誤ってセットしたようだ。
ベッドから飛び起きてクローゼットを開け、スーツの下に着るシャツを探す。が、クリーニング済みのものが一着もない。仕方なく洗濯カゴから昨日着用したシャツを引っ張り出し、匂いを確認する。一月という時期が幸いして、汗臭さは感じない。
多少の不快さを感じながら、二日連続で同じシャツを着ることにした。取るものもとりあえず、ヨレヨレのスーツ姿で家を出る。空は薄曇りで身を切るような寒さだったが、体を動かしたら汗ばむかもしれない。トレンチコートを小脇に抱えたまま、駅までの道のりを走り始めた。
記者クラブ室に到着すると、顔なじみの記者たちはすでに散っていた。それぞれ取材に向かっているのだろう。宮神は携帯電話を取り出し、同世代の記者、太陽新聞の青柳に電話をかけた。
「何だ、寝坊か?」
青柳は、こちらが言葉を発する前から、からかうような口調で話しかけてきた。
「すまんが、警電の結果を教えてくれないか」
「今日は特に何もなかった」
「ひとつ借りだ。必ず返す」
「期待せずに待ってるよ」
それだけ話して、すぐに電話を切った。警電とは、警戒電話の略だ。担当記者が持ち回りで管内の所轄署に連絡を入れて、新たに事件や事故が発生していないかを確認する。朝だけでなく、一日に数回行うのが通例である。
外に出ると、急に空腹をおぼえた。県庁で行われる発表物の取材まで、まだ少し余裕がある。宮神は県民会館の一階にある喫茶店に入り、モーニングセットを腹に入れながら朝刊各紙を読み始めた。