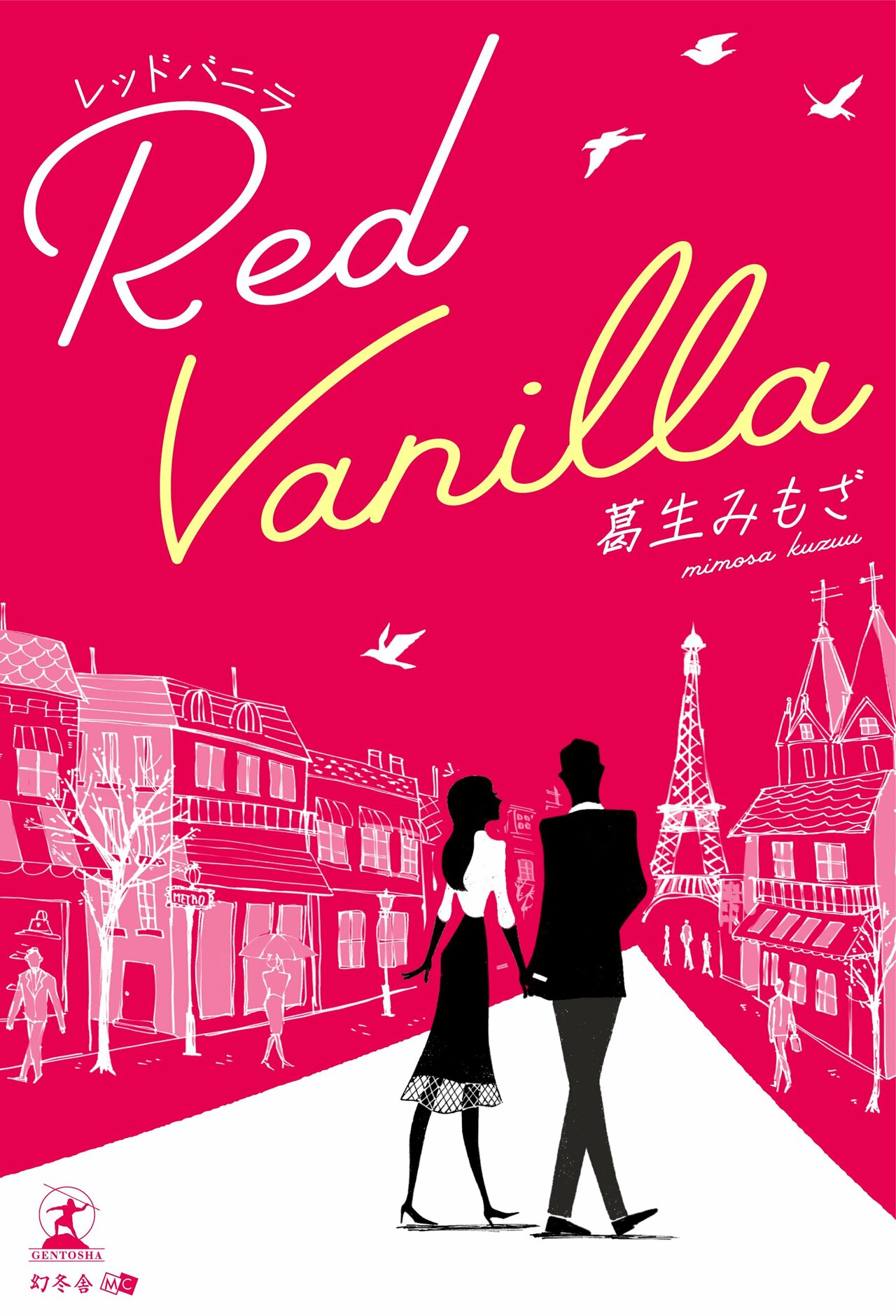宝石のやうなトワレを置く聖夜
二〇一七年のクリスマスを過ぎ、冬期講習を終えて大晦日前日になった。年末年始、今年は働くことにした。今夜は彩子の親友も泊まりに来るので、楽しい年越しになりそうだ。私は、無事に年を越せる幸せを思いながら、明日の特訓講習に備えるため眠りについた。
眠りの中で電話が鳴る。いつもの呼び出し音ではない、特別な人からの呼び出し音のようなメロディーだ。私は夢を見ている。ああ、素敵な夢だ。ほどなく朝が訪れたらしく、目覚まし時計で起こされてしまった。携帯電話のアラームを解除しようと、スマホを開けると、着信のサインがある。誰だろう、こんな朝早く。仕事の連絡かな。あわてて、着信を確かめると、国際電話の表示がある。国際電話!+33.フランスからだ。
出勤前の慌ただしさはあったものの私は、胸の高まりを抑えながらあわてて着信番号に折り返す。ジー・ジー・ジーと海外の電話特有の呼び出し音が鳴ると、とたんに胸も音を立ててドキドキした。すると「アロウ」と低い声がする。懐かしいリヤードの声だ。私は上ずったような声で「アロウ!」と叫ぶと、彼もすぐ、私だとわかったようだ。「元気だった⁉」といつものフランス語なまりの英語が聞こえてくる。
「元気よ。あなたは?」
「元気だよ」
「電話、ありがとう」
これだけ言うと、もうそれで心が通じ合ったことが実感できた。彼のフランス語が受話器を通して流れてくる。でも、よくわからない。でもお互いの弾んだ声で、お互いを懐かしく思っていることはわかる。
「ああ、ごめんなさい。私はあなたの言葉がわからないわ」
流暢な英語で思わず言えた。すると、彼が英語であわてて「気にしなくていい」と三回立て続けに返してきた。でも、とにかく彼は何か言いたそうだった。英語でしゃべりながら、私のことだろう、ベイビと呼んでいる。しかもI Love You.とも言っている。私は驚いたが、そのときの心境は「まさか」よりも「やっぱり」だった。何と言っていいか急に言葉が出なかったのと胸がいっぱいになったので返事をしなかったのだが、彼は通じていないと思ったようだ。ゆっくり「I Love You」と叫んでいる。
わかるから、それくらい。胸から溢れ出た思いは私の涙線を少し緩ませた。
「ええ。わたしも愛しているわ。パリに帰るわね」
「そうだ、それがいい。君がいないとさびしい」
「私の手紙を読んでくれたのね?」
「うん、読んだよ」
「ルーブルが後ろに映っている年賀状も出したのよ。クリスマスカードも。しばらく経ってから届くと思うの」
年の瀬の押し迫った二〇一七年の十二月三十日の朝のことだった。
幸せは、突然に天から降ってくる。
初明り棕櫚の十字架を握りしめ
私はリヤードの電話番号を知ることができて、ショートメールを送るようになった。お互いにフランス語と英語が一文の中に交じっているおかしな文章。
そして、私はまたもパリ行きを計画し始めるのだが、それはなかなか困難を伴うものだった。