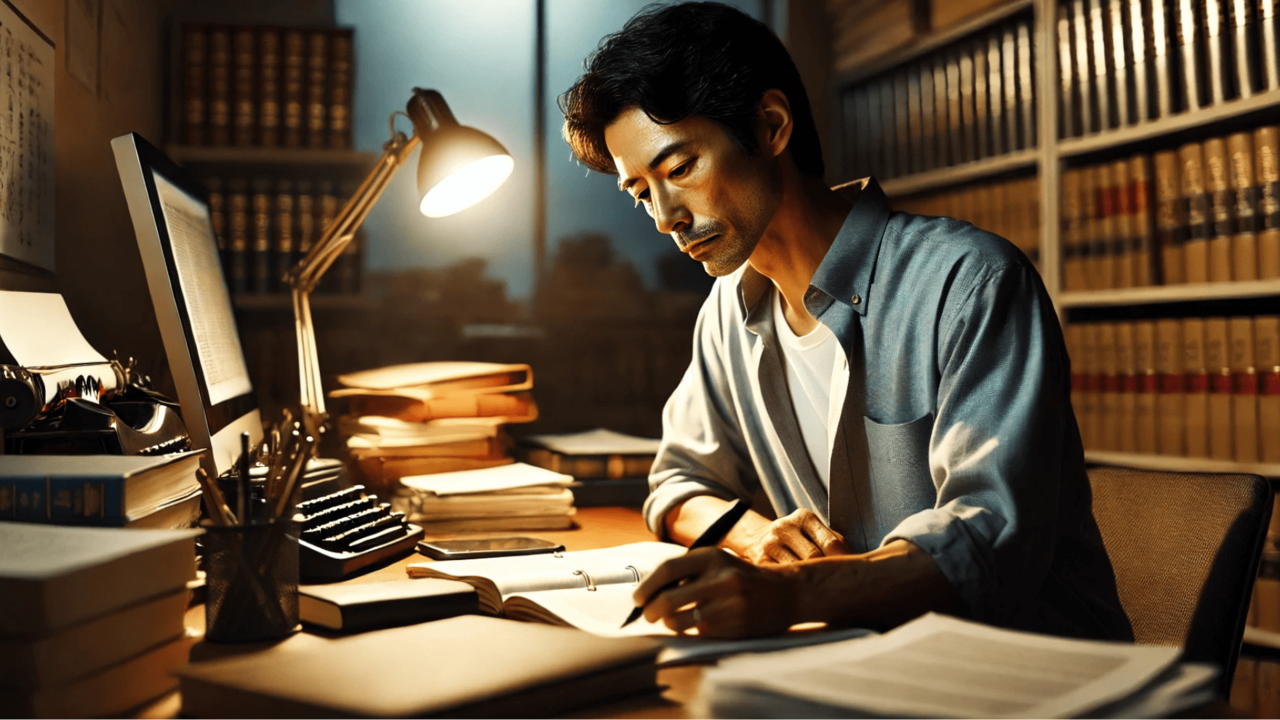第一章 突然の別れ
ヴェネツィアで
S先生は博史の同僚で、早稲田大学国際関係担当副理事。三カ月前にヴェネツィアでの会議のためにいらっしゃって、このアパートで夕食を差し上げた。そのときには息子もいて話が弾み、楽しいひと時を過ごした。S先生なら、ヴェニス国際大学への対処をお願いできる。
「後任の先生のために、このアパートが必要なら、すぐに空けるから。いつでも使ってもらえるようにするから、とお伝えして」
「わかった」
「……ほかのこと……お葬式のこととかは、帰ってから相談しましょう」
「うん、そうだね」
「……それから、朝になったら、両隣と庭続きのお宅にご挨拶に行って。いろいろご迷惑をおかけするかもしれないから」
「……パパ、この家に帰ってもらう?」
「もちろん。パパ、おうちが大好きだったもの。一階の和室に寝かせてあげて」
「でも、あの……寝かせてあげられるようになってない」
夫と子ども二人、かなり散らかしてしまったらしい。だが、どうしても、家に迎えたかった。どこかの会場に運んでそのままというのは、嫌だ。
「お隣さんに、お掃除を頼みなさい。本当に申し訳なくて恥ずかしいけど、この際、仕方ない」
「……そうだね」
思いつくままに話しながら、「しっかりせねばならぬ、きちんとせねばならぬ」と自分に言い聞かせ続けた。やらねばならぬことを口に出して話し合える娘の存在が、私を支えてくれた。
七時発の飛行機に乗るためには、午前三時にはアパートを出なければならない。それまでの間に、荷物を詰めなければ。娘との電話を切って、荷作りを始めた。何を持って帰るべきか。日本に帰ったら、葬儀をしなければならない。その際に必要な物一式。
私は、実父を二十歳のときに病気で亡くし、義母と実母も見送った。親戚や仕事関係の葬儀にも立ち会った経験がある。葬儀の手順はだいたいわかる。今回は、妻としての立場だ。ちゃんとお送りせねばならない。その役目は、ほかの誰にもできないことなのだ。私は、博史の妻なのだ。
まず、棺に入れる物の準備をせねばならない。夫の好きだった物。夫が大切にしていた物。アパート中のクローゼット、棚、机の引出しを点検した。ここぞというときのための背広、ジャケット、セーター、シャツ、パンツ、そのほかの洋服。とっておきだったペンケース、お気に入りの万年筆、普段使いの機能ペン。
胸が苦しくなったのは、ひと月ほど前にヴェネツィアで買ったばかりの靴を目にしたときだった。工房を兼ねた小さな紳士靴店で博史が見つけた、美しい茶色の革の紐靴。博史は私をその店に連れて行って店主に紹介し、「ね、いいだろ」と大喜びだった。
その靴を、胸に抱いた。すぐに込み上げてきた感情を、ぐっと押しとどめた。箱に入れ、バゲージに詰めた。周りをセーターでおおって、箱がつぶれないようにした。博史の思い出をたぐることを、自分に禁じた。感情に負けてしまったら、日本に帰れない。博史が今いるのは日本だ。私は彼のもとに帰らねばならない。