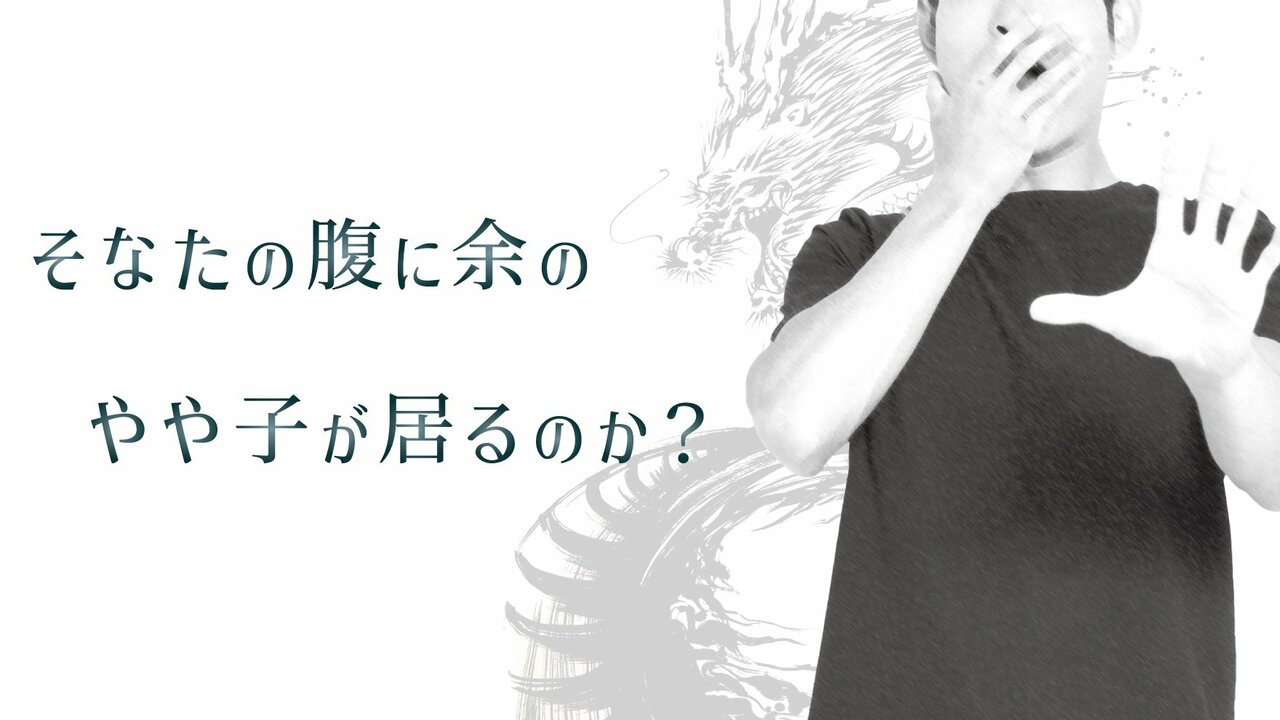「何をするのじゃ? 大事な剣を消すとは……」
「ほう~。そなたの腰に在るのは何であろうかな」
羅技は、何時の間にか左の腰紐に剣が挿してあることに気が付いた。鞘から抜くと素晴らしい美しさを持つ剣であった。
「余の尾にある龍族の唯一の武器である刺と、そなたの剣を合わせた。切れ味は以前のそなたの剣より格段に良い。その剣で仇を討て」
羅技は剣を鞘に納めると、赤龍の背に飛び乗った。
「あれっ? 手綱が無い」
「馬鹿を言うな。余は馬ではない。鬣を両の手でしっかりと摑むのじゃ」
「こ、こうか?」

恐る恐る鬣を摑むと、赤龍の身体が一瞬、黄金に染まった。
「余に宝が出来た!」
「宝?」
「そなたのことじゃ!」
赤龍はふっと笑うと一気に空へ駆け昇った。
「うわっ~」
「落馬。いや、落龍はするなよ! わっはっは~」
赤龍は誇らしそうに高笑いをし、さらに空高く上昇していった。
「剣の鍛練に行く。夕刻には帰る」と言い、重使主と中根とともに出掛けた羅技は、今日も帰って来ず、すでに三日が経っていた。森の奥宮に和清が秘かに建てた小さき館へ逃れ住んでいる紗久弥姫は、心配で食事もろくに口を通らず、眠ることも出来なかった。
それまでの羅技は、龍神守の里の次期当主として和清の代わりに遠くの里やムラに親善の品を届けに出かけることや、里に住む民達に必要な物資を買い付けに行き、十日から半月ほど里を離れることがよくあった。時には里を襲って来たそと人を悉く追い払う為に剣を振うこともあり、畑を荒らす猪や鹿を狩りに数日野宿をすることも度々あった。
紗久弥は羅技が姉上だと知って以来、朝早くから日が暮れる頃まで、父や里の武人達の仇を討つ為に剣の鍛練に森の奥へ出かけては擦り傷だらけになって帰って来る羅技を見て、大怪我を負わない様にと祈る毎日を送っていた。
紗久弥姫はとても心細く、隣の部屋で寝ている侍女達に泣き声が聞こえぬ様に羅技の寝衣を抱き締めていた。瞳からぽろぽろと零れ落ちる涙は、袖で拭っても止まりません。