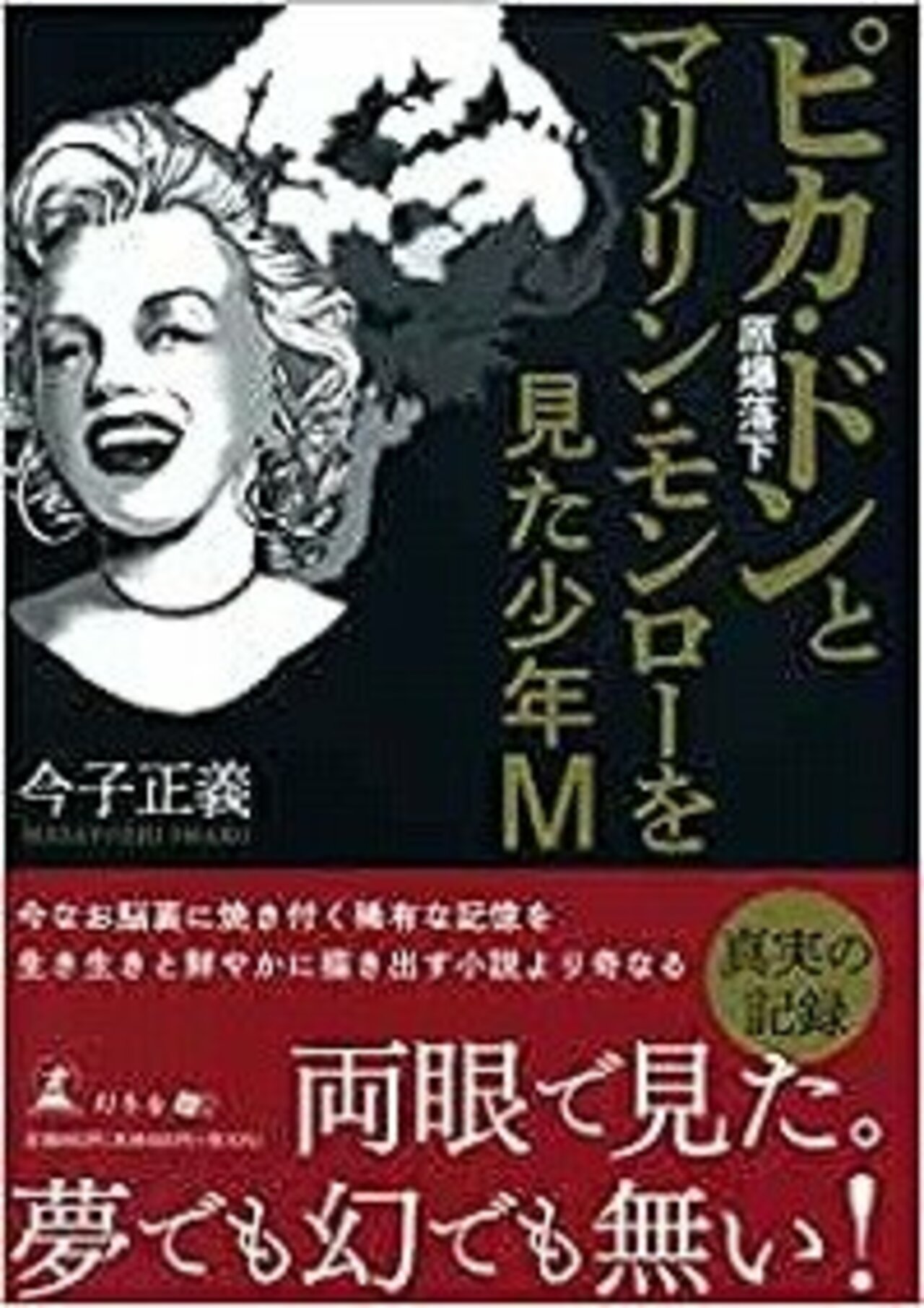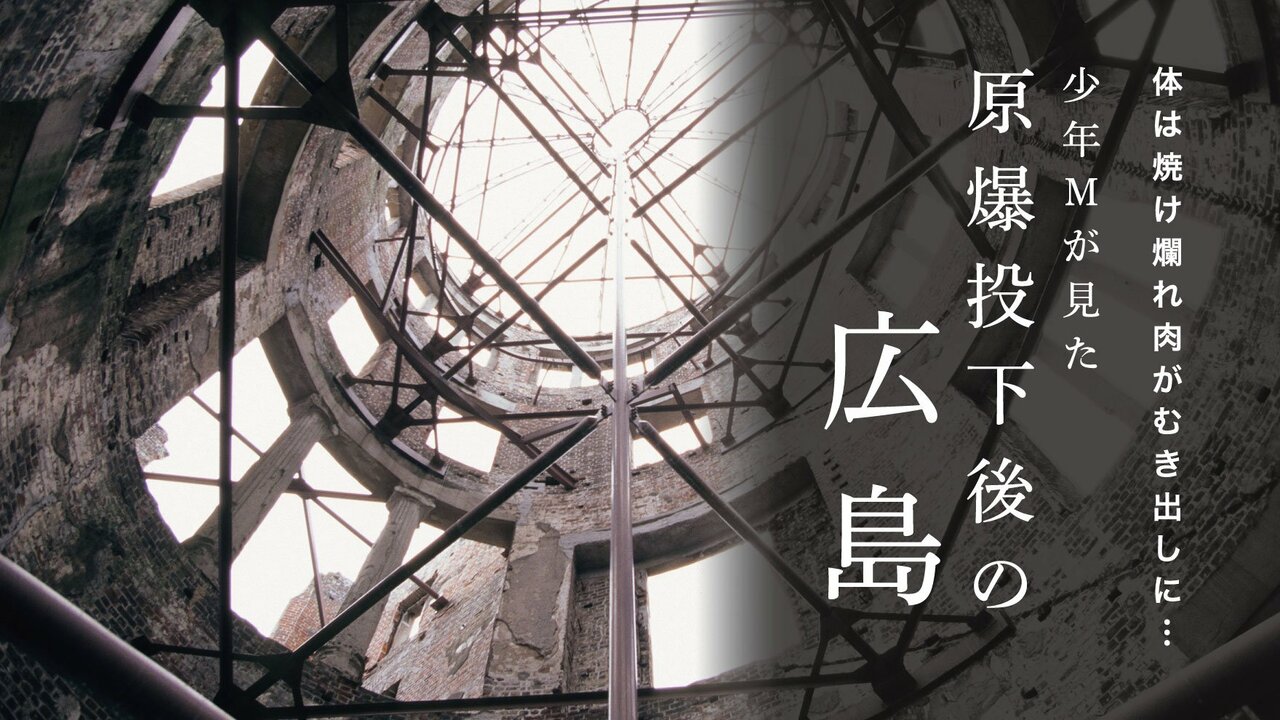玉音放送が流れた日
その日は、昭和二十年八月十五日だった。Mは晴雄の所へ家を引っ越したことを伝えに行く途中、田んぼの畦道を歩いてくると大きい黒い牛がいて、Mが駆け出すと追いかけてきた。走れるようになったMは必死に逃げて近くの家に駆け込んだ。
そこの縁側では数人の大人が集まってラジオを聞いていた。
「ビービー、ガガガッ」と雑音が入ってMには誰が何を言っているのか分からなかった。
「天皇陛下のお言葉じゃったのう。よう聞こえんかったが、日本は鬼畜米英との戦争に負けたんじゃ。本土決戦までやると言うとったのに、これからどうなるんじゃろうかのう」
と、爺やが、がっくりとうなだれた。
Mが「本当に日本が戦争に負けたんか」と問い質した。
「玉音放送で天皇陛下が言うたんじゃけえ、本当じゃろう」
「神風も吹かんかったのう」と、もう一人の老人が頭を抱えた。
「アメリカが来て、わしらは皆殺しされるんじゃないかのう」
と、他の老人が呟いた。
「これから、わしらは、どうすりゃええんかの」
と、おばさんが両手で顔を覆った。
「田舎にもアメリカ兵が乗り込んできて、若い女は連れていかれるんじゃないんかのう」
と、老婆が心配そうにうなだれた。
なんで天皇陛下は原爆を落とされる前に降参しなかったのかと、Mは思った。
ジープで乗り込んできた進駐軍
夏が終わりかけた頃、八重にも進駐軍がジープで乗り込んできた。若くて陽気なGIたちだった。
アメリカ兵ではなくオーストラリア兵だそうで、気が荒くて何をやるか分からないので気をつけるようにというフレが回った。
GIたちがジープに乗って、物珍しげに田舎町にも、やって来た。原爆後の広島を見たくて放射能の怖さも知らずに、やって来たのかもしれない。
甘いお菓子に飢えた子供たちが恐る恐るジープを取り囲んで「ギブミー、チョコレート。ギブミー、チュウインガム」と、行く手を阻んで手を差し伸べた。
Mは体の大きい赤ら顔の若い白人の進駐軍を見て、同じ人間ではないと思うほどだった。
彼らは日本の田舎の子供たちには意味不明の英語で声をかけ、陽気に相手になってくれて、ガムやチョコレートをジープからばらまき振る舞ってくれるので驚いた。
Mは、こんな大きい鬼のような相手を敵に回して戦っても勝てるわけがないとも思った。
やっと一つ拾えたガムを銀紙から出して初めて噛んだ味は格別だった。噛み続け、甘味がなくなっても口から出して取っておき、味がなくなったガムを翌日も噛み直した。