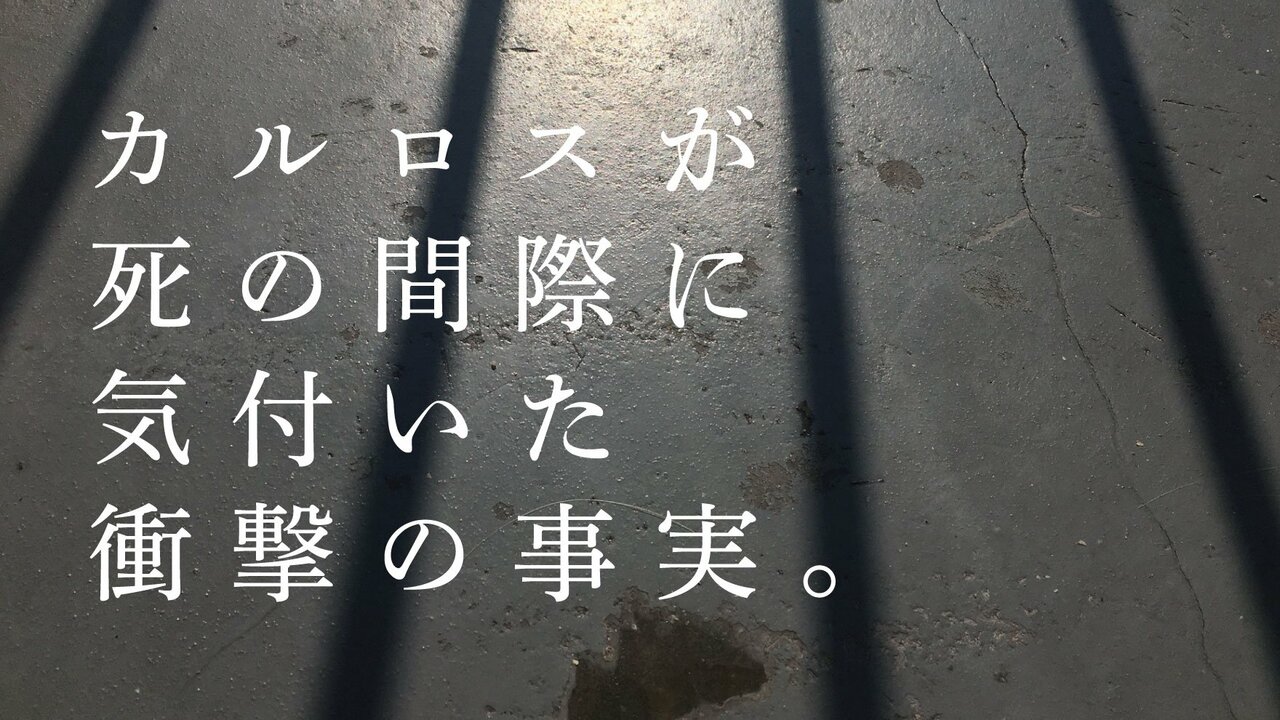体が弱ってくるのとは反対に、カルロスのうったえはだんだん強くなった。診察に来た医師の手を放さないのだった。
「先生、お願いです」
あまり、懸命にうったえるので、ついに願いがかなった。逮捕されてこの病院に来てから、二年がたっていた。カルロスは、いつ死んでもおかしくないほどだったので、刑務官たちの優しい心づかいで、死ぬ前に望みをかなえてやろう、ということになったのだった。
その日、カルロスが目を開けるとへロイーナとソフィアとフランシスコがいた。カルロスの心は、願いがかなった喜びでいっぱいになった。
「へロイーナ」
カルロスが、ふるえる手をのばして呼んだ。
(いいですか?)
とでも言うようにへロイーナは、ソフィアをちらっと見上げてから、カルロスに近づいた。近づいてくるへロイーナを見ていたカルロスの目が、へロイーナの首にかかっている銀のメダルにくぎづけになった。それは、自分が子供だったころ、母と一緒に牧場で暮らしたフィオリーナのメダル、自分が彫った「F」の花文字にちがいなかった。
カルロスの頭に、最後に見たフィオリーナの姿がよみがえった。今、目の前にいるへロイーナが、そのときのフィオリーナとそっくりであることに、初めて気が付いた。
(へロイーナとフィオリーナは同じ犬だ!)
カルロスの混乱した頭の中に、この思いが渦を巻いた。思わず、カルロスの口からなつかしい名前が出た。
「フィオリーナ」
その瞬間、へロイーナの体がびくっとふるえた。へロイーナは大きくとび上がって、カルロスのベッドに前足をかけ、カルロスの顔のにおいをかいだ。ソフィアとフランシスコはわけが分からず、立ちすくんでいた。へロイーナが一瞬にして、子犬に戻ってしまったように見えた。
「フィオリーナ。悪かったな。俺のしたことを許しておくれ」
カルロスはへロイーナの背中をさすりながら、何度も何度も謝った。へロイーナと会った翌日、カルロスは死んだ。口元に、ほほえみを浮かべて安らかに息を引き取った。