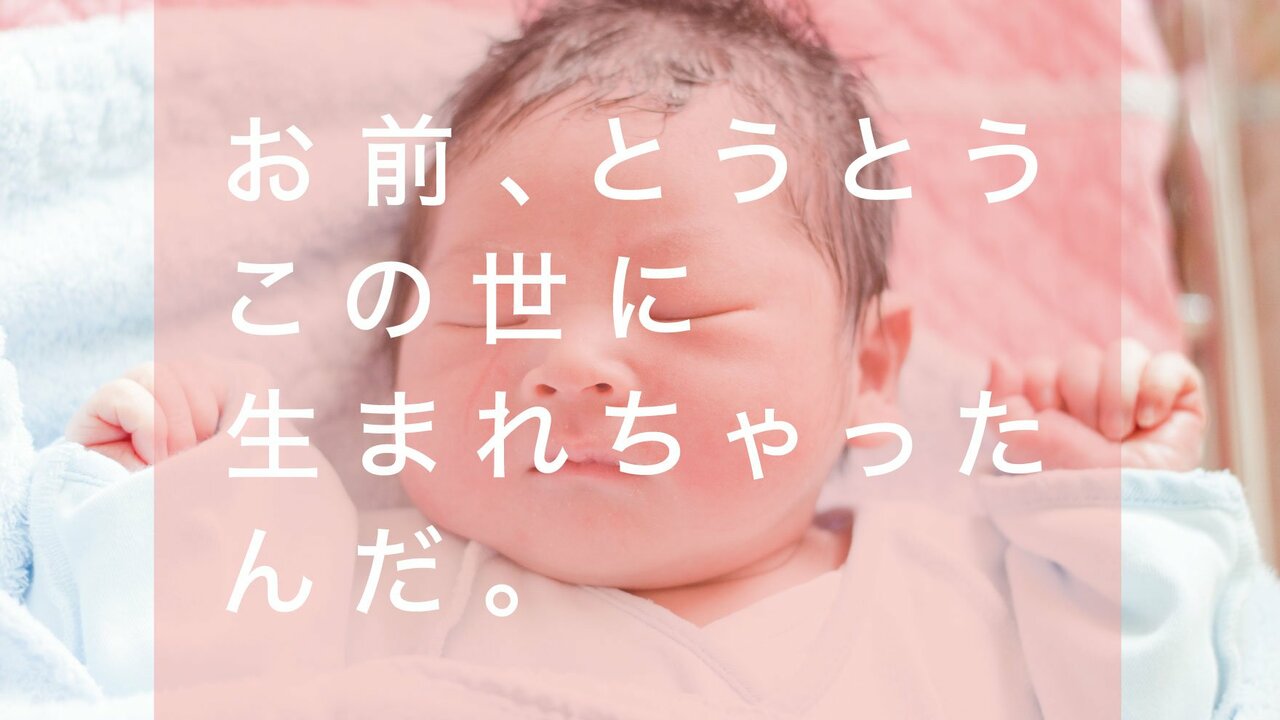『八汐の海』
カードの残高を見ながらゴールデンウィークまで引っ張った。
男らしく(するつもりで)淳の手を引いて送り届けて、かわいらしい母親に謝って
「この人の、理想の男性と違っていました」
傷心の娘を家に入れて、その人は静かに僕にありがとうと言った。僕は己を恥じた。
ありがとうと不思議な反応をしたあのかわいらしい女人は早や他界したのか……
一人娘の見え透いた嘘を許した訳は何だったのか……
両親は教職を棒に振った僕に、自分の蒔いた種だ、自分で刈りなさい、と言っただけ。これも堪えた。姉たちもさすがにこの時は静観するだけだった。
二番目の義兄に、あの子だったと報告したら驚いた。結婚するんだって、と言うと、重信さんはそんなこと言ってなかったぞ。そもそもその昔の一件を彼知らないのかなあ。
僕が想像するに淳の母親は父親に言わなかったんだ。だから重信氏も知らなかったんだ。
人生に、このような邂逅はそうあるものではないだろう。災厄なのか、恩恵なのか。僕を試みに合わせないでください。僕は彼女を不幸にする気はない。彼女の幸せを……けれどももし、願いが聴き届けられるなら、もう一度会いたい、もう一度確かめたい。伏せた眼を上げて僕を視る。今もその眼差しは僕の芯に炎を燃え立たせるだろうか。
両親は老人ホームに一年で見切りをつけて帰ってきた。一年居ればたくさんだ。生方じゃなくて多数の匿名の一人になりなさい、さすれば平等と博愛を提供しますと。俺とお母さんは不平等と偏愛と自由を愛好する。
勤しく動くおばさんが家事を手伝いに来る。父は時々物を書く。母は拡大鏡を使いながら雑誌を見ている。老親と僕。偶にいっしょに飯を食う。長閑だ。
「生まれただけでいいと言ってくれたんで、余計なことをしなかった。半世紀経ったら、違うことを言いたくないか?」
「うん」
「死ぬだけでいいというフレーズを思いついた」
「ブラックジョークか。まあまあの出来。僕らは草太に満足している」
頷いている母。
「僕も気儘を通した。でも気が付いたら、人生の後半、死ぬまでの道連れがいない。あなたたちのようになれない」
「俺たちが幸せのモデルというわけじゃない」
母は雑誌をテーブルに置きルーペを外して暫く僕を視た。柔和な魂の人。
「あなた……欲しがらなかったじゃない」
「……今までは」
「……僕が……大学辞めちゃったときのこと覚えている? 職も恋人もなくした……その子に、逢った……」
二人がちょっと身を乗り出す。
「高谷さんの伝て……逢っただけなんだ。挨拶しただけなんだ……」
「結婚するって……聴いて、辛くなった……若いから、相手も若いだろうね……」
母が立って腰をとんと叩いて背を伸ばし、奥のサイドテーブルからCDをとってくる。デイヴィド・ギャレットのメンデルスゾーンが流れ出る。母の子守歌だったと言う。演奏家は次々変わった。今はこの若きヴィルトゥオソを、なんとつつましやかな、と称賛する。
「草太、人はか弱く作られている。独りだったら生きられない。人を求めるように作られている。求めあって添い遂げることができるのは奇跡だ。僕らは日々そのことを実感している」
寂しくて堪らない。
義兄にわかるだろうか。