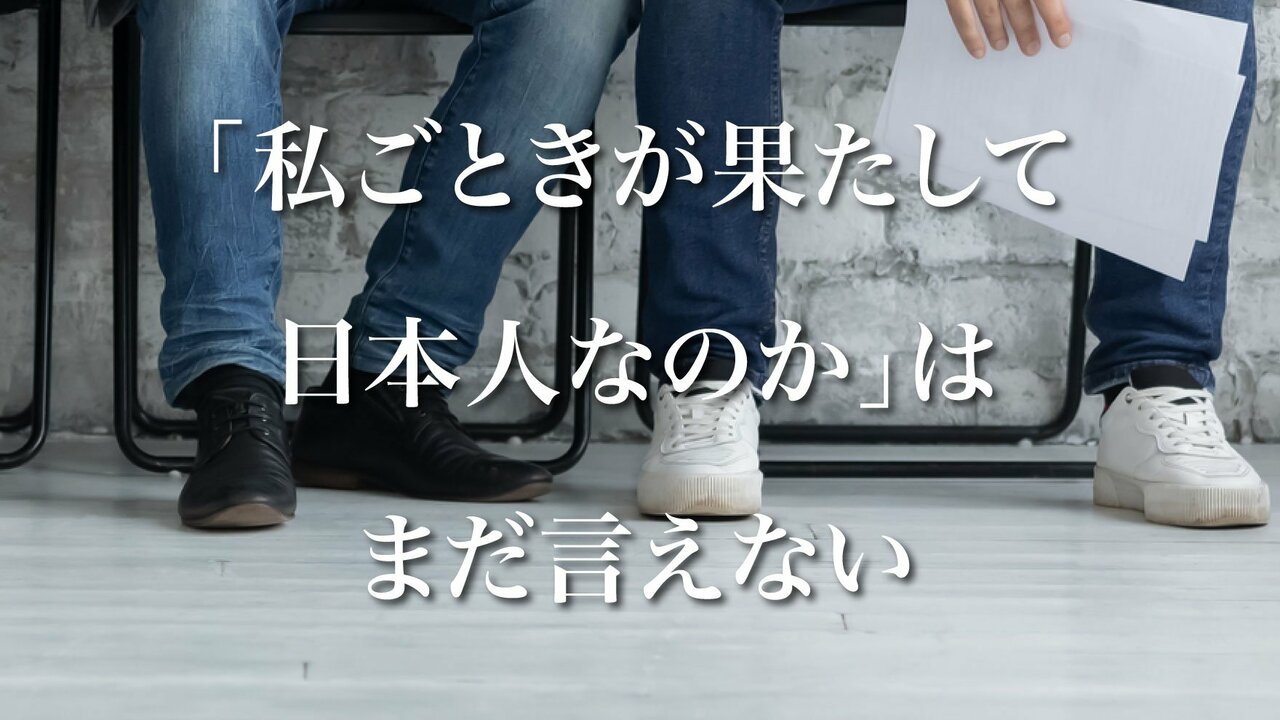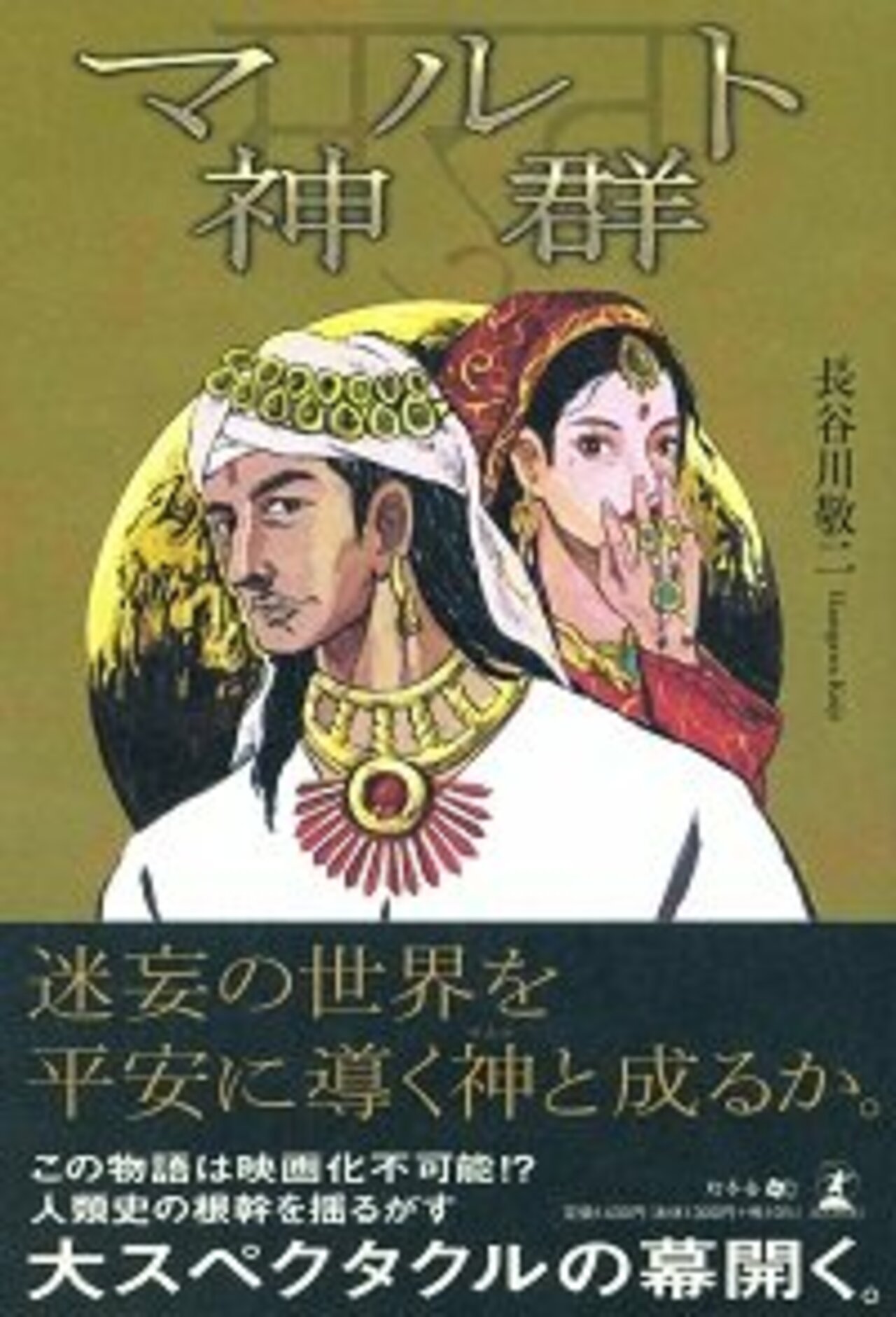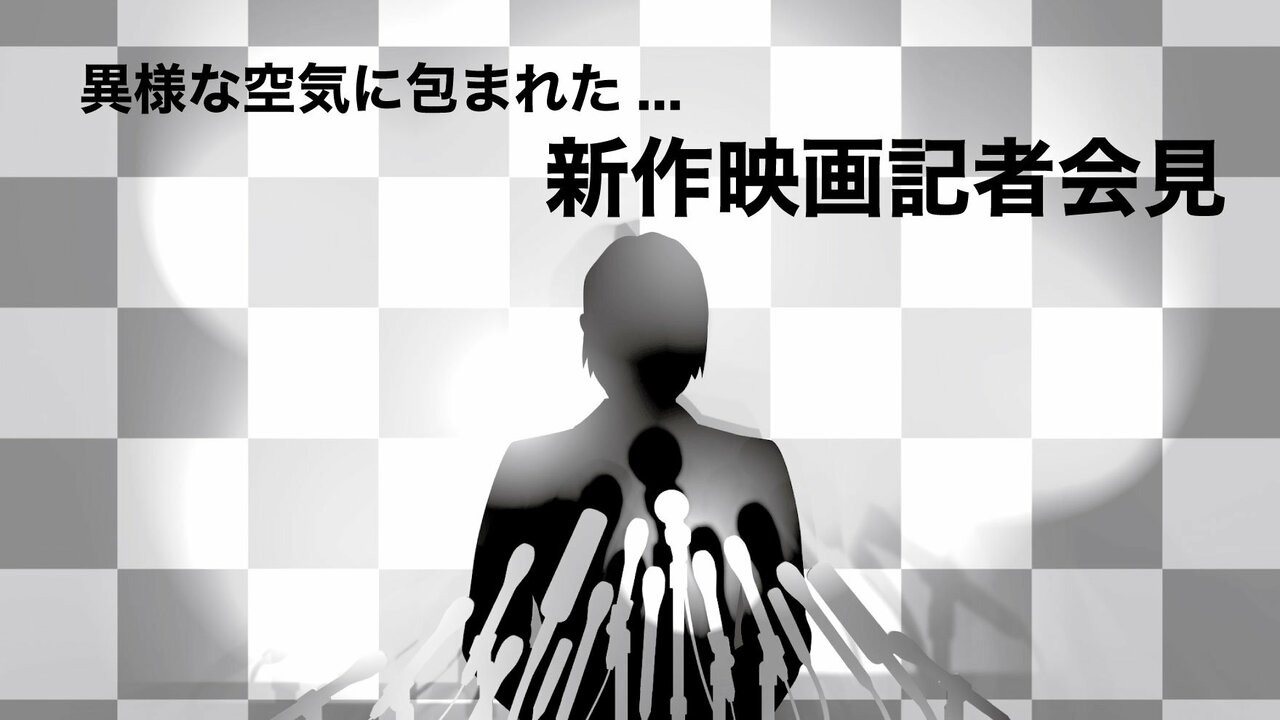第一章 宇宙開闢の歌
部屋の外で足音がし始めた。蓮台がドアに近づき取っ手を回した。
一人の屈強ともいうべき男が部屋に入ってきた。婆須槃頭だった。
普段の姿という言葉から勝手に想像していたよりいで立ちは、はるかに奇妙なものであった。インド古来の服装といってよいのか、笹野たちには見慣れぬ、そして何か馴染めない服装だった。
(そうだ。ネルーだ。インド初代首相のネルーのあのいでたちだ)
笹野には合点がいった。写真でしか見たことのないネルーの例の執務服をまとって、婆須槃頭は姿を見せた。ドアを開けた蓮台と軽く会釈を交わし笹野たちに笑みを送った。ハービク所長、涯監督、ハマーシュタインにはいつも見慣れているかのように気軽な、無視でもするような態度だった。ソファに近づき所長に会釈してから座った。頭上の帽子は纏ったまんまだ。ベージュ色の上下はぴったりと四肢に密着し、内部の肉体のたくましさを彷彿とさせた。蓮台が彼に寄り添い、三人のインド俳優は直立したまま彼の後ろに立った。
「結構な映画セットじゃないですか」
ステージに目をやりながら婆須槃頭はつぶやいた。英語だった。
「日本の方々、昨日は時間が短くて失礼をしました。婆須槃頭です。インタビューは今からやり直しということでよろしいか」
今度は日本語で笹野たちに繰り出された。
「ここにおられるお三方は皆私の同志だ。そして、背後の三人は皆私の分身といってよい男たちだ。皆、地道によく働いてくれる。そして彼女、宮市蓮台は私が身をもって庇護する、かけがえのない存在といってよいだろう」と、畳みかけるように紹介を終えた。
この会見場所の主が移り変わったと認識せざるを得ない瞬時の変化だった。笹野は先ほどまで高説を聞き出していた三人の変化を観察した。明らかに皆一様に婆須槃頭に気後れしだしていた。特に注意を引いたのはハマーシュタインだった。先ほどの笑みは影を潜め、何か後ろめたささえ感じる暗い表情になっていた。
婆須槃頭はそれを見逃さなかった。