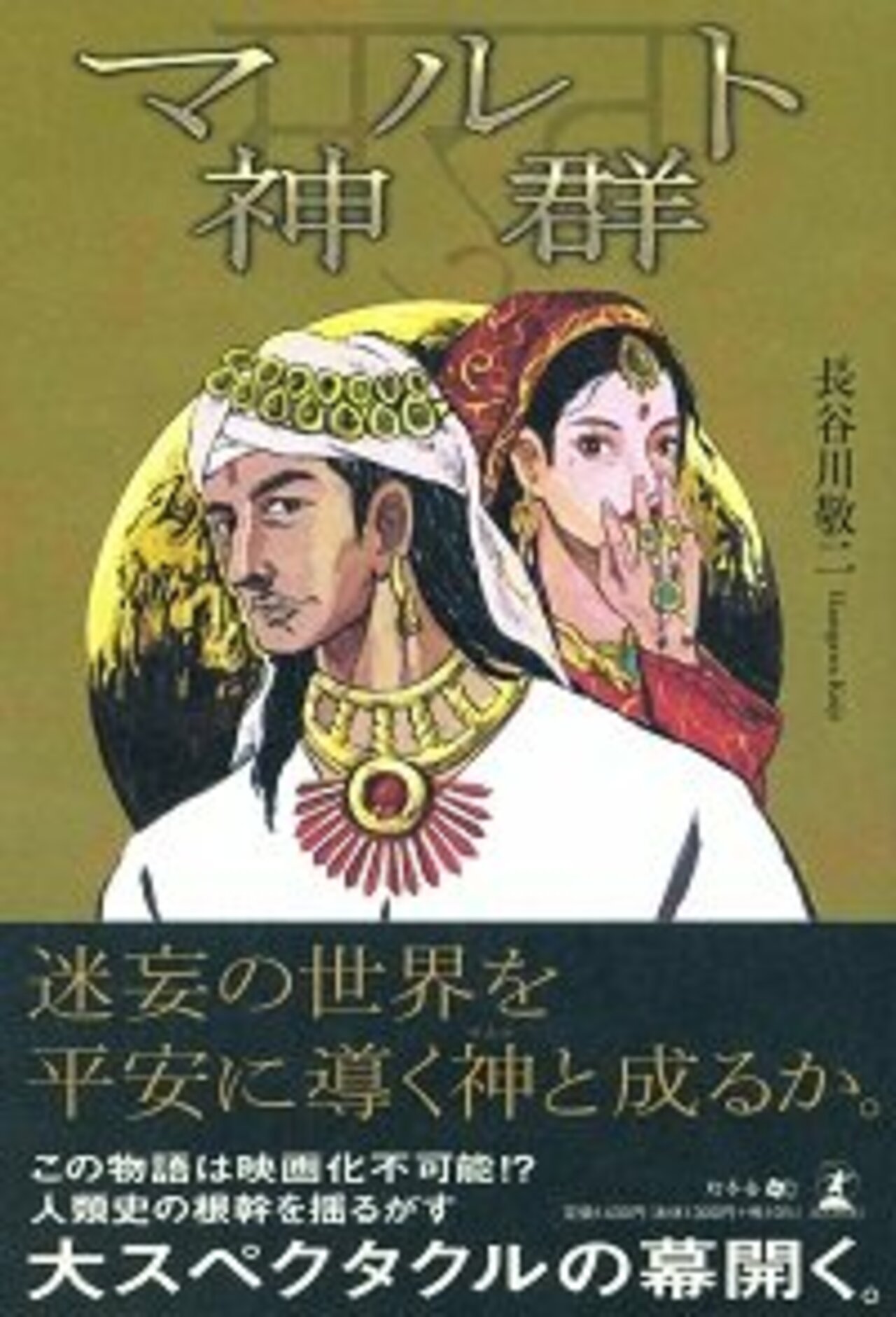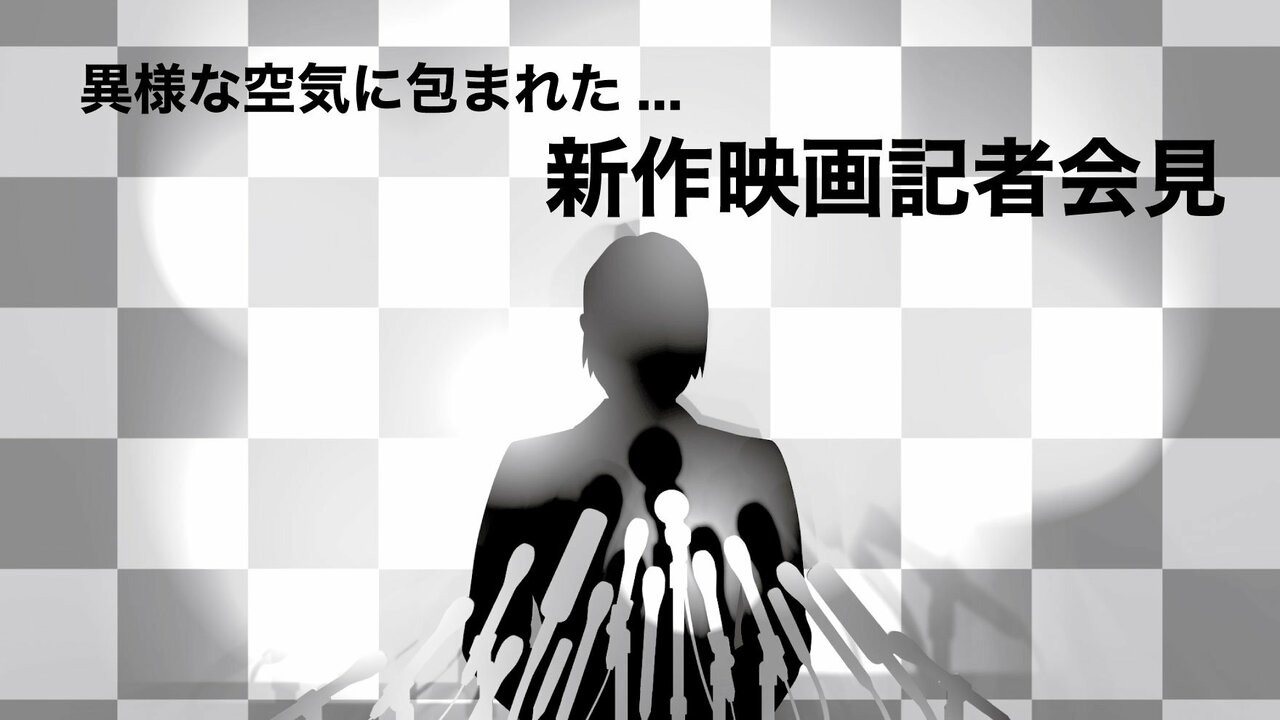第一章 宇宙開闢の歌
映画は非白人国家だけの国際会議の日本の立場も克明に描く。
主権主権を回復したもののアメリカを常に意識せざるを得なかった日本は、第一回会議への招待に果たして参加してよいものか苦悩する。
インド、中共、エジプトなどがいずれも国家首班級の人物を送り込んでくる中、日本は高碕達之助経済審議庁長官を代表として外務省の参与十数名などといった人選で体裁を地味にして参加する。
しかし彼らは現地で大歓迎を受ける。「よく来てくれた」「こうして独立できたのは日本のおかげだ。感謝する」「日本が戦わなかったら我々は依然植民地のままだったろう」などと有色人種の各国から歓迎攻めにあう。しかし、日本や欧米のマスコミは冷ややかにそれを無視する。会議に参加できなかった韓国の記者などは、
「日本はアジア諸国を侵略した当事国ではないか。なぜそのように歓待されるのか」と不満と疑問を口にする。戦勝国史観と李承晩大統領の徹底した反日教育に染まってしまった悲しむべき姿だ。
日本が戦ったのはイギリス、オランダ、フランス、アメリカなどのアジア植民地の宗主国だった。植民地にされていたアジア人を宗主国から解放し、独立自尊の気構えさえ教えていったのである。戦後も日本に戻らず、独立戦争に身を捧げた日本兵たちも何千人といた。特にインドネシアでは、ムルデカ運動として顕著であった。
やがて映画は脚本に若干の手直しはあったものの、ほぼ涯の見込み通りの形で完成した。しかし、興業的には失敗だった。
落胆する涯をハマーシュタインは励ました。
「君はかってイスラエルのモサドに命を狙われたことがあったそうじゃないか。ユダヤ人の俺は君の無実を信じる。どうにも日本人は好奇心が強すぎて無邪気に敵をこしらえてしまうところがある。君に今必要なことは日本人に感謝できる人と、場所を探してみることだな。それができたらまた俺のところへ戻ってこい」
やがて涯はアメリカを発ちアジアへと向かった。
自分の書いたシナリオに不備なところは多々あった。その不備をどうしても正したいという抑えがたい気持ちがアジアへと向かわせた。第二次大戦後、アジアの映画は急速に変貌を遂げていた。
涯はその動きそのものを克明に辿っていった。
「私は東南アジア中を見て回り、またインドネシアに戻ってきた。インドネシアは東南アジアの最南端に位置した東西に長い弓状の国である。十七世紀からのオランダの植民地を経て、第二次大戦後の独立を勝ち取り、現在は世界最多のイスラム教徒を有する、イスラム過激派の活動が著しい国である。首都ジャカルタ、ここに起居し始めてから私の近辺に様々な人種の人間が往来し始めた。それぞれの人種模様が私には興味深く、頭の中に様々なドラマを構築しては、一人悦に入っていた。
ある日のことだった。一人の日本人男性が私を訪ねてきた。三十代前半とみられるその男は名前を尽条彰だといった。今考えるとその男は奇禍と喜福を同時に運んできた一種得体のしれない異人種だった。その男は私にしきりにインドに行くことを勧めた。インドに行くことだ。そこで映画を通じて君の可能性を図ることだ、と」