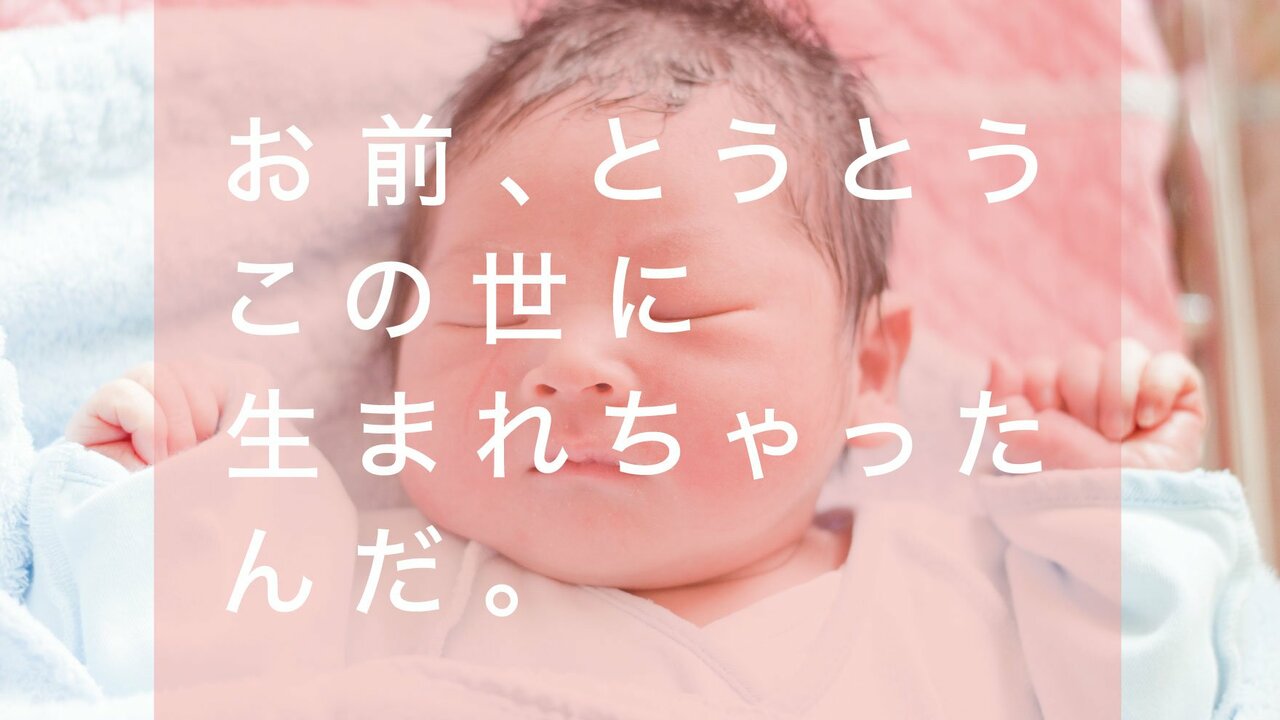「団地に住んでいた。よく泣く弟がいた。あいつ、最初の記憶は兄ちゃんが誰かに殴られている場面だと言う。屈辱だ。初めにいっしょにいたのは母方の祖父母だった。悲しそうで、僕らを可哀想に思ってくれていた。あとからの編集だが。
ある時、真っ赤な服を着た女が白っぽい車で知らない男と出て行くのを三階の窓から見ていた。そこから僕の不幸が始まった。飢えと弟の小便とうんこ、時々僕のも。濡れて悪臭のする布団に二人で寝た。
冷蔵庫を食い尽くし、パックのご飯をレンジにかけずに食って腹を下した。団地をうろついて他所のドアから宅配の弁当を盗んだ。コンビニで万引きしては捕まって大人たちから折檻された。親を捕まえたくてもいないから。いつも弟と二人組だったが、僕が主犯だ。弟、三つ下。餓鬼らまで追っかけたり突き飛ばしたりして嗤うんだ。除け者の壁が僕らを囲っていた。
一人、知らない優しいおばさんが握り飯をくれて、家に来て電話してくれた。施設に行くことになった。あとで知った事だが、おばさんは施設に行かなくて済むように親身に手を回してくれていたんだ。施設から迎えが来た。死に物狂いで抵抗した。危機一髪だった。
僕らは父方の祖父母の家に引き取られて、あの工房だよ。学校に上がった。事務所にいる、あれが僕の親父。長距離トラックに乗っていたんだ。景気も良くていい稼ぎだったんだって。滅多に帰ってこなかったが、帰ってきたときは土産が派手だった。記憶じゃそんなことが一度はあったような気もする。
思い出せない。母親は浮気して、僕らを置いて駆け落ちしちゃったんだ。爺ちゃん婆ちゃんは息子を叱ってとうとうトラックから降ろして堅気の職に就かせた。工房の跡継ぎさ。堅気って、どこか可笑しいだろう。とにかく団地では悲惨だった。正統のレ・ミゼラブル。不思議だ。もっと取り乱すかと心配だったけれど、割と平気で話せた。あのおばさん、恩人だけど、どうしたかなあ」
淳は堪えて聴いている。そっと首に腕を回して涙ぐんでいるので話す方も泣きたくなった。兄貴が不甲斐ない弟を可哀想で。
あいつは今でも家族以外とは話せない。吃るんだ。だけど、親父からは愛されている。親父は僕にはなんか打ち解けない。弟を護ってやれなかった兄だからね。弟は小さ過ぎて自分の悲惨を覚えてない、幸いなことに。だけど僕は引け目を感じる。どうしても。僻ひがみも。しょぼいけれど。美大にやってくれたし、アパートの一人暮らしを許してくれたっていうのに。弟? 太洋。ほら、入口に近いところでバーのカウンターの飾りを彫っていた奴。器用だ。コンマ一ミリでやれる。よく働く。素直だ。
「八汐くんも素直で……正直で、弟思いで、偉い」
「……正直じゃない……今の話は嘘じゃないけれど……僕は嫌われるね?」
「大好きよ」
淳の口調は八汐に自信を呼び起こす。
「僕を泊めてもいい?」
「それは……いいけど、今夜は……無理」
眼の奥を覗き込みながら唇を重ねる。
「その目が鬱陶しい」
「いやらしい、だろ」
「そう」
「そうだもの。情欲が燃え上がってる。ほら」
「そんな言葉、使うの……ふだんは……夜、一人で何している?」
「……あなたのことを想っている……あなたと知り合う前は、映画ばっかり観ていた。気が塞ぐと、夜中の街を放っつき歩く……」
「二人で放っつき歩く?……でも離れ方が難しいかな」
「あなたを送ってきて……やっぱり一人で帰るしかない」