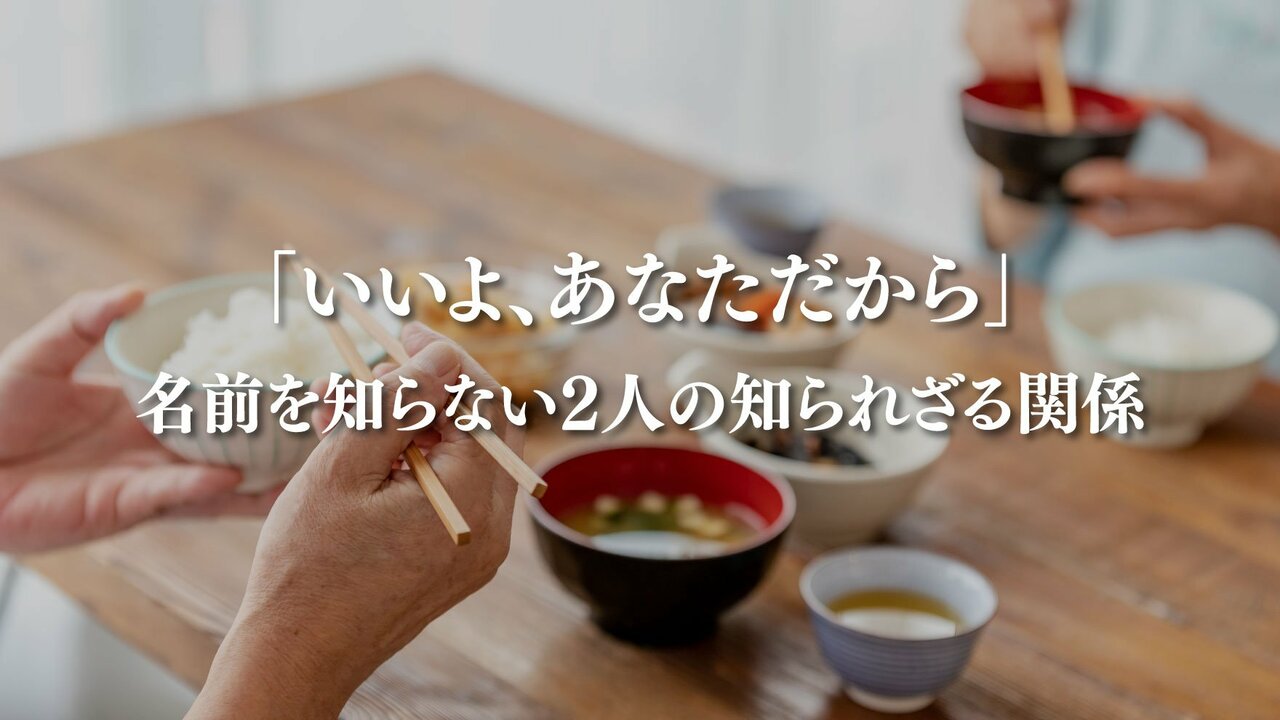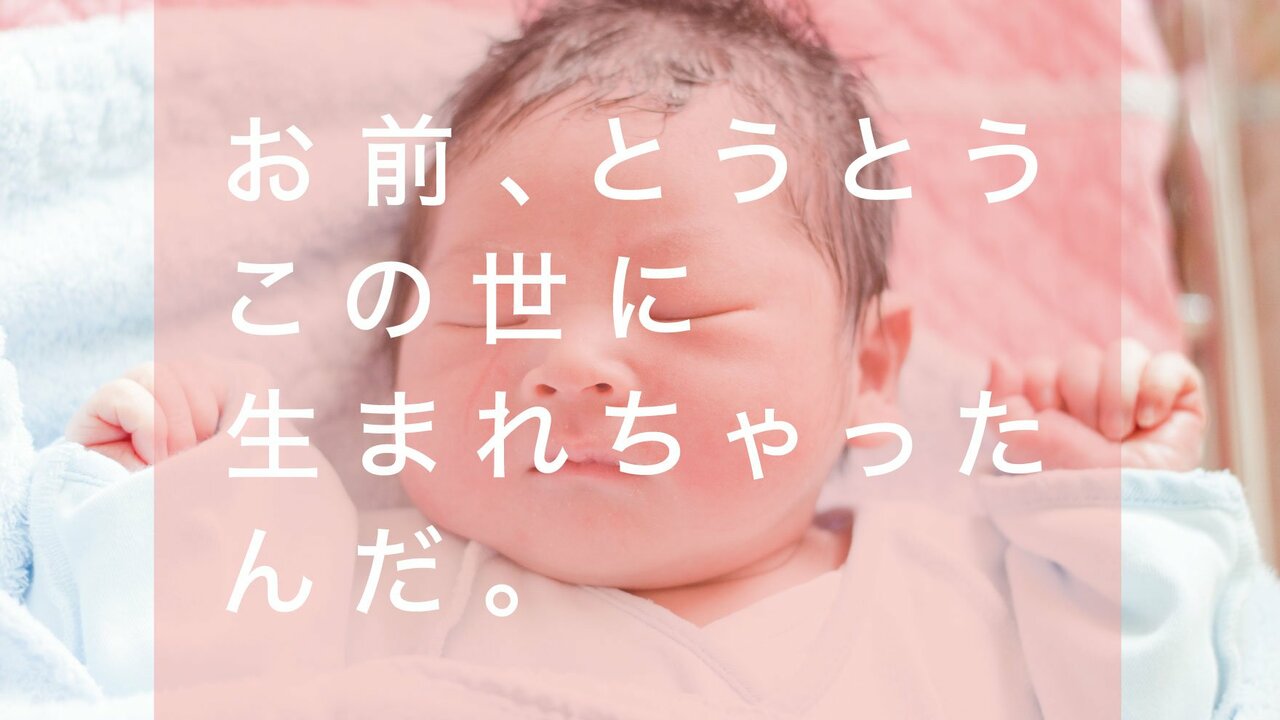『こまち』
さて、こちらの若者は保健所の駐車場で約束の女性が傘を差そうとしてロマンスグレーの男と内緒話に時間を取り、男は蝙蝠 を開いて黒のプリウスへ、女は機嫌よくこちらの助手席に収まるまで眼で追って心穏やかでいられなかった。長い手足と身の丈を持て余して所在なくポケットに手を落とすような塩梅で、かつて彼女の憧れた男性像から外れてどこか頼りない、優し気だがとてものことにエスコートにならないが、駅ビルの十階に上がるエレヴェーターで「足は?」と気遣いを見せる。
「……ふやけた。嘘。忘れていた。でも座敷がいい」
「……本当は早く帰りたい?」
「……ゆっくり食事……が済んだら、眠気が来ないうちに帰る」
朗らかに応じる。座敷で天ぷら御膳。差し向かいで。彼は左手で箸を使う。彼女が筍 の穂先の天ぷらを喜んで口にするのを箸を止めて視ている。旬の物。刺身ももずくも。なんでも器ごとおいしい。なんだってこの人はこう愉しそうなのだろう。聞こえたように
「空腹が最高のアペリティフ。一人の食事はただの燃料チャージだから」
「……あなたは、一人なの?」
「だから、こんなことも。なんとも自由。良いこと尽くめじゃないけれど」
若者を年下扱いだ。事実だろうが、あしらわれている。いいよ、あなただから。胸内で昂然とする。閑散とした木工所でコンマ五ミリを削られたウォルナットの板を見た彼女と眼が合った時の、もしその無口に言葉があったなら、春浅い路傍の陽だまりで高いところから降ってきた一粒の光と戯れるはこべを見つけた、見つかっていっしょに笑った、そうだったろうと確かめる蛮勇がなかったんだが。
「これで、美味しいお酒が少し、あれば完璧」
全く。
「ううん。言ってみただけ」
今日は完璧な偶然。
「あの板、あなたがどう使ったか、見たい」
「そ? どうぞ。晴れた日に」
「……今日の雨が、嬉しかったの、僕だけだ」
「わたし、嬉しそうじゃない? あなたが迷惑そうじゃなくて……無理してなければだけど」
駅前からバスも不便じゃないが
「約束だから送らせて」
仄暗い住宅街の木立に囲まれた平屋。玄関先の小さいプレートに『こまち』。眠りに落ちながら、名前を知らないことが可笑しかったり、聴きたい言葉、言ってほしい言葉があったように思ったりした。