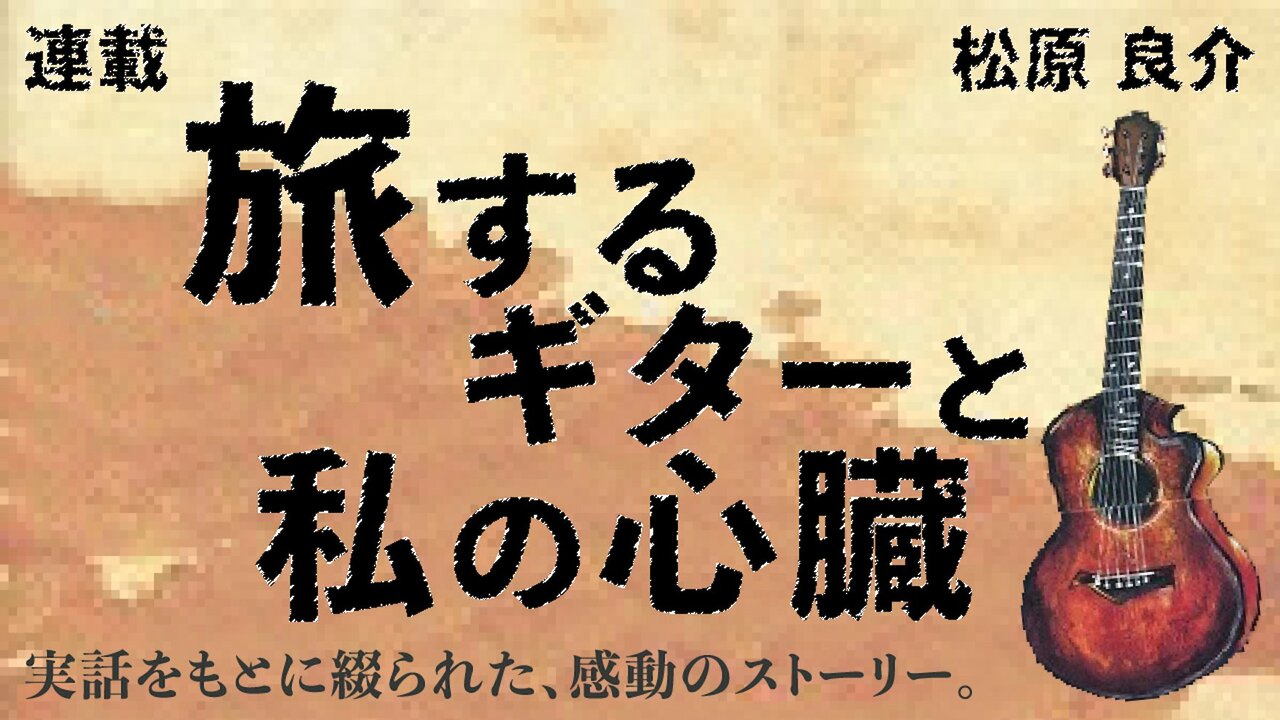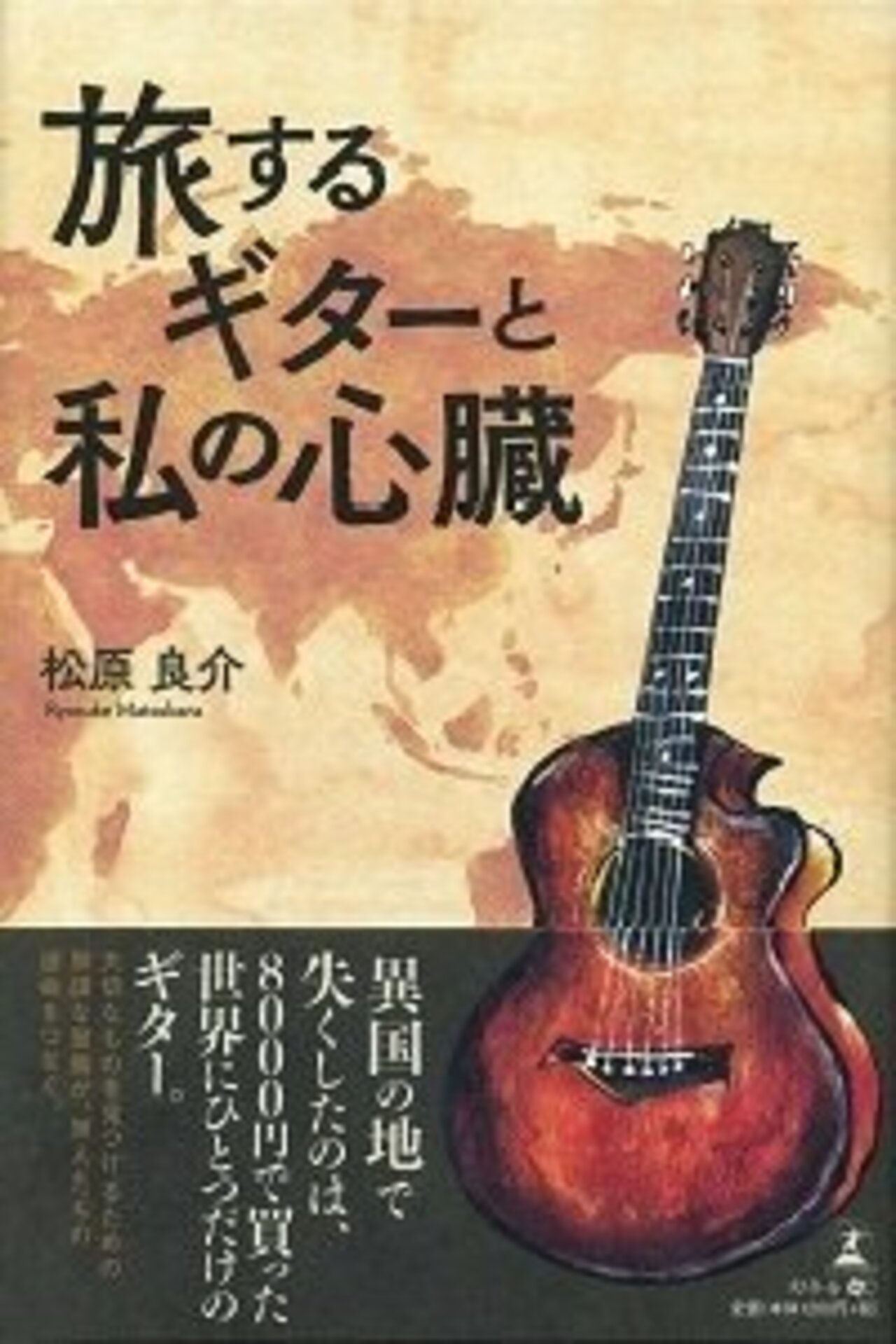彼の生き方を見て、「寝る場所は?」「風呂は?」「お金がなくなったらどうするんだ?」「安全なのか?」と、私はあれこれ想像しながら気持ちを高ぶらせていた。この無謀な冒険を綴った安藤のブログは、「旅人」ジャンルのブログランキングで2位以下を大きく突き放して1位を独走していた。
旅を開始したときの所持金はポケットに入っていた6000円のみという馬鹿げたもので、ヒッチハイクで知らない土地を周り、その日出会ったばかりの人の家に泊まったり、家がないときは公園で野宿をした。
そんな彼の旅は1年以上も続いていた。
私はリアルタイムで彼の旅を追うようになり、ブログが更新されるのを毎日楽しみにしていた。ユーモアに溢れた彼のブログを読んでいるときだけが、何事にもとらわれず安心して過ごせる時間だった。安藤の制限のない生き方は、今の私とは対極にあり、住む世界が違うとはまさにこのことだと思った。
私はペースメーカーが埋め込まれた左胸の上に、そっと右手を置いて目を閉じた。
安藤に自分の姿を重ね、自分が異国の路上でギターを弾く姿を想像した。
からりと晴れた空に雲はなく、その空は青く青くどこまでも続いている。気に入った街をみつけて、人通りの多い路地に腰を下ろす。ギターを弾きながら歌う自分の目の前を、さまざまな人種の人々がこっちをちらりと見ては通り過ぎていく。
やがて一人が足を止めると、一人、また一人と自然と人が集まってくる。自分の前には、小銭が入ったギターケースがあり、足を止めた欧米人が小銭を入れてくれる。
想像する旅のイメージは、私のもどかしい気持ちにほんの少しゆとりを与えたが、やがてそれが不可能だと考えるようになると、ぐったりするような倦怠感が身体を包んだ。
ブログに書かれる世界は私にとって決して届かない場所にあった。
入院して3週間ほど経った頃から、私は院内にあるカフェでほかの病室の患者たちと話すようになった。その頃になると見舞いに来る友人たちも極端に少なくなっていたので、院内で毎日のように顔を合わせる人たちと仲良くなるのは必然だったのかもしれない。
いつもグループの中心にいる西川という50歳半ばくらいの男性は、肺が悪いらしく、2年以上も入退院を繰り返している。彼は長老のような存在だった。
さっき通った先生とあの看護師はデキているとか、先週個室病棟に入院してきた若い患者は政治家の息子だとか、この病院の裏事情まで知っている。落語家のような西川の話は聞きごたえがあり、彼の周りにはいつも日替わりで人が集まっていた。
「お前さんは退院したら何がしたい?」「俺は来年の春に沖縄に行くんだ」
彼はいつも毒づいた口調で、ぶっきらぼうに未来の話をした。
私はここに来れば何かきっかけがつかめる気がしたので、どんなに気が乗らなくても毎日カフェに足を運ぶことを心掛けていた。
集まってくる人たちのなかには自分よりも若い人もいて、その病状は自分よりもはるかに重い人もいた。彼らは制限された生活のなかで自分と向き合い、前向きに生きている姿を私に見せてくれた。彼らに比べたら自分はまだマシなほうだった。自分の足で歩けるし、食事もできるし、会話もできる。やりたいことができる幸せを思い知らされたものだった。
自分が置かれている状況に対して悲観的になってしまい、つい見えなくなっていたが、自分にはまだ可能性に向かう力が残されているように思えた。同じ病状で孤独と戦い苦しんでいる人たちのために、自分ができることはないだろうか?〝今の自分にできること〟は何だろうか? それはシンプルだが、健常者であっても頭を悩ませる問題だった。
ある日、西川は突然ほかの病棟に移された。
彼の毒づいた話が聞けなくなるのは残念だったが、西川のおかげでカフェには定期的に人が集まるようになっていた。そして皆は西川が病棟を移された理由を、看護師に手を出したとか、先生に悪態をついたとか、適当な噂を作って楽しんでいた。同じ境遇だからこそ話し合える彼らとのこの時間は、私にとって大切なものになっていた。
カフェから病室に戻ると祐介が来ていた。
病院が教室からそれほど離れていないため、祐介は仕事の合間にふらりとやってくる。
「こいつは本当に予定がないのか?」と心配になるほど、祐介は暇さえあればよく見舞いに来てくれた。
毎度彼が見舞いと称して買ってくるドーナツは、私の好物であったが、食事制限のある自分の口に入ることはなかった。祐介はそれを知っていて買ってくるのだからあきれて笑ってしまう。
「なぁ祐介、俺って今何ができると思う?」
私はドーナツを頬張る祐介に向かって唐突に聞いてみた。祐介は口にドーナツを咥えながら、手についた砂糖を袋のなかで落とすと、
「あー、何だろうなぁ。そんなもん俺が聞きたいよ」
と言った。私の突拍子もない質問に困る様子は見られなかった。
私は別に何かいい答えを期待したわけではなかったが、少しだけ残念に思った。すると祐介は視線を落としながら、差し入れで持ってきた文庫本を特に読むわけでもなくペラペラとめくり始めた。
「でもさ、お前って人に何かを教えるのってうまいよな、そういうのは向いていると思ったよ」
祐介はぶっきらぼうに言った。私は、「え?」と声を漏らした。
「ほら、お前って頭いいけどそんなに器用なほうじゃないじゃん?」
「うるせーよ」
私がそう言って割って入ると、祐介は安心したように笑いながら続けた。
「正直言ってお前って『講師』って感じしなかったからさ。何ていうか、その……最初は大丈夫かなって思っていたんだ」
祐介はそう言って鼻先を掻いた。
「でもさ、いざ始まってみると子どもとか大人とか関係なく器用に教えてるお前を見て安心したというか……感心したんだよ。やりたいことを見つけて実現に向かってるお前を素直にすげーなって思った」
祐介は持っていた本をテーブルの上に置くと、それを丁寧に整える仕草をしながら言った。
「なぁ、ずっと聞きたかったんだけどさ」
祐介が声のトーンを変えて言った。
「最初、お前が俺のところに来て講師が足りないって誘ってくれたの、あれ嘘なんだろ?」
「何でそう思うんだ?」
ストレートな質問にドキッとしたが、私は慌てず返事を返した。
「だって、どう見ても講師は足りていたし、俺みたいな素人を入れる必要なんてなかったはずだよ。支払いだってキツかっただろ?」
「そうかもな」と私がごまかすようにそう言うと
「そうかもな、ってなんだよ」
と祐介は苦笑いを浮かべて言った。
「別にいいだろ、うまくいったんだから」
「うまくいってねーじゃん」
祐介がベッドの上の私を指さして言った。
今、教室は新規の生徒を断り、レッスンも縮小している。
私が倒れてからしばらくは大谷となんとかやってくれていたが、やはり運営までは厳しかったようだった。
おそらく私が復帰しても以前の状態には戻らないだろう。
そのあと、問診に来た看護師がかわいいとか、12階のナースステーションにもっとかわいい子がいるとか話題は変わったが、そんなに盛り上がらなかった。
「時間大丈夫か?」
時計を気にし始めた祐介に尋ねると、
「そうだな、そろそろ行くよ」
と言って席を立った。私が見送ろうとすると、祐介は、
「そのままでいいよ」
と迷惑そうな顔で言った。祐介はいつもこうやって帰るのだ。私は気遣うことなくベッドの上から手を挙げた。
「じゃあまたな」
と、いつもならそのまま去るはずの祐介だったが、その日は病室の赤いラインの前で立ち止まった。
「どうした?」
祐介は足元のラインをじーっと見つめていた。
「忘れものか?」
と声をかけると、祐介は思い出したようにこっちを振り返った。
「さっきの話だけどさ、結局音楽じゃないの? お前にできるのってさ」
祐介は笑ってそう言うと、
「元気になったらまたやろうな」
と言い残して出て行った。
まんざらでもない顔で祐介が言い放ったその言葉は、それからしばらく経っても私の胸に残っていた。モヤモヤしていた気持ちのなかにわずかながら光が差し込んだようだった。彼の残した言葉は決して答えなどではない。しかし、まぎれもなく私の気持ちを押し上げるものだった。生きるというシンプルな目的のために必要なのは、こうした未来へ向かう活力なのだ。
その日から私は計画を練った。
できることは限られている。だからこそ私に迷いなどなかった。