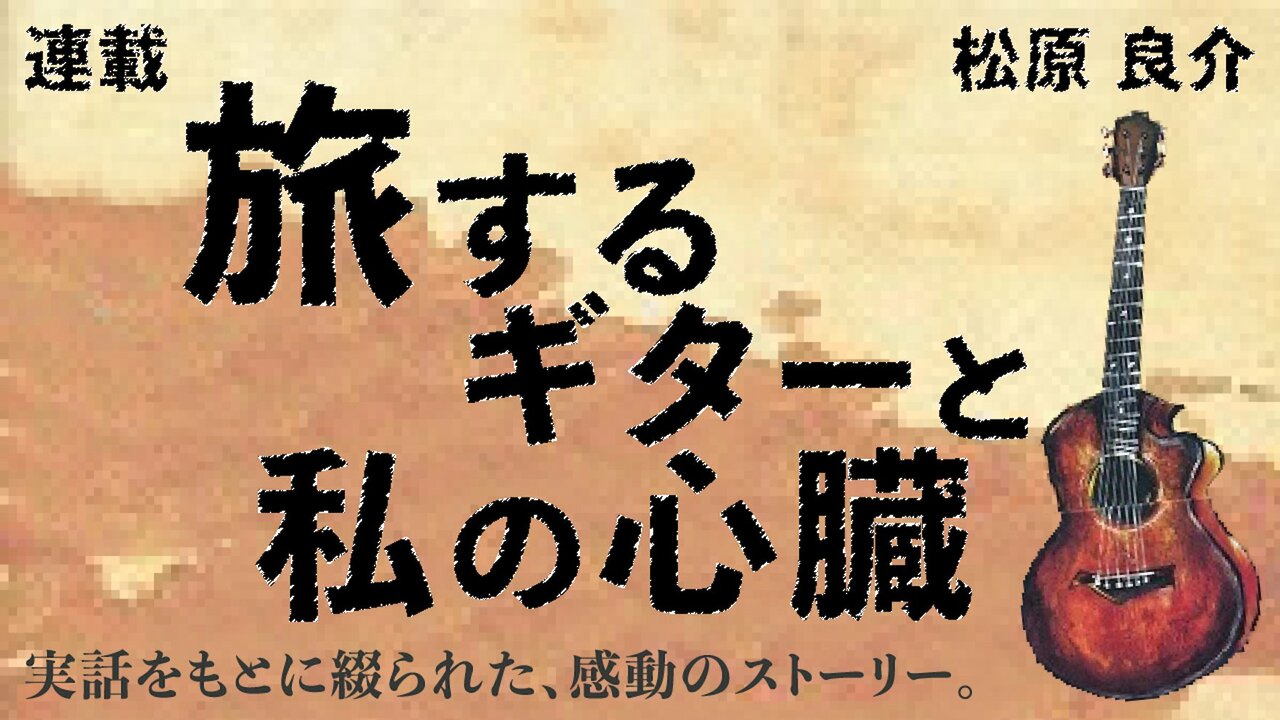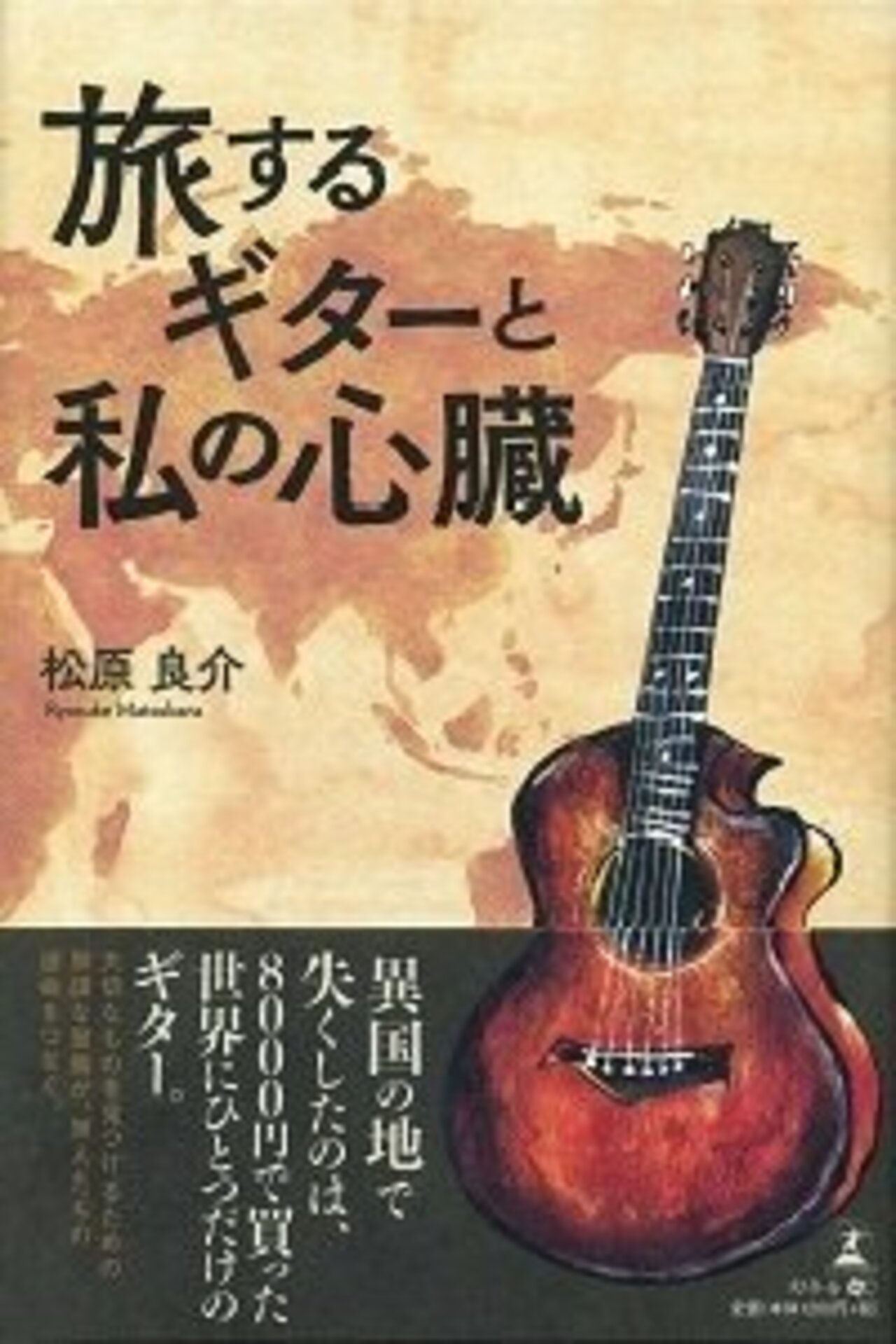私の名前はデイジー(チソン)
彼女の名前はハン・チソン。男みたいな名前だ。韓国で与えられたこの名前を、チソンは久しく使ったことがない。
大手家具メーカーの社員だった父が、横領の罪で有罪の判決を受けたのは、チソンが12歳のときだった。スキャンダルを好むマスコミが自宅や学校にまで押し寄せ、仲の良かった学校の友人や近所の人たちも冷ややかな目でチソンたちを見るようになった。
やがてそれがエスカレートすると嫌がらせやいじめに発展していった。
そんな生活から逃げるように、チソンは母と姉の3人で祖母のいる田舎に移り住んだが、そこでも噂はすぐに広まり、結局同じように犯罪者の娘として酷い仕打ちを受ける日々が続いた。それから名前を変えたり、何度も引っ越しを繰り返したが、すぐにマスコミが嗅ぎ付け、周囲に素性を知られるというイタチごっこが続いた。
もともと美容師だったチソンの母は、人前に出る仕事を避けるようになった。慣れない清掃員や工場での軽作業で生計を立てるほかに選択肢はなく、一家は幽霊のように細々と暮らしていた。守ってくれる大人も、相談できる友人もおらず、まだ幼かったチソンにとってそれは辛い日々だった。
それから数年が経ち、生活が安定し始めた頃、姉のソミンがアメリカの大学に行くことを母から聞かされた。姉を慕っていたチソンにとってそれは衝撃的な出来事だった。
ソミンはいつもチソンのそばにいてくれた。いじめに苦しんだときも、大人たちから嫌がらせを受けたときも、いつもかばってくれた。そんな唯一心を許せるソミンが、何の相談もなしにこの家を出ていく決断をしたことを、チソンはどうしても受け入れることができなかった。
それは自分たちを置いてこの地を離れる姉に対して、わずかながら裏切りに似た気持ちを抱いたせいもあったのかもしれない。なんにせよ、それからしばらくソミンとチソンはぎこちない時間を過ごした。
ソミンはことあるごとに、妹に気を遣っていたが、このときうまく接する術を知らなかったチソンは、つい姉を傷つけるような態度を取ってしまった。
渡米当日に母と二人で見送ったとき、空港でソミンはチソンを抱きしめながらずっと泣いていた。それは今まで誰にも見せたことがないような類の涙だった。相談相手もいないソミンが人知れず悩み、決断をしたことをチソンは、そのとき思い知った。
チソンは後に母から、ソミンは家族を呼び寄せるためにアメリカを選んだということを聞かされた。
その後、チソンは母と二人で新しい街に移った。引っ越した先は小さな古い家だったが広いキッチンを母は気に入ったようだった。キッチンの小窓から見える庭に白い雛菊が揺れていた。母はいつもそれを摘んで花瓶に挿していた。人々が話題にしなくなるくらい時間が経っていたせいか、その地には父の事件のことを知る人間は見当たらず、チソンたちの生活にようやく平穏が訪れていた。
ソミンがアメリカに旅立った一方で、チソンは家を出ることができなかった。
母の身を案じたということもあったが、チソン自身に一人で新しいことにチャレンジする勇気がなかったのが一番大きな理由だった。
なんとか素性を隠したまま大学を卒業したチソンは、そのまま移り住んだ街の旅行代理店で働いた。海外旅行専門の窓口を希望したのは、それが自分にできる精一杯の挑戦だったからである。
旅行代理店に入社してすぐに、海外研修で訪れたタイは、チソンの人生を大きく変えるものだった。そこはまるで映画のなかに紛れ込んだような異世界で、初めて自分の国を出たチソンの目に飛び込んできたものは、どれも刺激的に映った。
とくにチソンはバンコクの雰囲気が気に入り、研修が終わった後も連休を利用して何度も訪れていた。外に出たがらない母を無理やり説得して、一緒にバンコクを訪れたときには長年酷使してきた母の身体を労ろうと、いろんなマッサージやエステを試して回った。
このとき、母が艶を取り戻した自分の肌をさわって喜ぶ姿をみて、チソンは「この技術を学びたい」と思うようになった。いつかアメリカでエステサロンを始めたいと思うようになったのもこの頃からである。
目標を見つけたチソンは仕事をしながら学校に通い、整体や鍼灸、エステの資格を取得した。仕事との両立は大変だったが、目標に向かって没頭できることを見つけ喜びを感じていた。
転機が訪れたのはチソンが25歳になったときのことだった。
知人の紹介により、チソンはチェンマイにあるマッサージ教室でタイ式マッサージを学ぶことになったのだ。しかも家電付きの住まいも用意してくれるという好条件だった。
教室の隣にあるサロンでエステのお店を手伝うことが条件だったが、施術の体験ができる絶好の機会ととらえたチソンにとっては、むしろ好都合に思えた。ただ、母を残して家を離れることに抵抗があったため、なかなかそのことを母に話すことができなかった。
悩んだチソンは、アメリカにいるソミンにこのことを相談した。
「あなたはとても優しい子。でも、それだけじゃ私たちのような人間は生きていけないの。強く生きなきゃ」
その声は電話越しだったが、チソンはソミンに強く背中を押された気がした。
翌日、チソンが仕事を終えて自宅に戻ると、キッチンのほうからいい匂いがした。
食卓には二人では食べきれないほどの料理が並べられていた。ぐつぐつと煮える鍋の音。
母はキッチンで煮物を皿に盛りつけていた。
「今日はすごく豪勢ね? どうしたの?」
子どもみたいにチソンがはしゃぐと、母は嬉しそうに笑いながら、
「タイに行きたいんでしょ? ソミンから聞いたわ。お母さん嬉しくって」
と目元を緩めながら言った。
その顔を見たチソンは一瞬胸が苦しくなった。声が出せずに下を向いていると、母は自分が足かせになっていることを不憫に思っていたと話し、タイに行くことを優しく後押ししてくれた。
それからすぐ、チソンは勤めていた旅行代理店を辞め、初めて異国で生活することになった。出発当日、母は空港まで見送りに来なかった。
「またすぐに会えるから、空港には行かないわ。それに仕事も忙しいし」
母はさらりとそう言っていたが、おそらく涙を見られたくないのだと、チソンは思った。
空港での別れの辛さはソミンのときに知っていた。
バス停まで見送りに来てくれた母は、娘に小さな紙の袋を渡し、「機内で食べなさい」と少し目を赤くさせながら言った。匂いで袋のなかにはチソンが好きな母の焼き菓子が入っていることがわかった。気丈にふるまっていた母だったが、バスの扉が閉まると気が緩んだように泣いていたのがガラス越しでもわかった。母は見えなくなるまで手を振っていた。
一人で海外に行ったことは何度かあったが、チソンは少し不安だった。
《年老いた私のことは気にしないで、あなたの人生を生きなさい。あなたが幸せになってくれることこそが、私の幸せだから》
焼き菓子と一緒に入っていた母の短い手紙には、白い雛菊が描かれていた。母が雛菊を花瓶に挿す姿を思い出すと、その不安はあふれ出す涙と一緒にどこかへ消えた。機内で食べたその焼き菓子の味を一生忘れることはないだろうと、チソンは自らの幸せを誓った。
そしてチソンは目的の土地・チェンマイに到着した。
慣れない土地での生活に最初はいろいろと心配もあったが、暑さにもすぐに順応できた。与えられた部屋は想像よりも狭く、エアコンなどもなかったが、韓国での生活もそれほど安定していたわけではなかったこともあって、それほど苦ではなかった。
そんなことよりも周囲の目を気にすることなく、気兼ねなく生活できることが嬉しかった。マッサージ教室の生徒は日本人が多く、韓国人は自分だけだったが、マッサージ実習のペアを組んだ日本人女性のナツミは韓国に留学していた経験があり、韓国語が堪能だったので、その点はラッキーといえた。
年上のナツミは面倒見が良く、どこか雰囲気が姉のソミンに似ているとチソンは思っていた。チソンとナツミは互いにフィーリングが合い、住まいも近いため、いつも一緒だった。日本人の生徒が多いなか、言葉の通じないことに抵抗があったチソンが輪に入っていけたのも、通訳してくれるナツミの存在が大きかった。
「ねぇ、チソン。ニックネームはあるの?」
ナツミが無邪気に尋ねてきた。
「ニックネーム?」
「そう。ニックネームよ。韓国にいたときは友だちになんて呼ばれていたの?」
友人がいなかったチソンは返答に困ったが、ふと、母が好きだった花が頭に浮かんだ。
「デイジー(雛菊)…」
「デイジー? かわいい名前ね! そっちのほうが呼びやすいわ。よろしくねデイジー」
その日以来、チソンは自らを名乗るときはデイジーと名乗るようになった。
新しい土地で、新しい名前を手に入れたチソンはまるで生まれ変わったような気分と、希望に満ちた未来を感じていた。