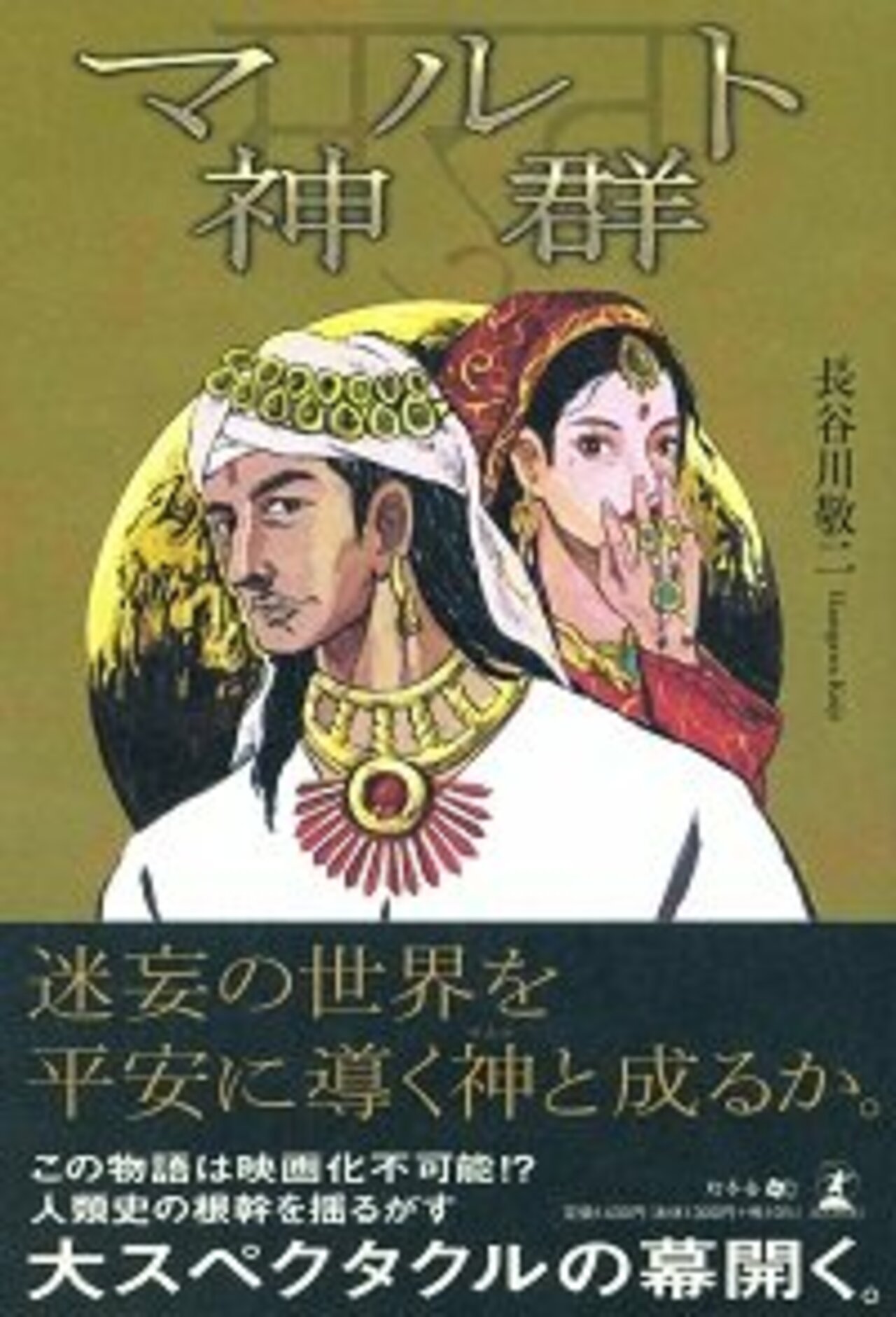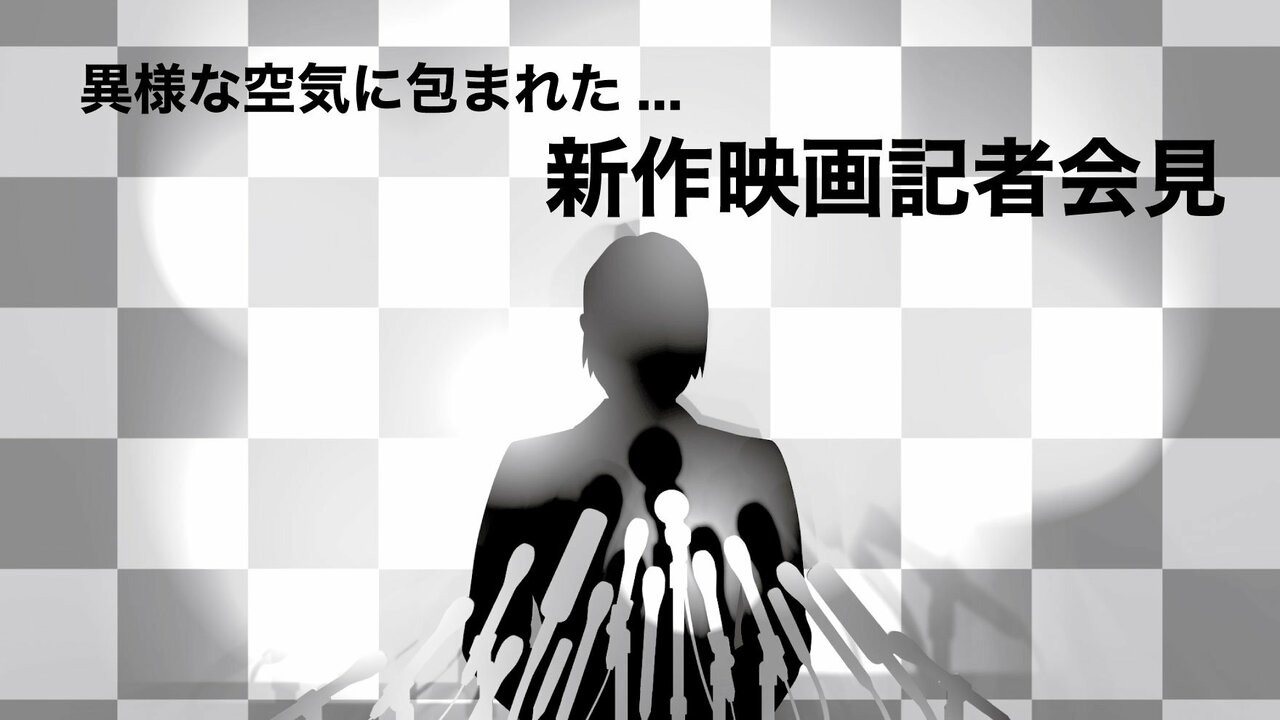コルカタ、かってのカルカッタは、六年の間に変貌していた。笹野は映画雑誌社の記者の内山秀和を伴って、コルカタのスバース・チャンドラ・ボース国際空港に降り立った。二月のことだった。インドの二月は、日本の春のころの陽気と思えばよい。すこぶる日本人の体質に安定感をもたらす時期だ。
空港から乗ったタクシーはクラクションを鳴らしっぱなしだった。道路をタクシーの中から見てみると、なんとも形容しがたい光景に満ちていた。自動車だけでなく、自転車、オートバイク、輪タク、歩行者、それに牛、犬までが我が物顔に道路を占め、歩を進めているのだった。
信号も無ければ、交通整理の警察官もいない。混沌がわずかな規則を遵守しつつも、全てがゆるやかに、しかも喧噪のうちに過ぎ去ってゆく。クラクションの洪水の中にタクシーはようやく撮影所に到着した。
「いやはや、混沌そのものだったな」
笹野はタクシーから降りながらそう愚痴った。コルカタの撮影所は想像していたよりも大きかった。
これまで日本や北アメリカの映画撮影所しか取材経験のない笹野にとって、初めて目の当たりにするインド映画撮影所だったが、スタジオの数、働くスタッフの数など、かって見た撮影所と何ら遜色はないコルカタで作られるインド映画はほとんどがベンガル語映画である。
インド映画とひとくくりにされても実態はそう簡単なものではない。ムンバイ、ひと昔前はボンベイといったその都市で製作される映画、ヒンディー語で作られるそれらは「ボリウッド映画」と揶揄されて世界に広まった。
それからタミル語、テルグ語、ベンガル語と映画で使われる言語によって製作される映画の多様性は、ほとんどがインド国民の娯楽を目当てにしているものだから、汎世界性を有する作品は勢い限られてくることになる。大半がマサラムーヴィーとなって、映画館が庶民のうっぷん晴らしのための社交場とあい果てることとなるのだ。